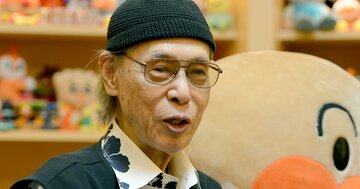『月刊高知』への配属は、やなせたかしのその後の運命を2つの意味で決定づけました。
「編集」のプロになる大きなきっかけとなったこと。そしてもう1つは生涯の伴侶、小松暢と出会ったことです。
紙メディアにおける表現技法を
上流から下流まで学ぶ場だった
『月刊高知』の仕事を通じて、やなせたかしは、「デザイン」と共に後年の彼の仕事の方法論の軸の1つとなっている「編集」を学びました。
「新聞記者として入社したのに雑誌の編集をすることになったのです。表紙からカット、挿絵、取材、座談会の司会、すべてやりました」「広告取りから集金の雑務、原稿依頼もルポ記事も全部こなして勉強になりました」(『人生なんて夢だけど』フレーベル館 2005)
「スタッフは編集長以下4人だけ。絵は描けるわ、文章も書けるわ、で僕に向いていましたね。付録のすごろくまで作った。編集も組み版から何から全部やるので覚えてしまいました」(『やなせたかし メルヘンの魔術師 90年の軌跡』中村圭子編 河出書房新社 2009)
やなせたかしが『月刊高知』に在籍したのは1年ほどですが、ここで彼はアンパンマンに至るまでの仕事の型を獲得します。それは、「編集者」である自分が、「漫画家」「執筆者」「イラストレーター」「デザイナー」である自分に仕事を発注する、「一人雑誌編集部」ともいうべきスタイルです。
『月刊高知』でやなせたかしはすでに紙メディアに求められる表現技法の大半を自分でこなしています。取材・執筆、イラスト、漫画、レイアウト、そして表紙絵も含めたカバーデザイン。さらに以上の仕事を発注する編集者でもありました。
「やさしいライオン」(編集部注/1969年に幼児向け絵本として刊行。やなせたかしの出世作となった)も「アンパンマン」も、ラジオから始まって、大人向けメルヘン、子供向け絵本、アニメーション、映画と、マルチメディアに作品世界が広がりましたが、やなせたかしは人任せにせず、自分自身でプロデュースしました。その根っこにあるのが、『月刊高知』で鍛えられた編集仕事だったことは間違いありません。