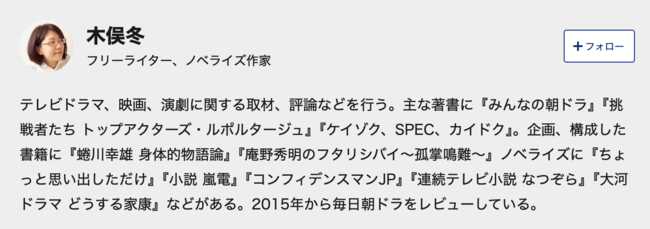ジャーナリズムとは何かを
考えさせられる第68回
このエピソードを現代的な視点で考えると、東海林は意外とデスクワークの人で思想や哲学や理屈が先だって、現実を知らないように見える。物書きが陥りがちなパターンだ。
ただ、戦後間もない時代と考えると、手酷い敗戦という最大級の絶望を経験しているはずなのに、東海林の反応はいささかナイーブすぎるようにも思う。東海林や岩清水は戦争に行ってなくて、温度が違うのかもしれない。
だからこそ、もっと実体験を聞いて、それを記事にしないと、新聞社という守られた場所から見た記事なんて国家の言ってることとなんら変わらないだろう。ジャーナリズムとは何かを考えさせられるエピソードであった。
絶望の隣は希望、と聞いた東海林は闇市の廃品を売ってる店で「HOPE」という名のアメリカの雑誌を買う。嵩が見ていた雑誌だ。売っていたのは健太郎(高橋文哉)。
入れ違いに嵩が帰ってくる。「希望」を嵩とのぶ、2人が東海林に手渡したことになる。
希望の火が灯った東海林は局長の霧島(野村万蔵)に食い下がって行く。こういう寓話的仕掛けは良い。
その頃、朝田家ではメイコ(原菜乃華)が何か希望に満ちた目で蘭子(河合優実)にお金を貸してほしいと頼んでいた。あちこちでちいさな希望の芽がでている。
嵩は、健太郎から、誕生日に万年筆を贈られて、漫画を描くように発破をかけられる。
言われるまで誕生日を忘れていた嵩。彼がぼんやりしているのか、誕生日なんて考えられないくらい絶望していたのか。
橋爪紳一朗の演出回は、画と画の切り替えをカメラの横移動で見せることが時々ある。第67回は編集部内を横移動して部屋の広さを見せたり、第68回はのぶの背中から局長の背中に移動したり。それが特徴的だ。