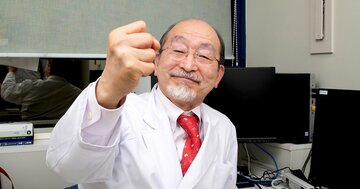黄色腫ができる人は
脂質異常症であるケースが大半
血管内でプラークが出現し、それが破裂すれば血栓ができて、脳梗塞や心筋梗塞を発症する恐れが高まりますが、黄色腫が皮膚の下で破れてもここに血栓ができるわけではありませんから、直接的に体に悪影響を及ぼすことは考えにくいでしょう。
ただし黄色腫ができる人は、悪玉コレステロール値が高いなど脂質異常症であるケースが大半。それも遺伝性の強い、もともと脂質異常症になりやすい体質の人(家族性高コレステロール血症)が多いです。
ヨーロッパの学会誌(「Atherosclerosis」誌)で2017年に発表された論文(※2)では、黄色腫が出現すると、心血管イベントすなわち心筋梗塞などが起こりやすいと報告されています。高コレステロール血症(脂質異常症)の患者102人中21人に黄色腫が認められ、患者らに冠動脈造影CT検査を行うと、黄色腫がある人は冠動脈疾患がより広範囲に及んでいるのです。
悪玉コレステロールが低下すると
黄色腫は縮小する
また、黄色腫のある患者がスタチン(悪玉コレステロールを低下させ、動脈硬化などを予防する薬)を服用し、悪玉コレステロールが十分に低下すると、黄色腫が縮小することもわかっています。
つまり黄色腫が出現するということは体内で動脈硬化が進んでいることを示し、これが小さくなれば体内の血管の状態も改善されているという指標になるのです。
余談になりますが、コレステロールを下げる薬はさまざまにあり、その人に合った適切な薬を処方することが非常に重要です。日本とアメリカではそれぞれ動脈硬化のリスク計算式があり、患者の性や年齢、コレステロール値や血圧などを入力すると適切な薬がわかります。両国の指標を考慮しながら薬を選択すると、薬の効果の過不足といった事態になりにくいと考えています。
そして動脈硬化の進行を判断するには、血液検査の数値だけでなく、「CT検査」「MRA検査」や「頸動脈エコーなどの超音波検査」といった画像診断も大切です。数字的にボーダーラインでも、血管が狭くなっている部分や血栓、潰瘍(かいよう)などがなければ服薬よりも生活習慣改善に力を入れればいいでしょう。
一方で、検査数値はそれほど悪くなくても、CT画像で血管が真っ白(血管の石灰化といわれ、動脈硬化が進行してカルシウムがたまる)であれば服薬が必要です。
さて動脈硬化が起きている可能性が高いサインとして、耳たぶのシワ、まぶたや膝、肘にできる黄色腫を紹介しました。もう一つ、重要なサインがあります。