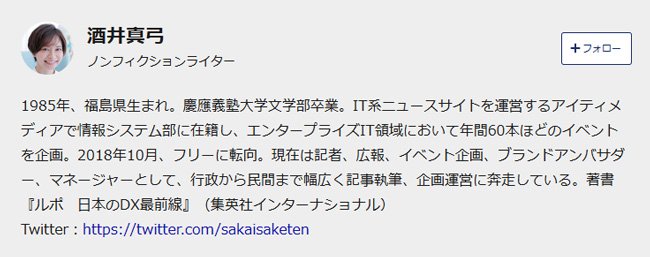開発には苦労もあった。二人はこれまで認証試験に関わったことがなく、その複雑なプロセスを理解するのに難儀した。現地現物の精神で認証試験の現場に入り込み、熟練者たちの協力や助言を得ることで業務理解を深めたという。二人をサポートしたDX推進室長の金允護(キムユンホ)氏も、工場の朝のラジオ体操から参加して信頼関係を築いていった。
また、設備や計測器からデータを取得するにはハードウェアの知識が不可欠で、ソフトウェア開発の知識だけでは対応できない場面もあった。そこで設備メーカーや現場の担当者などと連携し、データ取得のパターンを確認していったという。
現在は10種の試験でこのシステムが適用されている。今後は社内での市民開発を拡大し、約100種ある他の試験への横展開を目指すという。笠原氏と中城氏は「手を挙げる機会がないだけで、デジタルの世界に興味がある人は工場の中にたくさん隠れている」と話す。
「現場の方々は本当に大変な仕事をしています。僕らに対しても気をつかってくれて、『これができたらいいんだけど、無理だったらごめんね』と言ってくれる。だから少しでも皆さんが楽になるように、という気持ちで開発しています」(笠原氏)
現場の社員が自力で業務課題を解決するDX
今回のDX活用事例共有会でもっとも印象的だったのは、現場の社員が自ら業務課題を解決している点だ。DXは往々にして推進側と現場との温度差に悩まされるものだが、ここでは従来のモノづくりに高い専門性を持つメンバーが、AIやプログラミングを積極的に学び始めている。
いいクルマを作りたいという情熱と仲間を思う気持ちで課題解決に挑む姿は、まさにDXの本質と言えるだろう。これが、歴史ある日本企業の底力。血の通ったソリューションが次々と生まれる正体か――そんなことを感じた一日だった。