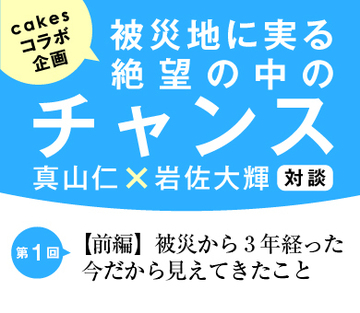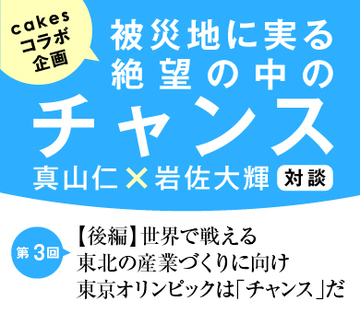――それは本が売れないだけではなく、読者の反響も物足りないということですか?
真山 いや、読者はいるんですよ。編集者や評論家のなかに、専門家、つまりプロがいなくなった気がします。アマゾンのレビューを見ると、読者の方がちゃんと読めてるなあと思うこともあります。本を作る側に、本当に小説が好きな人がどれだけいるのかと、ずっと疑問に思ってます。
バブル崩壊以後、この国を覆っている風潮でもあるのですが、すべては「数字」。売れれば勝ち。結果さえ出ればいい、という考え方ですね。それが出版の世界にも及んで、「本が好きかどうか」ということはあまり関係なくなっている。それは非常に残念です。
真山小説の原点も見られる
幻のデビュー作が待望の文庫化
――では、ここから個々の作品に寄っていきます。まずは“幻のデビュー作”である『連鎖破綻 ダブルギアリング』。2003年、経済小説というジャンルでデビューを飾ったわけですが、その経緯についてうかがえますか。
真山 作家になる前はライターでした。ダイヤモンド社から、ビジネス書のゴーストライターの仕事を受けていたころ、同社で「経済小説大賞」を作ろうという話が出た。ビジネス書から文芸書への進出ですね。その際、ダイヤモンド社も新人作家を発掘していく姿勢を示すために、私に声がかかったんですね。
もともと『ダブルギアリング』の原案は、大手生命保険会社のOBの方が持ち込んできた小説でした。それを「共著」という形で練り直したわけですが、実は私、白状しますと、それまで企業小説、経済小説というものを読んだことがなかったんです。山崎豊子さんの『華麗なる一族』や『沈まぬ太陽』などは好きでしたが、私の中であれは経済小説ではないので、そもそもどう書いていいのかわからない。引き受ける時はかなり悩みました。
――よく「デビュー作にはすべてがある」と言われますけれど、改めて『ダブルギアリング』を読むと、非常に荒削りですが、やはり真山小説の原型が全部入っているという感じがしますね。
真山 それはあると思います。確かに『ハゲタカ』の原型はあそこにある。さらに言うと、『ベイジン』(東洋経済新報社、現幻冬舎文庫)のプロローグも『ダブルギアリング』と同じパターンなんです。まずピンチのシーンから入って、時間をさかのぼる手法。登場人物が追い詰められた中で動いていく設定も、いくつかの作品に共通パターンがあります。そういう意味では原点です。
ただ、当時は「経済小説はお勉強小説」というイメージがあったので、非常に説明過多ですよね。単行本は2段組みだったし、読むのがしんどい(笑)。
――表紙からして暗いですよねえ(笑)。もう絶望しかない感じ。
真山 登場人物がみんな何かを背負っているし、不幸だし、報われない。でも、この小説は乱世で始まった21世紀を象徴する内容で、そういう意味で、私はラッキーだったとも思うんです。
今回文庫で出すにあたって、この作品に関してはある種の記念として、あまり手を入れるつもりはないんですが、『ハゲタカ』の主要人物である鷲津政彦(元ジャズ・ピアニストという異色の経歴をもつ外資系バイアウト・ファンドの敏腕マネージャー)の原型は、『ダブルギアリング』の各務裕之だと言われるかなとは、ずっと思っていました。どこか斜に構えてビジネスを見ていますが、芯は強く行動力もある。芝野健夫(『ハゲタカ』)と中根亮介(『ダブルギアリング』)に至っては、金融機関のエリートとして、ほとんど双子みたいな設定ですからね。
その時わかったのが、「自分は経済嫌いだ」ということなんです。人が作る社会なのに、すべてを数字に置き換えていく発想が、どこか経済にはある。もちろん、世の中が数字で回っているのは確かなんだけれど、小説としては、数字に人が挑んでいく物語を書きたいと思ったんですね。