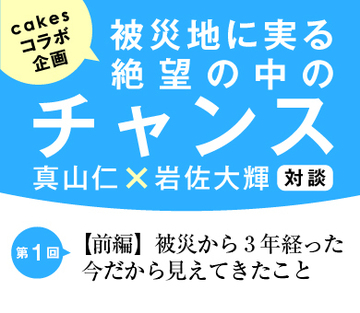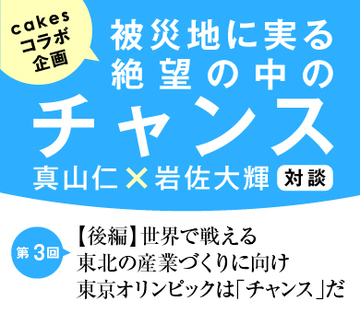――その思いが『ハゲタカ』として結実した。
真山 そうですね。あと、『ダブルギアリング』での反省は、「嫉妬こそが物語の原動力」であることを、明確に意識していなかったことです。とくに男の嫉妬心は、たぶん最も大きくて深い情念なんですよ。
私は最初、社会の大きな仕組みから生まれる歪みを描きたかったので、あまり情念に振り回されると、動機が個人的になりすぎて、話が矮小化されると思っていたんです。でも、『ダブルギアリング』を出した後、「自分の恨みを晴らしてくれ」という情報提供者が現れました。経済や社会は、数字や組織じゃなくて、根っこでは人間くさい嫉妬や情念を原動力として動いている。それを小説で書くことが大事だとわかってきたんですね。
深い絶望と虚無を抱えた
キャラクターが多いのはなぜ?
――『ハゲタカ』では、「悪役」だった外資系“ハゲタカ”ファンドを、一転ヒーローにしてみせた。いわば正邪逆転。
真山 「真山仁」として再出発する際も、やはり経済小説であることが条件でした。しかし、私は経済に精通しているわけでもない。どうせゼロから勉強するんだから、金融で誰もあまり取り組んだことのないものをやろうと。それでハゲタカ外資をやろうということになった。
 「日本をおかしくしてるのは、バブル期に栄耀栄華を極めた人たちだ」(真山さん)
「日本をおかしくしてるのは、バブル期に栄耀栄華を極めた人たちだ」(真山さん)
私が本能的に感じたのは、今この国をおかしくしてるのは、バブル期に栄耀栄華を極めた人たちだということ。そんな人たちは、バブル崩壊後にいわば悪役、敵役を探してたんですよ。
その悪役が「ハゲタカ外資」だった。世の中が悪くなったのは、外資がむしり取ったからだと。でも、真相は違う。小説のポイントを、バブル崩壊の実態とその真相の究明に定めました。さらに、『ハゲタカ』は、「悪い奴」を格好良く描いた方が、世の中の真実がもっと見えてくるのではと考え、言ってみればピカレスク(悪漢)小説の手法をとることにしました。
――そこで誕生した「鷲津政彦」ですが、軽いところもあるけれど、非常に深い絶望と虚無を抱えたキャラクターですよね。真山さんの主人公は、割とそういう人が多い。なぜなんですか。
真山 ひとつは読書歴の影響ですね。報われない主人公が好きなんです。ル・カレの『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』のジョージ・スマイリーがそうだし、フリーマントルの『消されかけた男』のチャーリー・マフィンもそうだし、金田一耕助だってそうですよね。
われわれの世代って、たぶんどこかにニヒリズムがあるんですね。われわれが社会人になった80年代半ばって、いわゆる団塊の世代の嘘っぽさみたいなものが見え始めた時代でしょう。ちょうどバブルに向かう好景気の時代なんだけど、ポップな明るさの反面、やっぱり根っこにニヒリズムみたいなのがあって、そっちの方が私はかっこいいと思っていたので、それもたぶん影響してるんだと思いますけどね。
――世代的には、いわゆる「しらけ世代」とか「新人類」と言われた世代ですね。
真山 何せ連続幼女誘拐殺人の宮崎勤と同い年ですから、いろいろ言われましたね。筑紫哲也さんが「朝日ジャーナル」で私たち世代を「新人類」と初めて称して話題になりました。ただ、自分が自分の世代を代表してるとは、あまり思わない。世代の代表として、物語を書いている意識はないです。