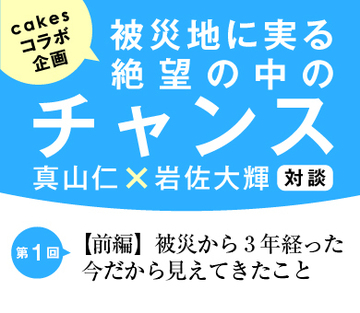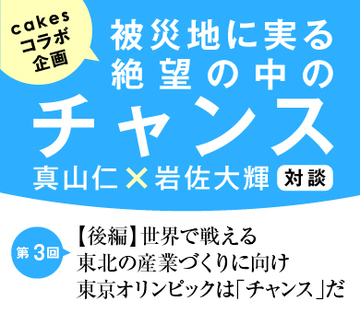――バブル絶頂期は何を感じていましたか?
真山 ちょうど中部読売新聞の岐阜支局にいた時期ですが、昭和天皇がいつ崩御するかということで走り回っていた記憶しかありません。
最近の若者は、バブル期を知らない自分たちは不幸だって言うけれど、そんなの嘘っぱちですよ。実はわれわれの世代で、バブルでいい目を見た人間なんて、ほとんどいないんじゃないですか。恩恵を受けたのは、証券会社、広告代理店、テレビ局、出版社など、ごく一部の業界の人たちだけなんじゃないか。地方記者にとっては「バブル、それ何?」って感じでしたね。
ドラマで生まれた
もうひとりの鷲津
――『ベイジン』の連載が始まった2007年に、NHKで『ハゲタカ』のドラマが放送されます。これがベストセラーのきっかけになるわけですが、今振り返って、ドラマについてはどう感じていますか?
真山 デビュー作があれだけすばらしいドラマになったのは。幸せなことです。やっぱりNHKはすごいなと思うのは、どこの地方へ行っても、取材相手の3人に1人は「ドラマを見た」って言うんです。これはやっぱり大きい。
もちろん本も、ものすごく売れましたし、映画にもなった。そのおかげで、20代後半から30代の若い層に、熱狂的真山ファンがいるんですね。この10年間の運はすべて凝縮されているくらい、ドラマ化は幸せなことだったと思います。
――一方で、ドラマの『ハゲタカ』と小説の『ハゲタカ』って、だいぶ違いますよね。
真山 全然違いますね(笑)。
――原作者としてはどのように感じましたか?
真山 最初にNHKからお話が来た時に、原作との違いにどれぐらいこだわりますかって聞かれたんです。こちらからお願いすることは一点だけ、ハゲタカのせいで日本がおかしくなったというのだけはやめてくれと言いました。
この小説は、言い訳ばっかりしている日本人がハゲタカにむしり取られる、原因も結果も日本人の自業自得だ、という物語なので、そこをドラマとして作ってくれるのであれば、もう鷲津が女でも構わないし、新しい登場人物を入れても構わない、と。
ただし、第1話の脚本を読んだ時はその譲れない一点がきちんと伝わってないのかと不安に感じて、製作統括の方と話しました。なぜか鷲津が元銀行マンで、鷲津を追跡するジャーナリスト(演じたのは栗山千明)の父親がその銀行の取引先だなんて、奇遇すぎて解せないし、これだと物語を小さくするんじゃないんですかとは、すごく言いました。