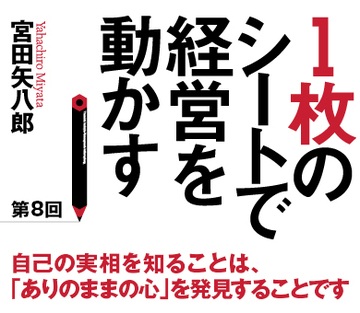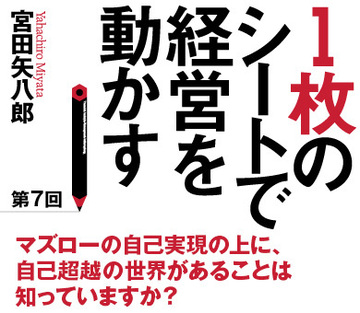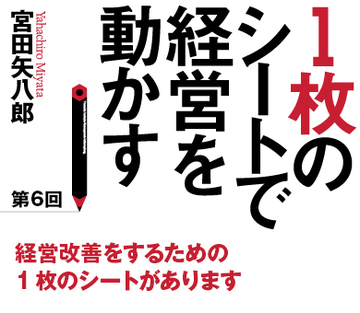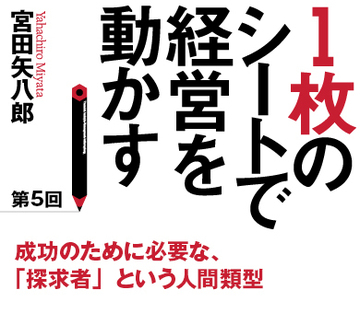今回のテーマは人間学のクライマックス、自己超越です。これは世界の諸宗教の究極のテーマであり、人間が考え得る限りの究極の到達点でもあります。
普通の人は合理的な探求の結果として自己超越に達すると考えます。思索、修業、経験、洞察等々。マズローもそうでした。彼はそのような自分の思想を「生物学的神秘主義」と表現しました。要するに、人間の連続的な成長の結果としての自己超越への到達、と。
人間の成長・発展・完成の到達点としての自己超越という常識的発想は――どのような過程を経ようと、外側から見ればそう見えるのかもしれませんが――成長・発展・完成のための最初の押さえ所を曖昧にします。そこを外したなら、どんなプロセスもボタンの掛け違いになるというような。それが前回のテーマ、懺悔なのです。
そもそも、宗教とは人間の「破れ」、世界の「不条理」の故に生じたものです。この苦しみからの脱却――救済あるいは解脱――こそが宗教の本来領域で、これを可能にするものとしての自己超越という取組みなのですが、「合理的探求者」には「破れ」と「不条理」の決定的な認識がありません。だから、超越世界へ入るのが、易しいようで決定的に難しいのです。
以下に、易しくも難しい事例を三つ、ご紹介しましょう。
第一は、13世紀、宋の時代の禅の本『無門関』の一節です。著者は無門慧開(1183~1260)。この本の序文にひとつの偈(げ)があります。
大道無門/千差路あり/此の関を透得せば/乾坤に独歩せん
「いいか、悟りに至る大道はすべての人間の目の前に、何の隠し立てもなく開かれている。誰でも、いつでも入れるのだ。それなのに、ここを通って入って行くものが少ないのはどうしたことだ。この無門という門を通過した者は、広漠たる大宇宙を一人、堂々と歩むのだ」。
ざっと、このような意味です。中国の禅はざっくりと、さっぱりしたものです。
第二はユダヤ系のドイツ人哲学者エーリッヒ・グートキント(1877~?)の『人間性の破産と超克』(原著は1937年出版)です。ユダヤ系のドイツ人で1937年と言えば、大方の読者は著者の置かれた状況の厳しさがおわかりでしょう。この本はドイツ語ではなく、亡命先のイギリスにおいて英語で出版されました。この本の緒言に次のような文章があります。
「地上の何ものにもまして堅固、何ものよりも烈しく、何ものよりも切実なる一個の直観というものがある。それは人間が彼の初原の瞬間への還帰にほかならない。何故にこの還帰が年々切々の一可能性であってはいけないというのであるか?
この偉大なる根源の選択がまさになさるべき時に、人間は蹉跌した。そして、生存の構造が破壊された。しかし、この永遠の拒絶が成されて以来、人間の根源の、腐敗以前の状態が、新しく、たえ間なく、自らを示顕しないという時はなかった。ただの一瞬も、人間の勇断一つで、人間の初原の完全状態に復帰しえないという瞬間というものはなかった。」
これがユダヤ教の基本スタンスなのです。マズローの思想もこの系譜にあります。現実には、たった一つの勇断で人間初原の完全状態に復帰したような人間は一人もいないのです。
一方は中国禅、もう一方はユダヤ教。両者とも人間は入ろうと思えば何の造作もなく超越世界に入れると述べています。しかし、繰り返しになりますが、簡単に入った人はいないのです。
その理由は、「大道無門」と言いながら「無門」という門があって、普通の人間にはその門が見えないのです。これが「合理的探求者」の越えることのできない限界です。
言い換えれば、知の領域と自己超越の領域は別次元なのだという経験的認識が必要なのです。その区別がつかない場合、それはその人が自己実現レベルで自己超越を受け止めているという証拠、要するに、頭でわかっているだけなのです。
しかし、この宇宙には人間知力の思いも及ばない、巨大な深い何かがあります。その何かがわかった者には、その門が見えるのです。その何かに触れた者は、門の扉を開ける鍵を持つのです。
第三の事例がそれです。岩手県出身の詩人に村上昭夫(1927~68)という人がいました。1950年23歳で結核を発病し1968年に41歳で亡くなっています(同年に第18回H氏賞を受賞)。彼は仏教色の濃い詩を残していますが(『村上昭夫詩集 動物哀歌』1983年)、その中に「雁の声」というものがあります。
雁の声を聞いた/雁の渡ってゆく声は/あの涯のない宇宙の涯の深さと/おんなじだ
私は治らない病気を持っているから/それで/雁の声が聞こえるのだ
治らない人の病いは/あの涯のない宇宙の涯の深さと/おんなじだ
雁の渡ってゆく姿を/私なら見れると思う/雁のゆきつく先のところを/私なら知れると思う/雁をそこまで行って抱けるのは/私よりほかないのだと思う
雁の声を聞いたのだ/雁の一心に渡ってゆくあの声を/私は聞いたのだ
結核は当時の死病です。「治らない病気を持っている」と村上は言っています。治らないという絶望のなかで、彼は「雁の声を聞いた」と告白します。「治らない」と思い知らされた絶望の悲しみの中で、彼は「雁の声を聞いた」のです。
雁の声の深さは、あの涯のない宇宙の、涯の深さとおんなじだ。自分の治らない病は、あの涯のない宇宙の、涯の深さとおんなじだ、と。だから、自分は雁の声が聞こえるのだ、と。
釈迦が、高い空を一心に渡ってゆく雁と同じように孤独な求道の旅を続けて行った。その釈迦の心が自分ならわかると彼は言うのです。
ここで、涯のない宇宙の涯の深さ、雁のように高い空を一心に渡って行った釈迦の探求の深さ、治らない病気に絶望している自分の心、が重なっているのです。これが前回述べた「懺悔」の姿です。
この懺悔のプロセスを通って人間は自己実現の段階から自己超越の段階へと移っていきます。
結論です。宗教は人間の「破れ」と世界の「不条理」の故に生じており、この苦しみに打ち砕かれて救いを求めるときに、自己超越の世界は開かれるのです。