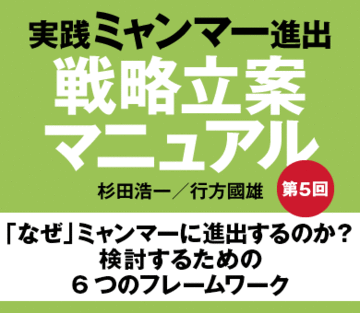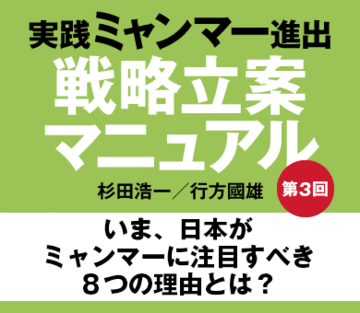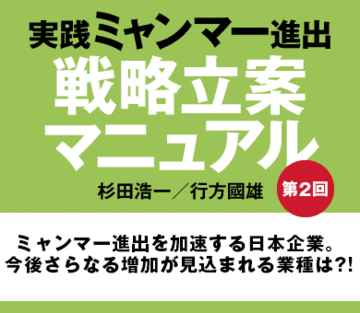ミャンマー・タイ両国にとってのダウェーの位置付け
ミャンマー側にとってのダウェーの位置付けは比較的わかりやすい。開発が起草された2008年当時、国内の低迷する経済のテコ入れ策として、大型船舶が停泊できる本格的な工業団地を造り、ゆくゆくは経済のハブに成長させるという大きなテーマを持っていた。本来であれば、ベトナム程度の開発発展の道をたどれたはずだったのが、軍事政権による実質的な鎖国状態が続いたことにより、5年から10年の単位でベトナムやカンボジアのようなASEANの後発組にさえ後れを取ってしまったことに対する危機感だ。
そうした中で、ティラワ以上のダウェーの戦略的重要性について、ミャンマーのテイン・セインをはじめとする政府側は深く認識していると松島氏は言う。「ASEANの経済統合が今後進む中では、今までのような一国で独立した国民経済、国民国家としての成長を前提にした首都近くの経済特区ではなく、バンコクのようなより大きな経済圏と連結し、深海港という域外への貿易・通商の出口戦略を持った開発でなければ、経済的な一体性が確保できず、経済性の高い競争力のある開発を行うことができない。つまり、ODAなど外国政府から借金するにしても、そのお金をしっかり返済することが可能になる強靭な経済成長を担保にする必要があると、しっかり認識しています。皮膚感覚でアジアの経済統合の真意を理解しているのです。加えて、後発の利益による環境配慮型開発、人権や社会的影響を加味した包括的開発を前提にして、タイでなかなか建設できない化学コンビナートや製鉄の上流工程等の施設を呼び込んで、タイ側のバリューチェーンと一体化することができれば、タイ側からの関心及び資金をしっかりと引き出すことができると理解しており、実際その方向で進んでいます」。
一方で、タイにとってのダウェーとは、どのような位置付けなのだろうか。彼らにとっては、過去の大規模開発における成功パターンの再現にある。タイは、1970年代後半からイースタン・シーボードと称される、バンコクから東側の海岸線の工業化計画を進行させた。その結果、レムチャンバン港、マープタープット港を擁するタイ最大の工業開発拠点として結実した。現在、タイの工業出荷額の約25%程度をこの地域が担うほど、タイの成長に大きく寄与している。
タイ側はダウェーを、「イースタン・シーボード」の成功を踏襲するかの如く、「ウェスタン・シーボード」と称しており、明らかにそのネーミング自体が、彼らにとってのダウェーへの期待感を表現している。イースタン・シーボード開発当時の1980年代は、まさに日本の経済成長が東南アジアを席巻していた時期で、その勢いを取り込む形で開発された。時は巡って現在では、インド、中東、ヨーロッパ向けの経済活動が活発化する中で、タイの西側に向けてのゲートウェイ確保の重要度が高まってきた。マラッカ海峡を通さずに300kmでバンコクにアクセスできる西側向けの水深20mの大型港湾施設と、それにつながる大規模工業団地のニーズが高まっていたのである。
「加えて、タイ側にとっての意義付けとしてもう一つ重要な点があります」と松島氏は言う。「先ほどミャンマー側の意義で述べたように、特に、大型港湾と素材系の大規模工業団地は、タイ国内では新たな知識集約産業などの重点分野への展開を前提に、今や国内ではなかなか建設ができないのです。こうした鉄鋼、特に高炉建設とか、ガスタービン、ペトロケミカル等の大型の素材系の装置産業を、後発の利益によって、環境配慮や社会的影響を十二分に盛り込んだ開発のできるダウェーで、タイの 産業のバリューチェーンにおける上流工程として呼び込むことは、明らかにタイ政府がダウェーで狙っているポイントです。ダウェー周辺の地盤の固さも、深海港の設置を中心に、こういった事業を呼び込む際のプラス要因です」。
なぜ国家レベルのプロジェクトを
タイの開発会社が1社で担うことになったのか
それだけの戦略的な意義付けを持つダウェーの開発を最初に担ったのは、タイの大手建設・開発会社であるITD社だった。なぜITD社だったのか? 現在でもタイの主要建設会社の一角であるITD社は、2014年売上高47,973百万バーツ(当時の日本円で約1,630億円相当)、2015年11月15日時点の時価総額で41,180百万バーツ(同約1,400億円)を有する大企業だ。
このダウェーの開発権を獲得した2010年は、売上高で36,076百万バーツ当時(同約980億円)、時価総額約18,600百万バーツ(同約500億円)で、当時もタイを代表する建設会社だった。
ただ、大手建設会社ではあったとしても、ティラワの10倍以上の開発案件に取り組むには無理があったのではと思われる。加えて、ITD社以外にも当時、タイには現地の工業団地開発・運営の最大手であるアマタやロジャナといった、当時よりしっかりとした開発実績を有する企業があった中で、こうした企業をさしおいて、なぜ彼らが単独で受注したのだろうか。本来ならば、国が主導して、ITD社を含めてのより大掛かりなコンソーシアムを組成して進める方法があったのではないかとの疑問が湧く。
「それには二つの理由があります」と松島氏は言う。「一つ目は、そもそも当時、ITD社以外がこの案件には手を挙げなかったのです。このダウェーの開発計画は、ミャンマー側は独裁者のタンシュエをトップとする軍事政権で、外国の一民間企業に対してでも、開発を一括してオファーすることが容易であったのでしょう。またタイのクーデター後の軍主導の政権同士の関係の中で、更に進んでいくことになりました。ただ、その当時からダウェー開発を一企業レベルで突き進めることのリスクは明確で、特に開発のプロになればなるほど、そのリスクは自明でした。従って、そうしたより実力のある企業は皆手を引いてしまったのです」。
二つ目の理由は、ITD社の会長の開発案件への思い入れとトップダウンでの意思決定の速さだった。ITD社の会長は、自社を建設会社から大規模開発を手掛けるディベロッパーへ転換させることを試みていた。ただ実績に乏しいITD社は、タイ国内でそれまで大規模開発プロジェクトに深く関わることができていなかった。そんな中で、他企業が乗り気でなかったことにより、急きょ自分たちの前に大規模開発案件を手掛ける話が転がってきた。国を代表する大型開発案件に主役として関与することを夢見ていた会長にとって、ダウェーの開発案件は、まさに自社にとってうってつけのプロジェクトとして映ったのだった。こうして、ワンマン経営で決断力の速い会長の鶴の一声で、ITD社が開発主導となることが決まったのだ。こうして、2008年5月ミャンマー政府・タイ政府間で基本合意調印がなされ、2010年にはITD社がミャンマー政府よりダウェー開発の事業権を獲得し開発が進められてきた。