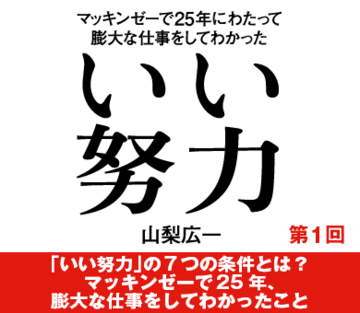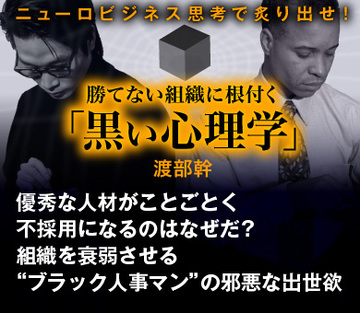努力には「いい努力」と「そうでない努力」がある。では、その「ちがい」とは何か?最高の成果が得られる「いい努力」をするための考え方、動き方とは?何がせっかくの努力をただの「時間のムダ」に変えてしまうのか?
世界最高のコンサルティングファームのトップコンサルタントとして得た豊富な経験から生み出した、生産性が劇的に上がる「仕事の方法」について、話題の新刊『マッキンゼーで25年にわたって膨大な仕事をしてわかった いい努力』から紹介する。
誤った評価基準が生み出す「困った優等生」
組織における評価の基準が不適切であれば、これもいい努力の壁になり得る。
これは社員にとってはどうしようもないが、経営者にはぜひ考えてほしい問題だ。
会社にはそれぞれ、「こういう人が優秀だ」というイメージがある。会社によって優秀さの定義は意外と一様ではないものだ。
そんな個々の定義にそって社員は働き、上司は部下を評価し、「できる社員、できない社員」という評判も生まれる。
だから、その「優秀」の定義が間違っていると、その組織の生産性は上がらない。正しい評価がなされていなければ、部下は成果と関係のない目的に向けた努力を目指すようになるからだ。
評価が間違っている例としていちばん多いのは、インターフェイスの完成度、つまり仕事や当人の見栄えで評価するというものだ。「書類がきちんと整っているか」「説明がうまいか」という表面的な印象で評価が決まるのだ。
この傾向が顕著な大企業は少なくないし、成果が数値で表れない間接部門やスタッフ職ではこういう現象が生じやすい。
こうした会社や組織で評価されがちなのは、
「提案自体はそれほどでもないけれど、資料が読みやすい」
「たいした内容はなくても、ハキハキと話し、説明がうまい」
「何をするにしてもソツがなく、感じがいい」
といったタイプだ。
また、彼らのような「インターフェイス優等生」タイプは目立つから、まわりもなんとなく彼らの振る舞いに倣うようになり、間違ったロールモデルが誕生する。