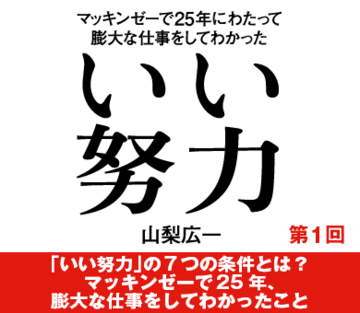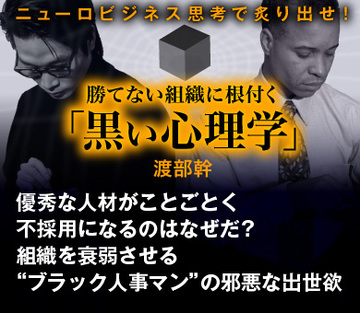「インターフェイス優等生」が上に立つと、とんでもないことになる
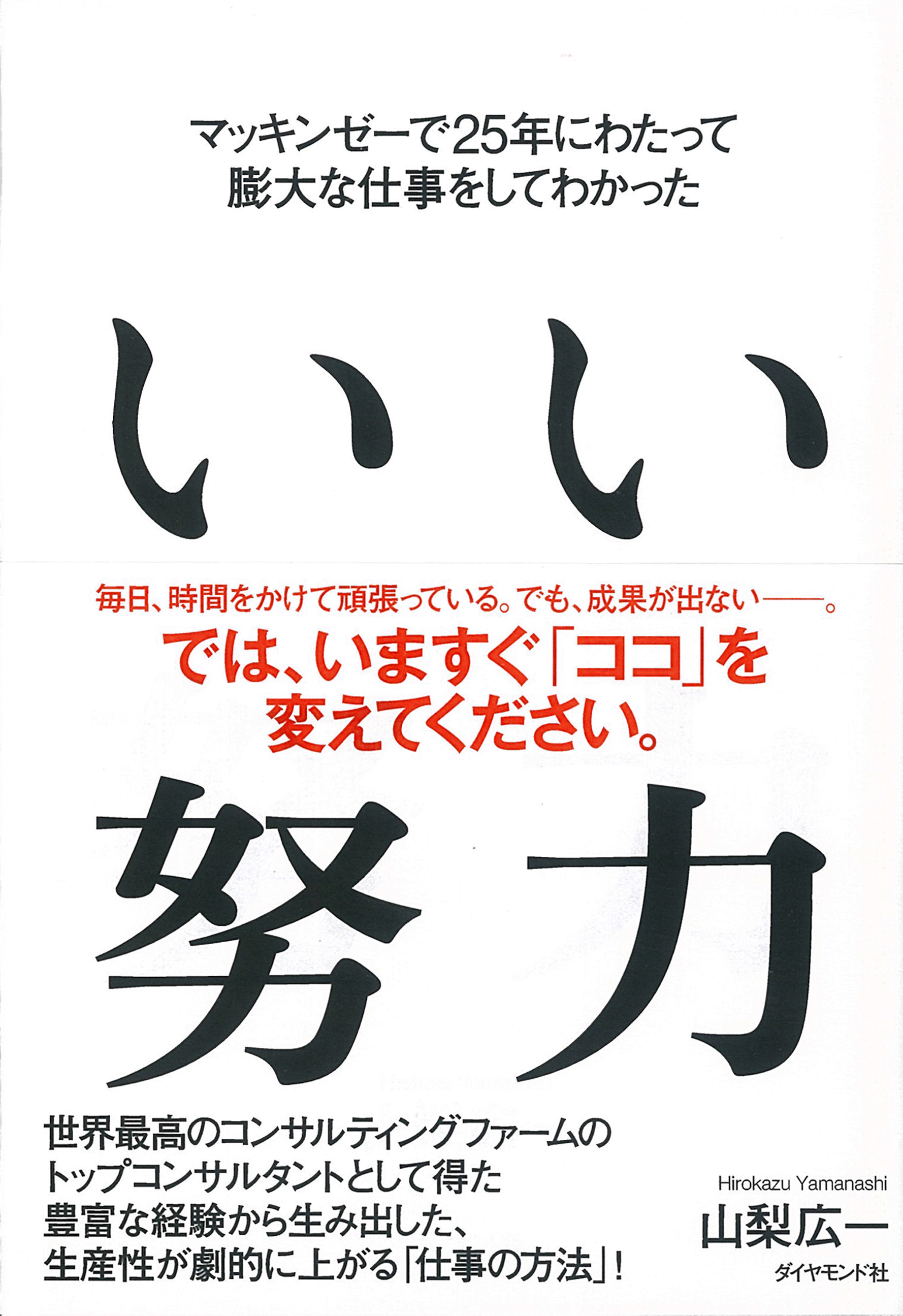 『マッキンゼーで25年にわたって膨大な仕事をしてわかった いい努力』(山梨広一著、定価1500円+税)絶賛発売中!
『マッキンゼーで25年にわたって膨大な仕事をしてわかった いい努力』(山梨広一著、定価1500円+税)絶賛発売中!
正しい評価ができない上司にとって、インターフェイス優等生の部下はいい部下だ。部下が成果を出せるように指導しない上司、自分が成果を出すための便利な補佐役として部下を使う上司も、インターフェイス優等生の部下を重用する。上司に引き立てられるとますますインターフェイスがよくなり、人事考課も高くなる。
だが、間違った評価で昇進した人がリーダーになると、困ったことになる。正しい判断をしたり、いいアイデアを出したり、問題解決をしたり、部下を指導するという実質的な仕事で成果を出して昇進したわけではないから、いざ自分が責任者になって負荷のかかる仕事を任せられても、なかなか成果を出せないのだ。
こうなるとまわりも本人も、やがて途方に暮れてしまう。これまではなんの問題もなく、上司にも人事にも「任せておけば大丈夫な人」「優秀な部下」と思われてきたのだ。本人にも「自分はできる」という自負があり、エリートと目されていたのに、こうして厳しい現実に直面すると、挫折して腐ってしまう。
インターフェイス優等生タイプが無意味な努力をしてしまう原因は、彼らが姑息なアピール上手だとか、ごますり体質だからというわけではない。
たんに会社に、成果よりも「整った資料」や「クリアな説明」などのインターフェイスを評価する風土があるからだ。
社員はどうしても会社のニーズに応えようとしてしまう。すると能力がある人もその使い道を間違い、いい努力をしなくなってしまう。
正しい評価は、非常に難しいものだ。私はコンサルタントとして何人かの優れた人事の責任者と仕事をしてきたが、彼らが口を揃えて言う「正しい評価をする方法」は、たった一つ。人を好きになり、個々の人材を一生懸命見ることだ。
人を好きでない人は、人を見る目が育たない。魚の嫌いな人が築地で働いてもいい魚を見極められないし、馬が嫌いな人が競馬場のパドックで馬のコンディションを見抜くことも不可能だろう。
人が好きで、人に関心が高く、人と過ごすことに時間を使う人が評価する側にいれば、いい努力が生まれやすくなる。手続きがうまいか、話し方がうまいか、資料がきれいかではなく、人そのものを見る。
人の上に立つ人にはぜひ心がけてほしいことだ。
(※この原稿は書籍『マッキンゼーで25年にわたって膨大な仕事をしてわかった いい努力』から抜粋して掲載しています)