「実験の力」でビジネスの成功率を向上させる【前編】
世界的ベストセラーとなった『コア・コンピタンス経営』(共著者:コイムバトーレ K.プラハラード)の著者で、ロンドン・ビジネススクール客員教授のゲイリー・ハメル。『ウォール・ストリート・ジャーナル』紙が選ぶ「世界で最も影響力のあるビジネス思想家」の一人でもある彼が、MITプレス発行の論文誌『Innovations』に発表した論文「実験の力」( The Power of Experimentation )の翻訳全文を、2回にわけて掲載する。
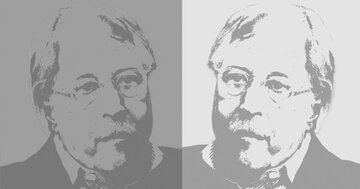
なぜブロックチェーンはイノベーションをもたらすのか?
『イノベーションのジレンマ』(翔泳社)で知られるクレイトン・クリステンセンは、2020年1月23日、67歳で他界した。今回紹介する「第3の解」は、逝去する1カ月前、MITプレスが発行するジャーナル『イノベーションズ 』に掲載されたもので、これまで未訳のままだった。『ダイヤモンドクォータリー ニューズレター』の発行に当たり、その邦訳を連載していく。

制度づくりが先か、それともイノベーション投資が先か?
『イノベーションのジレンマ』(翔泳社)で知られるクレイトン・クリステンセンは、2020年1月23日、67歳で他界した。今回紹介する「第3の解」は、逝去する1カ月前、MITプレスが発行するジャーナル『イノベーションズ 』に掲載されたもので、これまで未訳のままだった。『ダイヤモンドクォータリー ニューズレター』の発行に当たり、その邦訳を連載していく。

「イノベーションのレシピ」はどう生まれるのか?
『イノベーションのジレンマ』(翔泳社)で知られるクレイトン・クリステンセンは、2020年1月23日、67歳で他界した。今回紹介する「第3の解」は、逝去する1カ月前、MITプレスが発行するジャーナル『イノベーションズ 』に掲載されたもので、これまで未訳のままだった。『ダイヤモンドクォータリー ニューズレター』の発行に当たり、その邦訳を連載していく。

⻑期的な経済成⻑の原動⼒は、アイデアか? 制度か?
『イノベーションのジレンマ』(翔泳社)で知られるクレイトン・クリステンセンは、2020年1月23日、67歳で他界した。今回紹介する「第3の解」は、逝去する1カ月前、MITプレスが発行するジャーナル『イノベーションズ 』に掲載されたもので、これまで未訳のままだった。『ダイヤモンドクォータリー ニューズレター』の発行に当たり、その邦訳を連載していく。

日本製造業のサステナブル&サーキュラーなビジネスモデルを考える【イベントリポート】
ヨーロッパを中心に持続可能な循環経済モデルへの移行が加速している。こうしたパラダイムシフトの時代にあって、日本の製造業はどのようなビジネスモデルを描き、それを実装していけばよいのか。この大きなテーマについて考察を深めるためにダイヤモンドクォータリー編集部では、循環経済研究の第一人者と先進的な取り組みを行っている企業の幹部を招くセミナーを企画。2024年1月31日と2月29日の2回にわたって開催した。
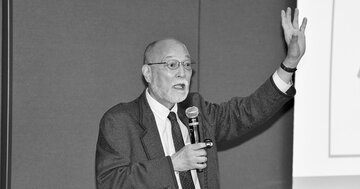
無形資産が重視される昨今、企業理念を求心力に、競争力の源泉である人的資本の強化が求められている。しかし、立派な企業理念も「額に入れられた標語」では意味を成さない。従業員エンゲージメントを高め、イノベーティブな組織を築くため、核心となる企業理念を現場にいかに浸透させるか。企業のイノベーション支援を行う佐宗邦威氏と、アプリを活用した従業員エンゲージメントソリューションを提供するヤプリの山本崇博氏が、進化する理念経営について語る。
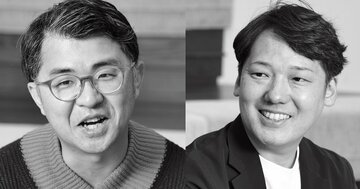
生成AIの爆発的な普及により、先進テクノロジーの倫理的・法的・社会的課題が議論の的になっている。すなわち、ELSI(Ethical, Legal, and Social Issues)の重要性の認識である。これらの課題は国・地域や個人の価値観に左右され、時とともに揺れ動く。そして、政策立案や企業活動に大きな影響を及ぼす。こうした動的かつ包括的な課題に対応していくためには、どのような姿勢と知性が必要なのか。AI技術に詳しく、国際的なAIガバナンスの構築にも携わっている中央大学国際情報学部教授の須藤修氏に聞いた。

目に見える現象を扱う古典物理学の原理だけで動くコンピュータでは、目に見えない世界で起きている現象の複雑さを正確には反映できない。だからこそ、目に見えない世界の原理に基づいた計算ができるコンピュータの存在が必要である、というリチャード・P.ファインマンの概念をもとに誕生した量子コンピュータを、ビジネスで活用しようという動きが近年活発化している。しかし、そもそも量子コンピュータとは何なのかを知ることは一筋縄ではいかない。得体の知れない機械をビジネスに導入することをためらう経営者も少なからずいるだろう。そのような中、頭で理解する前にまずは量子コンピュータを一度使ってみて、そこから得られる実利を実感してみてほしいと訴える日本の物理学者がいる。東北大学大学院情報科学研究科教授、東京工業大学理学院物理学系教授を兼務し、かつ量子コンピュータによる企業向けサービスを提供するスタートアップ、シグマアイ代表取締役を務める大関真之氏に、量子コンピュータとは何なのか、そしてどのようにビジネスに活用し、可能性を広げられるのか、量子コンピュータがもたらす未来について聞いた。

いまさら「コンピュータとは何か」という存在理由、「コンピュータで何を実現したいのか」という根源的本質を問う人は稀だろう。しかしその一方で、その発展は著しく、多岐にわたって専門分化を日々遂げており、むろん昨今いわれる「IT人材」もすべてをもれなく知り尽くしているわけではない。かくして、コンピュータは身近だが、遠い存在となり、いまや実体のわからない“巨象”と化している。もはやキャッチアップが追い付かず、IT部門やコンサルタントが何を話しているのか理解できず、現場に任せ切りになっているマネジャーは少なくない。過去を振り返っても全社変革運動が一筋縄ではいかないが、とりわけDXの場合、トップはもとよりミドルマネジメントのITリテラシーのばらつきが足を引っ張っているのは想像にかたくない。とはいえ、そういう現状を一気に変えることは現実的ではない。それでも、少なくとも「コンピュータは何を可能せしめるのか」「自分たちはコンピュータで何がしたいのか」について自分の言葉で語れる必要はあるだろう。そこで、「コンピュータとは何か」についていま一度考え直してみたい。スーパーコンピュータ「富岳」の総責任者である、理化学研究所計算科学研究センター センター長の松岡聡氏をお招きし、第一人者の知見と経験を聞く。

企業変革なくして価値創造は実現しないDXを問い直す時
ダイヤモンドクォータリーでは、企業変革と価値創造を主眼に置いたDXをテーマに、2024年2月8日、「ダイヤモンドクォータリー創刊7周年フォーラム」を開催した。本稿は、東芝 代表取締役社長執行役員CEOの島田太郎氏による基調講演と、キーエンス、ブリヂストン、花王という日本を代表する企業のエグゼクティブとマネジメントに精通するアカデミアによるパネルディスカッション、2つのプログラムの要旨をまとめた採録である。

100%防御ではなく、自由がもたらす創造性とリスクのバランスを取る
企業に対するサイバー攻撃の高度化、組織化が急速に進行する中、従来の「境界型防御」から「ゼロトラストセキュリティ」への移行が急がれている。一方で、ゼロトラストセキュリティは、ともすると管理者の負担が重くなり、利用者の利便性も損なうという指摘がある。セキュリティと投資コストや利用者の自由度など、相克する課題の解決策として注目されるのが「セキュリティ ファブリック」というアプローチだ。

企業には、持続的な成長の実現に向けた「聖域なき事業ポートフォリオ改革」が求められている。そこで有効な手段の一つとなるのが、ノンコアの事業や子会社を切り出す「カーブアウト型M&A」だ。しかしながら、事業売却ならではの高い障壁が立ちはだかるカーブアウトに二の足を踏む企業も少なくない。成功に導くためには何が必要なのか。M&Aのプロフェッショナルである西川大介氏に、その要諦を聞く。

個別企業単位では高度なオペレーションや熟練技能に強みを持つ我が国製造業だが、製造業大国として復権するには、デジタル変革と企業の枠を超えたデータ連携など大胆なモデルチェンジが必要だと指摘される。日本を代表する製造業の一社であり、2021年から3年連続でDX銘柄に選定されている旭化成の取締役 兼 専務執行役員 デジタルトランスフォーメーション統括、久世和資氏が描く、ものづくり大国復権へのシナリオを聞いた。

コロナ禍での物流の停滞、中国のレアメタル禁輸、ロシアのウクライナ侵攻、台湾有事への懸念など、世界情勢が不安定化し、地政学上のリスクが高まる中で、企業は難しい選択を迫られている。そこで、昨今注目されているのが、軍事面だけでなく経済面でも他国からの脅威に備える「経済安全保障」だ。経済安全保障に対する考え方、とらえ方は千差万別で、企業経営者の中でも、危機感や当事者意識には温度差がある。茫洋とした経済安全保障の定義や範囲、論点をはっきりさせたうえで、日本企業の喫緊の課題は何か、経済安全保障を通じていかに日本の技術力を高め、自国の競争優位をどう打ち立てるか。東京大学公共政策大学院教授、国際文化会館地経学研究所所長の鈴木一人氏に、その方策について聞いた。

いまや「人権」が脱炭素と並ぶグローバルアジェンダとなったことは紛れもない事実である。欧米諸国では企業活動による人権侵害を規制する法整備や輸入制限が進み、人権に関する情報開示や解決アクションを求める投資家からのプレッシャーも強まっている。人権を軽視する企業はグローバルサプライチェーンから排除され、投資家から低評価を受ける可能性がある。人権方針を掲げるところは増えているものの、日本企業の頭をいま悩ませているのが、「人権デューディリジェンス」である。なぜグローバルサプライチェーンにおける人権リスクをくまなく調査し、対処しなければならないのか。時に「人権後進国」と揶揄される日本は、なぜ人権意識が低いのか。ビジネスと人権のエバンジェリストとして日々奔走する国際労働機関 駐日事務所の田中竜介氏が、「人権の国際基準」を正しく理解するためのポイントを語る。

製造業の未来:SX時代における「日本のものづくり」を考える【イベントリポート】
ダイヤモンドクォータリー編集部では、製造業の経営層や次世代リーダーを対象に、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)の時代における「日本のものづくり」のあり方をともに考えるワークショップを含めたセミナーを企画し、8月29日と9月21日の2回にわたって実施した。有識者による基調講演と特別講演、先進的なSXに取り組む大手メーカーを招いたパネルディスカッションも行われた当日の模様をリポートする。

東京証券取引所による資本コストと株価を意識した経営の要請を受け、自社の「安すぎる株価」問題に多くの企業が直面している。投資家との間で、企業価値に対する認識はなぜ乖離してしまうのか。ESG情報開示の第一人者である北川哲雄氏は、トップマネジメントによる投資家との意義ある対話と「エンゲージメント」こそが、溝を埋めるカギになると指摘する。

2021年6月のコーポレートガバナンス・コード改訂の目玉は、「取締役会の機能発揮」であった。これを受けて、東京証券取引所プライム市場上場企業では独立社外取締役の3分の1以上の選任、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会・報酬委員会の設置などを求められることとなった。21世紀に入ってからの日本における取締役会とガバナンスの変化を、日本取締役協会の初代会長でもあった宮内義彦氏はどう見ているのか。企業成長ひいては日本経済の成長を後押しする“取締役の使命”について提言してもらう。

世界における日本の存在感は、「失われた30年」「ジャパニフィケーション」という言葉が示しているように、すっかり低迷している。こうした不名誉な評価を返上するには何が必要か。今回の対談では、三菱商事の垣内威彦会長をお招きし、エネルギーの自給自足、一気通貫した送配電システム、いまだタブー視されている原子力発電、実用化が見えてきた常温核融合など、エネルギー関連のトピックスについて意見交換がなされた。2050年までにカーボンニュートラルを達成するという国際公約を守るためだけでなく、経済安全保障、イノベーション立国という視点からも、示唆に富んだ議論となった。

