人的資源から人的資本へ──。人的資本が注目されるようになった発端は無形資産の定量化であり、SDGs/ESGが棹差したといわれる。しかし、「人材版伊藤レポート」には人事や組織の研究者が参加していないように、誰もが一家言あるためDX以上に玉石混交の議論が予想される。そこで、専門家の中の専門家である鶴光太郎氏に、日本の人的資本経営に関する課題や危うい議論、向かうべき方向性などについてレクチャーを受ける。

不確実性が高まる一方の現代において、変化に対して柔軟かつ迅速に経営をアジャストさせるには、データマネジメントを中核とした企業活動全般の変革が不可欠となる。その前提となるのが、ファクトの収集・評価、ファクトに基づく予測という科学的経営の実践だ。AIアルゴリズムによる科学的経営をRidgelinez(リッジラインズ)の野村昌弘氏が解説する。

「DevOps」というキーワードをご存じだろうか。ソフトウェア開発の現場から生まれたこのソリューションがいま、組織変革に有効な手法の一つとして世界中で注目を集めている。VUCAといわれるこの時代において、ビジネスモデルだけでなく、その土台となる組織をどうトランスフォームしていくかが大きな課題となる企業にとって、DevOpsが持つ変革力のインパクトは見逃せない。Claris Internationalが、みずからの変革体験を通じて知ったDevOpsの真価を語る。

2020年に「デジタルサービス会社への変革」を宣言したリコーは、その大胆な変革の推進が評価され、経済産業省と東京証券取引所によって「DX銘柄2022」に選定された。米GE(ゼネラル・エレクトリック)や中国アリババグループの日本法人で経営の指揮を執った後、リコーのCDIOとしてデジタル戦略を統括する田中豊人氏に、DXの現在地と目指すゴールを聞いた。

エンターテインメントの世界は、エンジニアリングのような設計図では表現できないし、費用対効果もはっきりしない。また、過去のトラックレコードが必ずしも成功を保証しない世界でもある。こうした不確実性の高いエンターテインメント産業において、トップランナーの一社がバンダイナムコである。同社はなぜ好業績を続けているのか。クリエイターをはじめとする社員の能力をいかに引き出し、創造性や感性といった無形資産を付加価値に転嫁させているのか。代表取締役社長 グループCEOの川口勝氏に「創造性のマネジメント」の要諦を聞く。

一代で一流企業を築き上げた創業者、V字回復を果たした中興の祖など、名実を伴った経営トップの後を継ぐ者は、えてして期待を裏切ることがある。経営者育成機関とまでいわれるプロクター・アンド・ギャンブルやゼネラル・エレクトリックですら「逆V字」を招いている。ならば、こうした創業経営者や中興の祖ならではの思考回路や行動様式をあらかじめ“移植”しておけば、つまり次世代リーダーの育成を徹底していれば、逆V字を回避できるのではないか。そのベストプラクティスといえるミスミグループ本社の核心に迫るべく、大野龍隆社長と膝を交えた。

組織人は失敗を恐れる。しかし、挑戦には必ずリスクが伴う。失敗学の提唱者、畑村洋太郎氏が『失敗学のすすめ』(講談社)を上梓したのは、いまから20余年も前のことである。しかし、失敗の積極的活用、失敗への不寛容や減点主義は、依然として大半の組織にはびこっている。2022年春に「失敗学2・0」ともいえる『新 失敗学』(講談社)を書き下ろした畑村氏に話を伺い、失敗は必然であり、失敗に学ぶこと、失敗を許すことの重要性、それはリーダーの大切な仕事の一つであることを再確認した。

岩垂邦彦日本で最初の外資系企業をつくった技術者企業家
1880年代後半はアメリカにおける電力事業の黎明期に当たるが、この時、「電流戦争」と呼ばれる、2人の天才科学者の確執があった。すなわち、発明王ことトーマス・エジソンは直流システムを主張し、ニコラ・テスラは交流システムこそ優れていると訴え、互いに譲らなかったのだ。最終的には、ナイアガラの滝の発電事業でテスラの交流発電機が採用され、以降交流が主流となる。この電流戦争は日本にも及んだ。それは、エジソンの発明に感銘を受け東京電燈(東京電力の前身の一つ)設立を働きかけた藤岡市助(工部大学校教授)は、みずから技師長になって直流システムを採用し、一方、のちに大阪電燈(関西電力の前身の一つ)の技師長となる岩垂邦彦は交流を選択した。実を言うと、テスラも岩垂もエジソンの下で働いていたのだが──。この岩垂邦彦という男、日本で最初の外資系企業、日本電気(NEC)の創業者であり、いまあらためて評価すべき「技術者企業家」の先駆者といえる。
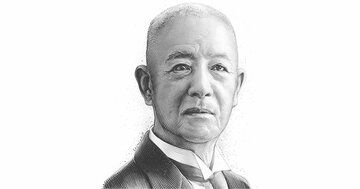
無形資産のベストパートナーを探すパーパスドリブンM&A
コロナ禍でも活況が続くM&A市場だが、「何のためか」という目的が不明瞭であることにより、シナジーが生まれそうにないにもかかわらず、人気のDX銘柄に飛び付いて高値づかみをしてしまうケースも目につく。それらに共通しているのは、みずからのありたい姿を長期的な視点で描き切れていない点だろう。手段の目的化に陥らず、真の目的にたどり着くM&Aを実現するには何が必要なのか――。

環境変化の激しさが増大する一方、ビジネス活動の状況は把握しづらいものになっている。バリューチェーンは複雑化しており、サブスクリプションなど新たなビジネスモデルを手掛ける企業も増えた。マネジメントの難易度は、以前とは比較にならないほど高まっている。データアナリティクスによって、未来を予測し、変化への動的管理を行い、中長期にわたる企業の全体最適を導く「次世代EPM(Enterprise Performance Management)」が、いま注目されている。

紙の図面と試作機によるすり合わせといったアナログなものづくりでの成功体験が、日本の製造業のDXを阻んでいる。現地現物主義や現場力といった日本の強みを活かしながら、製造プロセスとビジネスモデルのDXを進めるためには、設計を起点とする「3Dデジタルツイン」が大きな威力を発揮する。

デジタル世界でのシミュレーションと現実世界へのフィードバックループは、設計・開発から生産、アフターサービスに至る製品ライフサイクル全体に大きな変革をもたらす可能性を秘める。だが、日本の強みを活かすデジタルツインの活用法については、まだその解を見出せていない。その具体的なアプローチとして東京大学の梅田靖教授が提唱するのが、人を中心とするデジタルエンジニアリングサイクル「デジタルトリプレット」である。

関東圏の社会インフラの一端を担い、脱炭素という世界的な課題解決のリーディング企業の一社として、その一挙手一投足が注目されている東京ガス。とはいえエネルギーリテラシーは、門外漢である一般事業会社のビジネスリーダーにすると、特定部門の担当でもなければ、なかなか身につかない。そこで、ビジネスリーダーの脱炭素・エネルギーリテラシーに資する一助となるよう、東京ガス社長の内田高史氏に、同社の取り組みの紹介を通じて、日本の脱炭素の針路を示してもらった。

2021年6月、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に続いて、「自然関連財務情報開示タスクフォース」(TNFD)が発足した。脱炭素に続いて「生物多様性」についても、産業界に責任ある行動がいっそう求められることを示唆している。ベストセラー『ゾウの時間 ネズミの時間』そして『生物多様性』(いずれも中公新書)の著者、本川達雄氏は、数値や論理など合理・科学主義では説明し切れない生物多様性の内在的価値の重要性を説く。それは、ダイバーシティや脱炭素の核心を突く指摘であった。
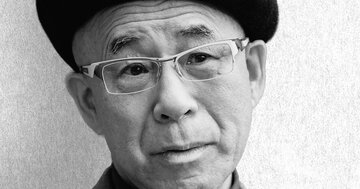
「2025年カーボンニュートラル」という目標達成に向け、日本の産業界がいっせいに動き始めた。他方、脱炭素実現に向けては、さまざまなイノベーションと社会実装の加速が必須である。アンモニアやメタンを活用する脱炭素技術の開発において産業界からの期待が大きいIHIは、既存技術・インフラを活かした「トランジション」戦略と、画期的なブレークスルーによる「トランスフォーメーション」戦略の両構えで、カーボンニュートラル社会の実現を目指す。

浅野総一郎渋沢栄一が認めた不撓不屈の起業家
渋沢を語るうえで欠かせない事業家がいる。浅野総一郎である。総一郎の事業家人生をたどると、ビジネスチャンスなどそこら辺に転がっており、だからこそ起業や新規事業ごとき身構えるほどのものではないが、育成・成長させることは難しいという、古くて新しい教訓が見えてくる。それは、文字通り、ベンチャーには失敗がつきまとうという意味でもある。ところが、この当たり前のことが脇に置かれ、失敗を前科のようにマイナス評価し、安定を是とする考え方が日本全体に染み付いている。明治から高度成長期に至るまで、欧米に大きく遅れていた日本に、さまざまな産業を勃興し、「東洋の奇跡」を起こしたのは、挑戦と失敗を繰り返してきた産業人たちである。浅野総一郎はその代表格であり、落第経営者どころか、一流の経営者だったといえる。

京都大学の協力の下に始まった、総長の湊長博氏と京都大学を卒業したビジネスリーダーたちとのシリーズ対談。第1回目は、1978年工学部卒のNTT代表取締役社長、澤田純氏をお招きし、第2回目では、MS&ADホールディングス会長の柄澤康喜氏にご登場いただいた。柄澤氏は現在、経団連でダイバーシティ推進委員会と経済財政委員会の委員長を務めており、ダイバーシティ&インクルージョン、人生100年時代、何よりリスクマネジメントについて造詣が深い。今回の対談でも、産学の立場の違いこそあれ、これらのトピックスのみならず、教育の問題などについて建設的な意見が交わされた。

京都大学の協力の下に始まった、総長の湊長博氏と京都大学を卒業したビジネスリーダーたちとのシリーズ対談。第1回目は、1978年工学部卒のNTT代表取締役社長、澤田純氏をお招きし、第2回目では、MS&ADホールディングス会長の柄澤康喜氏にご登場いただいた。柄澤氏は現在、経団連でダイバーシティ推進委員会と経済財政委員会の委員長を務めており、ダイバーシティ&インクルージョン、人生100年時代、何よりリスクマネジメントについて造詣が深い。今回の対談でも、産学の立場の違いこそあれ、これらのトピックスのみならず、教育の問題などについて建設的な意見が交わされた。

カーボンニュートラル実現の切り札、「GX経営」とは何か【イベントレポート】
「カーボンニュートラルLNGバイヤーズアライアンス」設立から約1年後の2022年3月10日、設立1周年を記念して「ダイヤモンドクォータリー特別フォーラム」が開催された。『ダイヤモンドクォータリー』では、企業変革すなわち「X経営」を取り上げているが、とりわけ注目しているのが、グリーントランスフォーメーション経営(GX経営)だ。特別フォーラムでは、タイトルに「カーボンニュートラルはGX経営から始まる」を掲げ、先進企業が登壇。キーパーソンによるセッションと、パネルディスカッションが行われた。

日本の知的競争力は、かつては世界に冠たるものであったが、1993年から約30年の間、低下し続けている。その復活を図るには「ヒューマナイジング・ストラテジー(人間くさい戦略)」がカギを握る。本稿では、一橋大学名誉教授である野中郁次郎氏が語った、今後の日本企業成長の鍵となる「共感経営」について紹介する。

