AIの技術進化と利用拡大が急速に進む一方、バイアスやデータ流出の懸念など新たな課題への社会的関心が高まっており、AIならではのリスクを適切に制御する「AIガバナンス」の構築・運用は、企業にとって待ったなしだ。AIがもたらすメリットの享受とリスクの抑制を両立するガバナンス体制をいかに整備するか――。KPMGジャパンの2人の専門家に聞いた。

経済戦争では企業が最初に被弾する
2025年、アメリカのトランプ第2次政権の誕生によって、グローバル化と自由主義経済を謳歌する時代の終焉はより明確となった。地政学的にいっそう混迷を深める世界において、企業はグローバルサプライチェーンの危機にさらされ続け、経営のグローバルスタンダードは幻影となりつつある。そんな環境の中で、日本企業は乱世を生き抜くための「シン日本流経営」が求められる──ダイヤモンドクォータリーはこうしたテーマを掲げ、2025年2月17日、都内で「ダイヤモンドクォータリー創刊8周年記念フォーラム」を開催した(主催:ダイヤモンド社 メディア局、協賛:Ridgelinez、ヤプリ、Wolters Kluwer CCH Tagetik)。本稿では、「企業版『経済安全保障』の論点」と題し、この分野の第一人者である東京大学公共政策大学院教授で国際文化会館 地経学研究所長を務める鈴木一人氏の基調講演の採録をお届けする。

日本の強みと世界のそれを異結合させるには?
なぜいま「シン日本流経営」が必要なのか──日本流経営は優れた元型を持ち、利他心、人基軸、編集力という日本ならではの「本(もと)」を軸に守破離(しゅはり)を繰り返し、世界で存在感を示してきた。では、なぜ多くの日本企業がそれを見失い、平成、令和という2つの時代を通じて競争力を低下させ続けることになったのか。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と持ち上げられたのもつかの間。バブル崩壊とともに一気に自信喪失に陥り、アメリカ流の株主至上主義に思い切り舵を切っていった。日本流を封印し、「世界標準」モデルを取り入れようとした結果が、平成の失敗を招いてしまったのである。そもそも世界標準というものは、世の中に存在しない。取り返しがつかなくなる前に、我々は日本流の本質を取り戻し、それを「シン日本流」にアップデートさせる知恵を発揮しなければならない。

野中郁次郎:知を探究し続けた人
2017年夏、「ダイヤモンドクォータリー創刊1周年記念フォーラム」が開かれ、基調講演は、野中郁次郎先生だった。演題は「日本の経営イノベーション宣言——経営者は『知的機動力』を発揮し、組織を再創造せよ」で、まさしく野中先生ならではのタイトルである。ちなみに、同誌創刊号のカバーストーリーにもご寄稿いただいている。
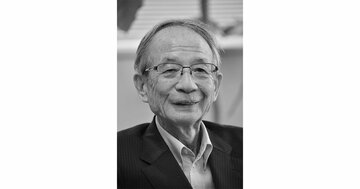
成長と脱皮を経て、企業が生まれ変わるには?
なぜいま「シン日本流経営」が必要なのか──日本流経営は優れた元型を持ち、利他心、人基軸、編集力という日本ならではの「本(もと)」を軸に守破離(しゅはり)を繰り返し、世界で存在感を示してきた。では、なぜ多くの日本企業がそれを見失い、平成、令和という2つの時代を通じて競争力を低下させ続けることになったのか。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と持ち上げられたのもつかの間。バブル崩壊とともに一気に自信喪失に陥り、アメリカ流の株主至上主義に思い切り舵を切っていった。日本流を封印し、「世界標準」モデルを取り入れようとした結果が、平成の失敗を招いてしまったのである。そもそも世界標準というものは、世の中に存在しない。取り返しがつかなくなる前に、我々は日本流の本質を取り戻し、それを「シン日本流」にアップデートさせる知恵を発揮しなければならない。

伝統から革新を生み出すには?
なぜいま「シン日本流経営」が必要なのか──日本流経営は優れた元型を持ち、利他心、人基軸、編集力という日本ならではの「本(もと)」を軸に守破離(しゅはり)を繰り返し、世界で存在感を示してきた。では、なぜ多くの日本企業がそれを見失い、平成、令和という2つの時代を通じて競争力を低下させ続けることになったのか。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と持ち上げられたのもつかの間。バブル崩壊とともに一気に自信喪失に陥り、アメリカ流の株主至上主義に思い切り舵を切っていった。日本流を封印し、「世界標準」モデルを取り入れようとした結果が、平成の失敗を招いてしまったのである。そもそも世界標準というものは、世の中に存在しない。取り返しがつかなくなる前に、我々は日本流の本質を取り戻し、それを「シン日本流」にアップデートさせる知恵を発揮しなければならない。

日本独自の経営モデルを取り戻すには?
なぜいま「シン日本流経営」が必要なのか──日本流経営は優れた元型を持ち、利他心、人基軸、編集力という日本ならではの「本(もと)」を軸に守破離を繰り返し、世界で存在感を示してきた。では、なぜ多くの日本企業がそれを見失い、平成、令和という2つの時代を通じて競争力を低下させ続けることになったのか。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と持ち上げられたのもつかの間。バブル崩壊とともに一気に自信喪失に陥り、アメリカ流の株主至上主義に思い切り舵を切っていった。日本流を封印し、「世界標準」モデルを取り入れようとした結果が、平成の失敗を招いてしまったのである。そもそも世界標準というものは、世の中に存在しない。取り返しがつかなくなる前に、我々は日本流の本質を取り戻し、それを「シン日本流」にアップデートさせる知恵を発揮しなければならない。

デフレからインフレへのシフトとともに早急な対応を迫られているのが、深刻な「人手不足」である。これまでは物流業、小売業、建設業などのフロントラインワーカーの現場が中心だったが、急速にその他の業種にも及び始めた。人手不足は供給制限を生み、サプライチェーンの維持だけでなく、企業の成長にも大きな影を落とす。人口減少時代を迎え撃つためのダイナミックな現場変革について考える。

生産年齢人口の急速な減少により、我が国において人手不足という構造危機の深刻化が止まらない。これに対処するには、デジタル化・自動化による生産性向上に加えて、高齢者や外国人人材、障がいのある人など多様な人材が活躍できる環境整備をこれまで以上に推進していく必要がある。多様な人材を引き付け、雇用し続けるために何が必要なのか。3社の取り組みからその糸口を探る。

コピーライターとして、1980年代の寵児だった糸井重里氏。その糸井氏が「クリエイティブがイニシアティブを握る新たなメディア」として1998年に立ち上げたのが、『ほぼ日刊イトイ新聞』である。20年以上にわたり読者から支持される人気サイトでありながら、インターネットメディアの常套手段であるサブスクリプション(定期購読)も広告掲載もいっさい行っていない。話題のニュースを追いかけて、ページビューを稼ぐわけでもない。にもかかわらず、高収益サイトとして自走できるのはなぜなのか。 その運営会社であるほぼ日は、2017年に東京証券取引所のジャスダック市場(現スタンダード市場)に上場を果たした。しかも糸井氏は、上場後初の株主総会の席で「株価や売上高を目標としない」と公言。総会後の株主ミーティングでは、「会社は株主のものではない」というメッセージを発信した。のっけから個性全開の上場だったのである。「時代に合わせすぎないことでしか、自分たちの役割は見つからない」と断言し、株式会社に人間的な人格を吹き込んでいるように見えるほぼ日。糸井氏の信念を形にした企業から、我々が学ぶことは多いはずだ。

急速に深刻さを増している「人手不足」。求める能力やスキルを持った人が足りない「人材不足」と混同されがちだが、働き手そのものが足りない人手不足は産業界全体にとってより深刻だ。その背景には、私たちが長期的に向き合わなければならない構造的問題である「人口減少」があり、それに伴う生産年齢人口の減少は、企業にとって避けて通れない経営課題となっている。この不可逆に進行する人口減少を、悲観的ではなく、むしろチャンスととらえるべきだと主張しているのが、京都大学 人と社会の未来研究院の広井良典教授である。拡大成長による成功体験を捨て、持続可能な社会と経済を実現させる「定常型社会」を提唱する広井先生に、人口減少時代における未来社会の姿と企業が生き残る道についてお聞きした。

資源を循環させるサーキュラーエコノミー(CE)の潮流は世界へ広がり、ヨーロッパでは法規制による標準化が加速する。では、日本ではどのように進めていくべきか。そのヒントとなるのが、イオングループの取り組みだ。イオンの鈴木隆博氏とその取り組みを支援する日本総合研究所(日本総研)の猪股未来氏が、CEの要諦と未来のビジョンについて語り合った。

人類の未来を変えるかもしれない量子技術の分野で、産業界の牽引役を担う東芝。同社はいち早く量子研究に取り組み、量子暗号通信では世界でも高い競争力を誇っている。島田太郎社長は、「インターネットがもたらしたのと同じか、それ以上の社会と産業構造の変化が、量子技術によって再び引き起こされる」と語る。経営再建中の東芝は、あらゆるものが「つながる」時代に向けた新産業創出で、第二の創業を果たせるのか。量子産業の潜在可能性と、東芝の勝ち筋を島田社長に聞jく。

妹尾堅一郎氏(産学連携推進機構 理事長)のロングインタビュー前編では、本格到来が迫る資源循環経済に向けた処方箋として、「使い続けのモノづくり」を中心とした新たなビジネスモデルへの転換を提唱された。それを踏まえた次なる議論が、後編のテーマとなる「イノベーション」である。妹尾氏は、「日本では企業の内外でイノベーションが濫用され、“何となく・何でもイノベーション症候群” が蔓延している」と警鐘を鳴らす。資源循環経済に向けて、日本企業の宿題といえるイノベーションをどう攻略していくべきなのか。ビジネスモデル研究の第一人者ならではの鋭い考察をお届けする。

大量生産・大量消費・大量廃棄の「線形経済」から、持続可能性を高める「循環経済」への移行は地球規模の大テーマだ。企業にとっては売り切り型から“使い続け”型へのコペルニクス的転回を意味する難事業だが、サステナビリティや経済安全保障などの社会的課題と企業成長を同時に実現できる大きなチャンスでもある。B2CとB2Bの領域において、使い続けモデルへのトランジションに挑む2社の事例を紹介する。

「実験の力」でビジネスの成功率を向上させる【後編】
世界的ベストセラーとなった『コア・コンピタンス経営』(共著者:コイムバトーレ K.プラハラード)の著者で、ロンドン・ビジネススクール客員教授のゲイリー・ハメル。『ウォール・ストリート・ジャーナル』紙が選ぶ「世界で最も影響力のあるビジネス思想家」の一人でもある彼が、MITプレス発行の論文誌『Innovations』に発表した論文「実験の力」( The Power of Experimentation )の翻訳全文を、2回にわけて掲載する。
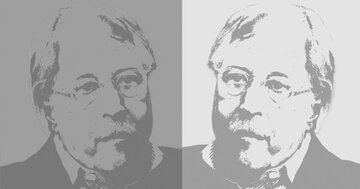
企業には社会変革を促すような経営・事業変革が求められ、長期的かつ持続的に企業価値の向上を図る必要がある。これを、サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)という。しかし、その実践は容易ではない。 社会変革をもたらす真の企業変革実現のため、経営者に求められる「覚悟」とは。伴走型の支援でSXの実践を促すKPMGサステナブルバリューサービス・ジャパンの土屋大輔氏と安東容載氏に、その要諦を聞いた。
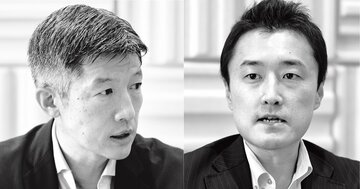
長きにわたる我が国の停滞は、不確実性を過度に恐れ、リスク回避を優先し、イノベーションと価値創造の活力を失ったことが要因といえる。ダウンサイドリスクを適切に管理しながらも、あるべき未来を創造するための挑戦や投資のモメンタムをいかに高めるか。過去8年で時価総額を10倍以上に伸ばした東京エレクトロン。今回は、コーポレートオフィサーの一人、長久保達也氏に同社が標榜する「攻めと攻めの経営」の神髄を聞く。

サステナビリティ経営を掲げる企業が増える中で、「循環経済」という言葉がよく聞かれるようになった。だが、循環経済というと「3R」(リデュース、リユース、リサイクル)、極論すればゴミ対策の一環として語られることが少なくない。つまり「環境汚染」問題としてとらえる人がほとんどだ。だが、循環経済の根底には、「資源枯渇」「資源調達」という問題も潜んでいる。「この難問を解決する策は、いまのところ循環経済以外に見つかっていない」と語るのは、ビジネスモデル研究の第一人者である妹尾堅一郎氏である。大量生産・大量消費・大量廃棄をベースとする線形経済から、極小生産・適小消費・無廃棄という循環経済への経済モデルのパラダイムシフト、つまりは「買い替え経済」から「使い続けの経済」への転換が不可欠であるという。モノが売れなくなる循環経済下で、企業はどう稼いでいけばよいのか。まさにビジネスモデルの大転換を迫られている。
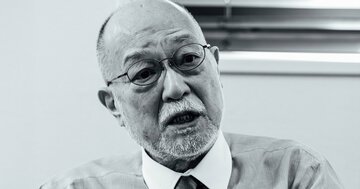
誰がためにイノベーションはあるのか?
『イノベーションのジレンマ』(翔泳社)で知られるクレイトン・クリステンセンは、2020年1月23日、67歳で他界した。今回紹介する「第3の解」は、逝去する1カ月前、MITプレスが発行するジャーナル『イノベーションズ』誌に掲載されたもので、これまで未訳のままだった。『ダイヤモンドクォータリー ニューズレター』の発行に当たり、その邦訳を連載していく。

