2020年6月1日に「改正労働施策総合推進法」(パワハラ防止法)が施行され、大企業の事業主にはパワハラ防止対策が義務付けられた。2022年4月1日には中小企業にも適用され、日本全体でパワハラは許されなくなった。この立法の背景には、職場における過労死や自殺、精神障害などが、多くの場合、いじめや嫌がらせ、言葉の暴力に起因していることがある。このような状況下にあって、あらためて注目されているのが、相手を尊重しつつ自分の意見を正当に主張し、理解してもらうコミュニケーション手法といわれる「アサーション」である。その伝道師【エバンジェリスト】であり、30年以上にわたって職場内のコミュニケーションの問題と向き合ってきた臨床心理士の平木典子氏に、アサーションの何たるかを聞く。

鮎川義介日産自動車をつくった男を再発見する
鮎川義介は「あいかわ・よしすけ」と読む。日産自動車創業の立役者である。しかし私見ながら、トヨタ自動車の豊田(とよだ)喜一郎――彼の妻と鮎川の妻は従姉妹同士であり、よってトヨタと日産の創業者一族は縁戚関係にある――や本田技研工業の本田宗一郎と同じような社会的認識は得られていないように思う。この機会に、まず鮎川の実業家としての経歴を駆け足でなぞってみよう。

人的資本経営の論点
『ダイヤモンドクォータリー』は創刊6周年を迎え、2023年3月10日にオンライン形式で記念フォーラムを開催した。テーマは「人的資本経営」。数ある経営課題の中でも、とりわけ人事や人材育成は経験則で語られることが多く、誤解や曲解が入り込みやすい分野である。今回はアカデミアから4人の専門家と、産業界から4人のプロフェッショナルをお招きして、2つのパネルディスカッションを実施。人的資本経営の本質について議論を深めた。本記事は、その要旨をまとめた採録である。

経営を中心として情報技術と社会構造の関係を長く研究してきた慶應義塾大学教授の國領二郎氏によれば、時代はいま近代工業文明からサイバー文明への転換期にある。中核的技術は化石エネルギーからデジタル技術へ、権力の源泉である富は貨幣から「信頼」へと移り変わり、信頼をベースに多様なプレーヤーが価値を創発する新たな統治機構が求められていると説く。その統治機構とは、どのようなものか。そして、企業はどう変化していくべきなのか。國領氏の提言を聞く。

人はパンのためだけに働くわけではなく、組織への愛着や人間関係、その組織でしか得られない知識や経験に何より価値を置いている。これは「シグニチャー・エクスペリエンス」と呼ばれ、従業員の維持(リテンション)を考えるうえで極めて重要であると同時に、その組織で鍛錬を重ねてきた人材こそが企業成長のカギを握る「差異性」を生み出すという。未曾有の危機の中でそのことに気づかされたANAホールディングス芝田浩二社長との対話から、働きがい、組織と従業員の関係、さらには人的資本経営の針路について考えてみたい。

今回のコロナ禍で一挙に普及したテレワークだが、アフターコロナにはリアルとオンラインの使い分け、これまで以上に賢い使い方など、言わば「コミュニケーションの再創造(リインベンション)」が要求される。会社と従業員の関係が様変わりし、多様なステークホルダーとの対話が求められるいま、特にリーダーにはコミュニケーション力のリスキリングが欠かせない。そこで、『対話のレッスン』(講談社学術文庫)などの著書がある平田オリザ氏に、「多文化共生」社会におけるコミュニケーションのあり方を学ぶ。
![[リーダー必修]コミュニケーション力のリスキリング](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/1/8/360wm/img_18136a53f8aaf5f40dcd9b09fa4a60e5119914.jpg)
デロイト トーマツ コンサルティングの戦略コンサルティング部門であるモニター デロイトは、デジタル時代における「人・物・金・情報」に続く第5の経営資源として「コミュニティ」を位置付ける。企業による一方的な価値提案ではなく、企業がステークホルダーとともに価値を共創していく時代においては、パーパスとデジタルでつながったコミュニティが大きな力を発揮するからだ。

安田善次郎「銀行王」と呼ばれた男の素顔
1921(大正10)年9月28日、安田財閥(現芙蓉グループ)の始祖、安田善次郎は、自宅に押し入ったテロリストの凶刃に倒れた。享年82。犯行動機は、善次郎が巨万の富を築き上げながら、社会的な責任を果たしていない、よって天誅を下さなければならない、というものだった。このテロリストの弁が一人歩きしたことで、善次郎は金の亡者、守銭奴というイメージがついてしまった。しかし、こうした評価は事実に反するものであり、実像から大きく外れている。

カーボンニュートラルに向けたエネルギートランジションの手法として、燃料アンモニアの活用を推進しているのはG7(主要7カ国)で我が国だけである。これは国際社会における異端の道なのか、あるいは科学的、合理的な脱炭素アプローチなのか。政府の総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の委員であり、エネルギー産業論の専門家である橘川武郎氏に聞いた。

データの価値が飛躍的に増大する中、世界各国で国家レベルでのデータ戦略がますます重視されている。巨大プラットフォーマーが主導するアメリカ、欧州委員会が域内市場とルール形成をリードするヨーロッパ、国家がデータを統治する中国など、その戦略は各国・地域によって異なる。データ戦略の基本ビジョンとして「Society 5.0」を掲げる我が国は、人間中心のデータ駆動型社会をいかに実現していくべきか。第3次情報革命としての「アンビエント情報社会」を提唱してきた、大阪大学総長の西尾章治郎氏に聞いた。

Daigasグループが掲げる3つのグループマインドの一つであり、同社の価値観として受け継がれてきた「進取の気性」。進取とは、既存の常識や旧弊に囚われることなく、積極的に新しいこと(サムシングニュー)に挑戦することを意味するが、さまざまな産業の揺籃期や変革期において、その後の優勝劣敗を決定付けてきた態度でもある。革新的なメタネーションモデルの開発をはじめ、多様な新規事業やイノベーション創出に成功している大阪ガスに、進取の重要性を学ぶ。

NTTグループが2020年に発表した「IOWN(アイオン)」は、パラダイムシフトを起こし、世の中を塗り替えるといわれている。光技術によって電気が光に置き換わると、通信や伝送はもとより、エネルギー消費において桁違いのインパクトがもたらされるからだ。IOWN構想の発案者であり、現在はその推進者である川添雄彦氏に、IOWNとは何か、このラディカルイノベーションをいかに普及させていくのか、その戦略を聞く。

グループ経営では、遠心力と求心力を同時に働かせるマネジメント、リーダーシップが要求されるといわれる。とはいえ、規模が大きければ大きいほど、矛盾やジレンマ、その結果としてのコンフリクトなど複雑さが増すため、けっして一筋縄ではいかない。こうした割り切れない問題であふれている、連結従業員数34万人超という大組織の改革を推進する島田明社長いわく「最後は人である」。本インタビューでは、人間第一主義の島田流のグループ経営の要諦を聞く。

“Digitize or Die”(デジタル化しなければ消えるしかない)というキャッチーな警句が飛び交うようになったのは、2014年ないしは2015年といわれている。こうしたビジネスジャーゴンは短命で終わることが多いが、デジタルトランスフォーメーション(DX)はいまなお経営課題の一丁目一番地であり、多くの企業がまだ試行錯誤の域にある。そこで本誌では、オムロンの代表取締役社長CEOの山田義仁氏をお招きし、ものづくり現場の革新を生み出す「企業理念経営」について講演していただいた。併せて、製造業のキーパーソンによるパネルディスカッションも実施。現在進行形でDXに取り組むクボタ、京セラの事例をひも解きながら、「製造業DXの現在地と未来」について考えたい。
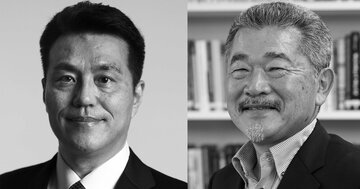
DXを進めなければ、2025年以降、毎年最大12兆円もの経済損失が生じる──経済産業省がまとめた『DXレポート』は、日本の多くの経営者を驚かせた。製造業も他人事ではない。少子高齢化・労働人口の減少に伴う人材難などを見ても、製造業DXは喫緊の課題である。アクセンチュアは、そんな製造業DXを牽引するキーワードとして「デジタルツイン・エンタープライズ」を挙げる。デジタルツインの全体像や導入の課題について、アクセンチュア インダストリーX本部で「エンジニアリング&マニュファクチャリング(設計&製造)」日本統括/マネジング・ディレクターを務める河野真一郎氏が、ダイヤモンドクォータリー創刊6周年記念フォーラムに登壇し、明快に語った。

これまでの経営管理ソフトウェアは、財務経理部門の業務改善という視点からデザインされていた。だが、事業価値や顧客価値を生み出しているのは「現場」であり、事業構造と現場の活動を見据えて、経営管理のあり方を再設計すべき時に来ている。企業が構築すべき次世代経営管理プラットフォームのあり方を、フュージョンズCEOの杉本啓氏に聞く。

「変革マネジメント力」こそ強力な無形資産である
“Digital or Die”(デジタルか死か)といわれ始めたのはいつだったか、いまから10年ほど前ではなかろうか。以降、日本でも多くの企業が「DX」を掲げ、あらゆる現場でデジタル変革が進められてきた。言わば「変革の日常化」が起きている様相だ。しかし、デジタル化ばかりに囚われ、肝心の「何を」変革するのかが定まっていない企業も少なくない。にもかかわらず、社内にはさまざまな変革プロジェクトが動き出している。こうした状況下で、DXの旗振り役を担うCDO(チーフデジタルオフィサー)をはじめとする経営者はどう対処すべきか。日常化した変革をマネージする手腕が問われている。

江副浩正ア・マン・オブ・アスピレーション
私がこれまで袖振り合った経営者は数多くあったけれども、江副さん、その先輩である森さん、そして大塚製薬の大塚明彦さんの3人は、まさに「考える人」だった。とにかくいつも繰り返し考えていた。現在、県立広島大学のビジネススクールと、10年やって正式には引退したはずの東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラムに関わっているが、多くの受講生がお題目や常套句を安易に使い、自分の言葉で語らない。したがって、自分が何を知らないか知らないし、深く考えられない。彼らだけに限らない。多くの企業人たちが、DXとかパーパスとか、昔の焼き直しのジャーゴンに疑いもなく飛び付いている。しかし、企業を成長させ、人々を駆動させるには、何より「アスピレーション」(「こうなりたい」という熱烈な願望)が欠かせない。江副さんは、まさにアスピレーションの塊のような人だった。

企業とは理想に向かって直線的に進化するものではなく、変化する環境に適応しながら紆余曲折しつつ、目標に向かうものである。そして、人や組織のマネジメントのあり方は、歴史、地理、政治、文化、技術などさまざま影響を受けながら変化する。古代文明から現代までを巨視的なパースペクティブでとらえた『マネジメントの文明史』の著者に、近未来の展望を聞く。

つい忘れがちであるが、脱炭素は一種の記号であり、そこには生物多様性や生態系など「自然資本」の毀損を食い止めるという目的が含意されている。近年、この自然資本を、維持・保全の域を超えてリジェネレーション(再生・拡大)していこうという「ネイチャーポジティブ」と呼ばれる取り組みが注目され始めている。では、ネイチャーポジティブの手本を探してみると、やはり自然資本を利活用している事業体が真っ先に浮かんでくる。そこで、300年以上にわたって自然資本と寄り添ってきた住友林業の光吉敏郎社長に、同社の取り組みについて聞くことで、ネイチャーポジティブ経営のヒントを見つけたい。

