
加藤 出
第204回
バイデン米副大統領は8月に北京を訪問した際、大衆食堂「桃記炒肝店」でランチを食べた。彼が地元客と談笑している様子は、中国のメディアで大きく取り上げられ、「麺外交」と呼ばれた。

第203回
日本では中国の最近の住宅市場の調整をとらえて、「ついに中国バブル崩壊か?」というニュアンスの報道がよく見られる。しかし、この調整は当局が意図したものだ。システミックリスクにつながりそうになったら、当局は急速に緩和に転じるだろう。

第202回
ブッシュ(父)元米大統領は、1992年の大統領選敗北について、グリーンスパンFRB議長への恨みを後のインタビューで語っていた。一方、来年の米大統領選で、オバマが再選される確率が成長率によってどう影響されるかというN・シルバー氏の予想を「ニューヨークタイムズ」が掲載している。

第201回
政府・日銀は10月31日に大規模な円売り・ドル買い介入を実施し、1ドル=75円は割らせない意思を示した。外国為替市場に警戒心を抱かせる効果は当面あるだろう。とはいえ、欧米の経済状況から判断すると、円高圧力は今後も続きやすい。

第200回
強烈なポジティブシンキングが、経済格差の激しい米国をこれまで支えてきた。だが、景気低迷の長期化に伴ってアメリカンドリームは揺らぎ、ウォール街の高額報酬に対する抗議活動が激しくなっている。

第199回
インフレ抑制のための金融引き締めの影響で、中国の第3四半期の実質成長率は+9.1%へと低下した。しかし、減速したとはいえ9%台である。先日行った北京は、上海以上にバブリーな空気が満ち溢れていた(富裕層は北京が最も多い)。

第198回
中国のトップ女優の1人、徐静蕾が主演・監督した映画「杜拉拉の昇進記」が昨年中国でヒットした。主人公ララ(拉拉)が北京の華やかな外資系大企業で、異例の昇進を果たしていくという話だ。現代中国のビジネス社会の世相がわかる映画である。

第197回
共和党の主要な大統領選候補者は、いずれもバーナンキFRB議長を激しく批判している。彼らは、デフレ回避を最優先にしてきたバーナンキのスタンスに共鳴していない。9月21日にFRBが“QE3”ではなく、「オペレーションツイスト」を採用した理由の一つに、こうした批判の存在が挙げられる。

第196回
米国で売られている日本製品が、現地のインフレに沿って値上げされてきたなら、為替レートは大幅な円高になっていても、日本の輸出企業は赤字にならないはずだ。ところが、日本の製造業が勝負している耐久消費財は、米国では20年で▲2%というデフレだ。

第195回
9月から上海に長期出張している。日欧米の金融市場関係者やマスメディアは、「中国の内需は失速しないか?」と心配している。しかし、中国では逆に「海外経済は大丈夫か?」と警戒する論調が多い。とはいえ、上海の街を歩くと、バブリーな人びとの勢いは衰えていないことに気づかされる。
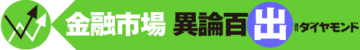
第194回
スイス国立銀行(中央銀行)は9月6日にユーロの対スイスフランの下限レート(1.20フラン)を設定。徹底介入により通貨高を阻止するという。日本政府がスイスの今回の決定をまねできるかというと難しい面がある。

第193回
最近、多くの債券市場参加者が最大のリスク要因として警戒し始めているのは、政府が日銀に国債の直接引き受けを要請することだ。財政再建に前向きな野田政権の誕生で、当面そのリスクは後退したとはいえ、与野党問わず、日銀国債引き受けを“財源”にすればよいと考える議員は非常に多い。
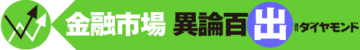
第192回
民主党の有志による「デフレから脱却し景気回復を目指す議員連盟」は8月23日に緊急声明を出し、QE1、QE2に匹敵する政策を行うよう日銀に求めたという。興味深いことに、非常に対照的な議論が米国で話題になっている。
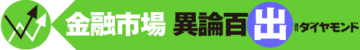
第191回
“超円高”といわれるが、インフレ率を勘案した実質レートで見れば様相はまったく変わってくる。たとえば日本に住んでいる人が10年ぶりにニューヨークに旅行に行くとしよう。ドル円レートはこの間におよそ36~38%上昇している。

第190回
ニューヨークのタイムズスクエア近くのビルの壁面に、「政府債務時計」の電光掲示板がある。米議会での政府債務上限引き上げ議論が新聞、テレビで連日大きく報じられていたため、同電光掲示板を見上げる通行人や観光客の姿が一時期多く見られた。
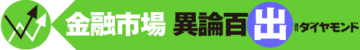
第189回
米国のマネーストック(マネーサプライ)M2が6月下旬から7月初めにかけて驚くほど急増した。6月22日から7月4日までの2週間で1646億ドルの増加(季節調整後)であり、リーマン・ブラザーズ破綻以降最大である。四半期末という季節要因も影響しているが、原因はそれだけではない。

第188回
米国経済の先行きに不透明感が漂っているが、農業を主産業とする州では様相が驚くほど異なっている。新興国の需要増大をベースにした穀物価格高騰が、農家の所得を急激に増大させ、その波及効果で従来は地味だった地域に経済ブームが起きている。

第187回
日銀はさまざまな手段を使って、じゃぶじゃぶに資金を供給しており、市場では強烈な資金余剰が続いている。一方で、被災者には保険金が入ってきており、多くの地方金融機関で預金が増加している。被災地での復興用の資金需要はまだ顕著には出てきおらず、運用難に直面している地方金融機関は多い。

第186回
「これは、マーケットにとってのヴイックスヴェポラッブ。治療にはならないが、症状は和らげた」。「ウォールストリート・ジャーナル」(6月28日)は、FRBのQE2(量的緩和策第2弾)に対するエコノミストの評価を掲載した。

第185回
先日の欧州出張時に、日本で買ったガイガーカウンター(放射線計測機)を持っていった。といっても数十万円もする本格的な機種は買えないので、5万円弱のお手軽な中国製である。
