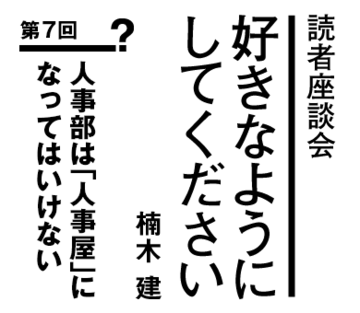楠木 建
【こりゃ最強だ】「超信頼されている人」の特徴・ベスト1
優れたリーダーは、「自分の感情」よりも「チームの成功」を意識している。ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再生し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「成功し続ける人になる秘訣」を紹介する。

「そりゃ仕事できるわ…」大事なプレゼンの場面、三流は何も準備しない、二流は原稿を準備する。では、一流は?
ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再建し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「成功し続ける人になる秘訣」を紹介する。

モルガン・スタンレー元CEOが語る「厳しい父」のおかげで得た2つの資質
世界の成功者の1人であるジェームス・ゴーマン(モルガン・スタンレー元CEO)は経験からの小さな学びを大事にしていた。ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再生し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「できる人になる秘訣」を紹介する。

部下が絶対一緒に仕事をしたくない上司の口癖・ナンバーワン
「信頼されるリーダー」と「嫌われるリーダー」の違いを決めているのは、特別な才能でもなく、経験からの小さな学びだ。世界の一流たちは、小さな学びを意識することで成功してきた。ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再生し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「人生も仕事も成功し続ける秘訣」を紹介する。

「できる人」と「できない人」を決定的に分けるたった1つの習慣
「できる人」と「できない人」の違いを決めているのは、特別な才能でもなく、経験からの小さな学びだ。世界の一流たちは、小さな学びを意識することで成功してきた。ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再生し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「人生も仕事も成功し続ける秘訣」を紹介する。

「圧倒的に成功しているのに、なぜ破滅的な行動を取るのか?」イーロン・マスクの「自爆的な行動」に見る成功者の心の闇
世界累計600万部突破のベストセラー作家が描く、イーロン・マスクによるツイッター社買収の“驚愕の舞台裏”。極上ノンフィクションとして読み応え抜群の1冊。話題の『Breaking Twitter』発売を記念して、一橋大学・特任教授の楠木建氏に本書の魅力を寄稿いただいた。

イーロン・マスクのTwitter改革がことごとく失敗した「たった1つの理由」とは
世界累計600万部突破のベストセラー作家が描く、イーロン・マスクによるツイッター社買収の“驚愕の舞台裏”。極上ノンフィクションとして読み応え抜群の1冊。話題の『Breaking Twitter』発売を記念して、一橋大学・特任教授の楠木建氏に本書の魅力を寄稿いただいた。

「彼に感情はないのか?」イーロン・マスクという「冷酷な天才」の正体
世界累計600万部突破のベストセラー作家が描く、イーロン・マスクによるツイッター社買収の“驚愕の舞台裏”。極上ノンフィクションとして読み応え抜群の1冊。話題の『Breaking Twitter』発売を記念して、一橋大学・特任教授の楠木建氏に本書の魅力を寄稿いただいた。

新型コロナウイルス禍により、日本経済は大きなインパクトを被った。足もとでは、世界的な利上げ観測やロシアのウクライナ侵攻によって円安、インフレが進行し、予断を許さない状況が続く。こうした不確実性を乗り越え、経営を「進化」させていくために、企業はどんな指針を持つべきか。一橋ビジネススクールの楠木 建教授に、競争戦略の要諦を聞いた。強い競争戦略の事例と企業が目指すべき経営の目的とは。

新型コロナウイルス禍により、日本経済は大きなインパクトを被った。足もとでは、世界的な利上げ観測やロシアのウクライナ侵攻によって円安、インフレが進行し、予断を許さない状況が続く。こうした不確実性を乗り越え、経営を「進化」させていくために、企業はどんな指針を持つべきか。一橋ビジネススクールの楠木 建教授に、競争戦略の要諦を聞いた。日本経済を覆う不確実性の正体と、企業が被った影響の本質とは。

高収益企業として注目を集めているワークマン。成熟した国内アパレル市場を主戦場としているにもかかわらず、ここ5年間の平均ROIC(投下資本収益率)で12.6パーセンテージポイント、平均ROS(営業利益率)で14.5パーセンテージポイント、それぞれ業界平均を大きく上回るパフォーマンスを出している。その成功の裏には優れた「戦略ストーリー」がある。

人間・松下幸之助の姿
「経営の神様」こと松下幸之助(1894~1989年)。数限りなくある評伝の中で、異彩を放つ。“正史”には書かれなかった人間性を描く。真の姿を知ることで、かえって幸之助への尊敬が募る。

読書したくなる、書評集
書評こそ最高の本選びの友。インターネット上の匿名の評価や星の数(の平均値)は参考にならない。プロの書評はレベルが違う。気が合う書き手が見つかったら、その人の書評に目を通す。これが本選びの王道だと心得ている。

大富豪の優れた人間洞察
祖父はギリシャの元首相、父は海運王という名門の出の著者が、上流社会の人々の行動様式について考察したコラム集。世界中のセレブリティーと直接的な交流があっただけに、その洞察にはキレとコクがある。

犯罪被害者の権利を守る
1999年に起きた光市母子殺害事件。ある日突然、最愛の妻と生後11ヵ月の娘を失った夫は、絶望の奈落へと落とされる。犯人は少年法に守られた18歳で、一審・二審とも判決は無期懲役。夫は司法の壁への挑戦を決意する。

経営学は科学であり、実学である。慶應義塾大学の琴坂将広准教授によるそんな問題提起がきっかけとなり、一橋大学の楠木建教授からこの問題を一緒に考えたいという提案をいただき、両者の対談が実現。実務から学問の道へと進んだ琴坂氏と、学問の道で探究し続けて来た楠木氏。2人の気鋭の経営学者が、それぞれ異なる立ち位置からこの難題に対する見解をぶつけ合った。対談後編。
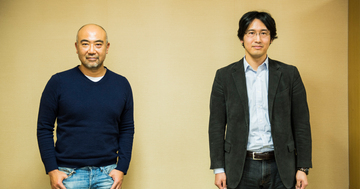
経営学は実学であり、科学である。慶應義塾大学の琴坂将広准教授によるそんな問題提起がきっかけとなり、一橋大学の楠木建教授からこの問題を一緒に考えたいという提案をいただき、両者の対談が実現。実務から学問の道へと進んだ琴坂氏と、学問の道で探究し続けて来た楠木氏。2人の気鋭の経営学者が、それぞれ異なる立ち位置からこの難題に対する見解をぶつけ合った。対談は前後編の全2回。

経営学は実学であり、科学である。慶應義塾大学の琴坂将広准教授によるそんな問題提起がきっかけとなり、一橋大学の楠木建教授からこの問題を一緒に考えたいという提案をいただき、両者の対談が実現。実務から学問の道へと進んだ琴坂氏と、学問の道で探究し続けて来た楠木氏。2人の気鋭の経営学者が、それぞれ異なる立ち位置からこの難題に対する見解をぶつけ合った。対談は前後編の全2回。

第8回
「好きなようにしてください」が成り立つ、暗黙の条件
人事部の仕事の本質から、なぜ人事部が制度設計に走りやすいのかまで、過去2回にわたって考えてきた座談会。最終回では、どうすれば組織で「好きなようにしてください」が成り立つのか、深堀します。
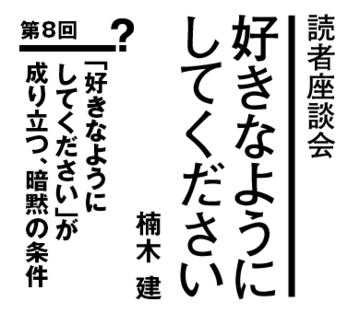
第7回
人事部は「人事屋」になってはいけない
制度をつくることに終始したり、他社の事例を追いかけたり…。人事に対して楠木氏が抱くイメージを、実際に人事部門で働く3名にぶつけます。楠木氏のイメージを覆す、3人の意見に注目です。