
鈴木貴博
富士通が携帯電話事業を売却すると報じられた。これで残された日本メーカーはソニー、シャープ、京セラの3社のみとなる。通常の市場なら1社の撤退で相応の残存者利益を享受できるが、携帯市場は様子が異なる。彼らは生き残ることができるか。

先日、興味深いニュースが出た。グループ会社で仮想通貨取引所も運営している金融情報サービス企業のフィスコが、ビットコイン建て社債を発行したというのだ。実際のところ、ビットコイン建ての債券で安全な資金調達はできるのか。

夏休みといえば読書である。夏休みは読書をしたい。そんなビジネスパーソンに向けて、私から「ナナメ目線」で選んだ何冊かの本を推薦したい。ビジネススキルの向上には役立たないが、きっと人生を見直すための参考になるに違いない。

北朝鮮がミサイルを発射しても日本人はあまり騒がなくなってきた。北朝鮮騒動に「慣れてきた」という言い方の方が正しい。しかし、現実を見るとそんなことは言っていられない。過去、安定した日々が突如暗転する事態には、必ず予兆があった。

先日、「大変なことになる!」とITビジネス通たちを唸らせるニュースが米紙で報道された。ソフトバンクが、配車サービス最大手のウーバーに大規模出資を打診しているというのだ。この報道が暗示するものは、タクシーを含む日本の自動車市場の激変だ。

日本の夏は明らかに暑くなっている。もはや猛暑というより酷暑だ。実は、こうなることを10年以上も前にスパコンが予測していたことをご存知だろうか。それによると、今後はもっとひどいことになる。もはやこれまでの夏の常識は通用しない。

リクルート『SUUMO』が毎年発表する「関東版 住みたい街ランキング」で、今年も異変が起きている。同じ「穴場地区」の中で、昨年上昇した赤羽などがランクダウンし、代わりに北千住などがランクアップしているのだ。背景にどんな事情があるのか。

今、流行りの「睡眠負債」という言葉。1時間ずつ2週間分の睡眠不足で、2日間の徹夜なみに生産性が低下し、深刻な病気の原因になるという、恐ろしい分析結果があるのだ。心当たりのあるビジネスパーソンが生活を改善するための心得とは?

エアバッグ問題への対応が後手に回り、窮地に陥った大手自動車部品メーカーのタカタが、民事再生法の適用を申請した。しかし、退任に追い込まれた高田重久会長兼社長はどこか他人事。背景には、創業家支配における独特な経営観がありそうだ。

日本国内でビットコインで代金を支払うことができる店舗数は、26万店を超えたそうだ。国内でアリペイが本格展開される見通しも出てきた。だが、仮想通貨や電子マネーが国内で普及していると言われても、当の日本人がピンと来ないのはなぜか。

ファミリーマートとドン・キホーテが業務提携を発表した。小売業の中で業態が重複しないので手を組みやすいという理由には、違和感を唱える声がある。しかし「初めからシナリオありき」なら、両社の提携は大きなメリットを生む可能性がある。

受験最大手のナガセが、「早稲田塾」の校舎を大量閉鎖すると発表した。同じナガセの傘下でも東進ハイスクールは好調だが、明暗はどこで分かれたのか。実は、少子化だけでは語り切れない構造変化の波が、受験産業に押し寄せているのだ。
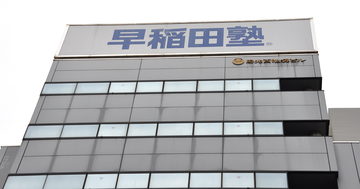
受動喫煙リスクが取沙汰されるなか、受動喫煙対策の切り札と見られていた「加熱式タバコ」までもが、健康増進法改正案の議論に翻弄されている。これには、政治的な思惑が実に複雑に絡んでいそうだ。現在の受動喫煙議論は「まとも」なのか。

過去最高益が視野に入り、復活を印象付けたソニー。しかし、平井CEOが挙げたある言葉が気にかかった。それは、リカーリング型ビジネスモデルの強化だ。ソニーには、悪いリカーリング型ビジネスモデルのせいで凋落した過去があるからだ。

先日、東芝が監査法人から「意見不表明」の状態で2017年3月期の巨額赤字見通しを発表するという、前代未聞の事態が起きた。東芝や日本郵政を窮地に追い込んだ「のれんの減損」とは何か。多くの優良企業が抱えるリスクの正体を解説する。

低迷するフジテレビの改革を期待された亀山千広社長の退任が決まった。後任社長は亀山氏よりかなり年上で、改革のイメージからは遠く、同社の今後に不安の声が募る。しかし、この人事はフジがようやく復活するきっかけになるかもしれない。

第52回
ヤマト運輸は、9月をめどに27年ぶりに基本運賃を5%~20%引き上げることを発表した。背景には、宅配便の取扱量の急増と荷物単価の減少による収益悪化がある。ただ、運賃の値上げだけで宅配便業者が苦境から脱することは難しいだろう。

厚労省にアルコール健康障害対策推進室が設置され、「政府によるアルコール規制がどこまで進むのか」とネット上で不安が広がっている。厚労省は「あくまで議論はこれから」と言っているが、飲酒が厳しく規制される可能性は否定できない。

ユナイテッド航空が降機を拒否した乗客を機内から引きずり出し、流血させた事件は、同社自身や株主に多大な損害を与えた。なぜこんなことが起きたのか。航空業界のコンサルティングを多く経験した立場から、背景にある業界特有の課題を斬る。

シリコンバレーの新興自動車メーカーであるテスラモーターズが時価総額でフォードを抜き、米国自動車メーカ―2位に躍り出た。市場は沸き立っているが、これは同社の真の実力なのか。その強みを検証し、世界の自動車市場の未来図を考える。
