竹田孝洋
#8
経済学者や経営学者、エコノミスト138人が選んだ経済、経営に関わる良書をランキング形式でお届けする特集『ベスト経済書・ビジネス書大賞2022』。今回のアンケートでは、日本経済の活路の指針となる書についても、識者に挙げてもらった。複数票を集めた厳選4冊を紹介する。

#7
経済学者や経営学者、エコノミスト138人が選んだ経済、経営に関わる良書をランキング形式でお届けする特集『ベスト経済書・ビジネス書大賞2022』。第11~21位に入った経済書を、選者の「推薦の言葉」とともに紹介する。識者が評価している点や注目している点を読んで、書を選ぶ際の参考にしてほしい。

#6
経済学者や経営学者、エコノミスト138人が選んだ経済、経営に関わる良書をランキング形式でお届けする特集『ベスト経済書・ビジネス書大賞2022』。第5~10位に入った経済書を、選者の「推薦の言葉」とともに紹介する。識者が評価している点や注目している点を読んで、書を選ぶ際の参考にしてほしい。

#5
経済学者や経営学者、エコノミスト138人が選んだ経済、経営に関わる良書をランキング形式でお届けする特集『ベスト経済書・ビジネス書大賞2022』。3位の『スタートアップの経済学 新しい企業の誕生と成長プロセスを学ぶ』の著者、加藤雅俊・関西学院大学経済学部教授兼アントレプレナーシップ研究センター長に、起業成功の条件について語ってもらった。
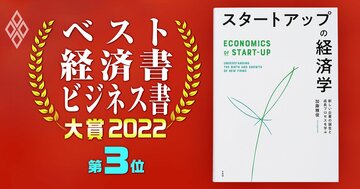
#4
経済学者や経営学者、エコノミスト138人が選んだ経済、経営に関わる良書をランキング形式でお届けする特集『ベスト経済書・ビジネス書大賞2022』。3位の『経済社会の学び方 健全な懐疑の目を養う』の著者、猪木武徳・大阪大学名誉教授に、経済社会を学ぶにあたっての“健全な懐疑”の大切さについて語ってもらった。
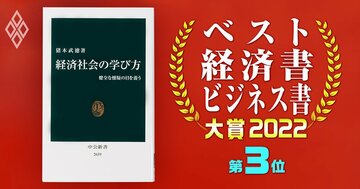
#3
経済学者や経営学者、エコノミスト138人が選んだ経済、経営に関わる良書をランキング形式でお届けする特集『ベスト経済書・ビジネス書大賞2022』。2位の『中小企業金融の経済学』の著者、植杉威一郎・一橋大学教授に、本書で解明したかった問い、中小企業金融の実態について語ってもらった。
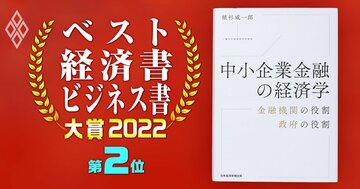
#2
経済学者や経営学者、エコノミスト138人が選んだ経済、経営に関わる良書をランキング形式でお届けする特集『ベスト経済書・ビジネス書大賞2022』。1位の『物価とは何か』の著者、渡辺努・ 東京大学大学院経済学研究科教授に、本書を表した動機、物価の面白さについて語ってもらった。
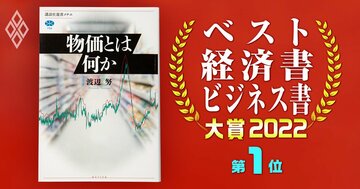
#1
経済学者や経営学者、エコノミスト138人が選んだ経済、経営に関わる良書をランキング形式でお届けする特集『ベスト経済書・ビジネス書大賞2022』。40 年ぶりの高インフレと大幅な円安に見舞われた日本経済。2022年のベスト経済書の顔触れにもそうした世相が反映され、物価や金融政策に関する書がランクインした。加えて、起業や中小企業の在り方を探究したものも上位に入った。20年のランキング以降続く、停滞する日本経済の活路を探る動きが表れたものといえる。

予告
ベスト経済書・ビジネス書大賞2022【全22冊】インフレ・超円安の世相を反映した必読書は?
経済学者や経営学者、エコノミスト138人が選んだ経済、経営に関わる良書をランキング形式でお届けする『ベスト経済書・ビジネス書大賞2022』。40年ぶりの高インフレと大幅な円安に見舞われた日本経済。2022年のランキングにもそうした世相が反映され、物価や金融政策に関する書がランクインした。推薦の言葉を添えて全22冊を紹介するとともに、日本の活路の指針となる書も取り上げた。

2月中には新しい日本銀行の総裁・副総裁の人事案が国会に提示される。政府が雨宮正佳副総裁に次期総裁就任を打診したとの報道が流れた。次期総裁には行き詰まりつつある異次元緩和の修正が求められる。そのかじ取り役として、異次元緩和の遂行を支えてきた雨宮氏は適任といえるだろう。

防衛費増額の財源として国債償還の60年ルールの80年への延長が取り沙汰されている。一見、財源が生まれるように見えるが、実態は借金の先送りであり、単に債務残高を増やすに過ぎない。

#14
2024年は5年に1度の公的年金の財政検証の年。それに合わせて年金制度改革が実施される。その柱は基礎年金の給付水準確保だ。厚生年金からの財政支援、加入期間の40年から45年への延長が検討されている。これらが盛り込まれると、年金給付額はどうなるのか試算した。高所得者は給付減に要注意だ。
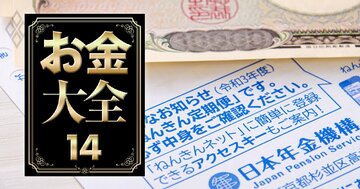
#6
米国や欧州の高インフレはいつ収束するのか。ピークの見えない日本の物価上昇はどうなるのか。インフレが収まったときに、以前のような低インフレ・低金利・低成長に戻るのか。物価分析の泰斗である渡辺努・東京大学教授と著名エコノミストである河野龍太郎・BNPパリバ証券経済調査本部長に徹底討論してもらった。

#1
元モルガン銀行(現JPモルガン・チェース)日本代表・東京支店長であり、金融マーケットをよく知る藤巻健史氏は、ハイパーインフレ、円暴落の日は「2023年中にも来る」と明言する。その引き金を引くのは、これまで異次元緩和を続け、国債発行残高の過半を保有する日本銀行だ。藤巻氏が「目の前にある」とする危機の構図とは?
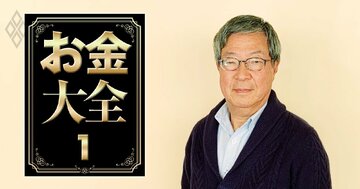
2022年12月20日、日本銀行は長期金利の許容幅拡大に踏み切った。利回り曲線のゆがみの解消、円安抑制などが狙いだ。ただ、23年にさらなる拡大に踏み切ることは容易ではない。その理由を明らかにする。

#12
米国のインフレ率急上昇と急速な利上げは、世界経済と金融市場を大きく揺るがした。2023年以降の米国のインフレ、金融政策、景気について、第一級の識者2人に対談してもらった。

#7
欧米の景気後退や中国経済の減速が確実視される2023年。日本の景気も欧米の後を追うのか?そこで著名エコノミスト11人が勢ぞろい。「成長率」「物価上昇率」「日本銀行の金融政策」など、23年の日本の景気を徹底予測する。

#4
2022年は、インフレ高進を抑制するための米国の急速な利上げによって、金融史に残る大幅な円安・ドル高が進んだ。23年の為替市場の動向について、9人の著名ストラテジストに大予想してもらった。

#2
失われた10年がいつの間にか30年に。長期停滞にあえぐ日本経済の活路はどこにあるのか。政府の各種委員も務める気鋭の3人の識者に徹底討論してもらった。

#12
外食需要が減る中で、憂き目に遭う企業はどこか。あのメディア企業にも危機が!?上場企業3935社の倒産危険度を総点検。リスクの高い509社をあぶり出した。倒産危険度ランキング総合版の第4段では、ワースト301~509を紹介する。
