竹田孝洋
マイナス金利解除後の日本銀行の「次の一手」はいつで、どこまで金利は上がるのか。追加利上げは物価動向次第なのは言うまでもないが、2024年春闘の高めの賃上げが中小企業にも波及し、物価押し上げ要因となっていけば25年末までに0.5%までの引き上げはありそうだ。さらに円安が予想外に進行した場合は、利上げの前倒しや最終的な政策金利の水準の上昇もあり得る。

マイナス金利が解除され、利上げが複数回行われたとして日本経済にその耐性はあるのか。10年にわたる異次元緩和の修正はどのように進めるべきなのか。日本銀行元副総裁である山口廣秀・日興リサーチセンター理事長へのインタビューの後編では、あるべき金利水準、金利引き上げの家計、金融機関などへの影響、異次元緩和からの出口戦略について語ってもらった。

日本銀行が3月18、19日に開く金融政策決定会合で、マイナス金利政策を解除する可能性が高まっている。今後の景気・物価動向、金利の見通し、異次元緩和からの出口戦略の進め方などについて日銀元副総裁である山口廣秀・日興リサーチセンター理事長へのインタビューを2回に分けてお届けする。前編では、もっと早くマイナス金利解除をすべきだった主張する山口氏に、2%物価目標達成の可否、金利引き上げの着地点などについて聞いた。

#9
日経平均株価と並ぶ日本株の代表的指標であるTOPIX(東証株価指数)は、いまだに最高値を更新していない。その原因を探っていくと、指数の算出方法における日経平均の“ゆがみ”が浮かび上がる。

質、量ともに世界基準のスタートアップを日本で生み出すために何が必要なのか。何を変えていくべきなのか。昨年に引き続き、入山章栄・早稲田大学大学院経営管理研究科・早稲田大学ビジネススクール教授、加藤雅俊・関西学院大学経済学部教授・同アントレプレナーシップ研究センター長、清水和彦・フォースタートアップス取締役兼アクセラレーション本部長、牧兼充・早稲田大学ビジネススクール准教授の4氏が大学教授や研究者の観点からこの問題について議論した。その内容を2回にわたりお届けする。後編では、スタートアップ人を育成するために必要な教育、大企業とスタートアップの関わり方などについて議論してもらった。

質、量ともに世界基準のスタートアップを日本で生み出すために何が必要なのか。何を変えていくべきなのか。昨年に引き続き、入山章栄・早稲田大学大学院経営管理研究科・早稲田大学ビジネススクール教授、加藤雅俊・関西学院大学経済学部教授・同アントレプレナーシップ研究センター長、清水和彦・フォースタートアップス取締役兼アクセラレーション本部長、牧兼充・早稲田大学ビジネススクール准教授の4氏が大学教授や研究者の観点からこの問題について議論した。その内容を2回にわたりお届けする。前編では、リスクを取る文化を育むための教育の欠如、大学のスタートアップへのかかわり方の薄さなどの課題について語ってもらった。

FRBのパウエル議長は、1月のFOMCで3月利下げに対して否定的な姿勢を示した。しかし、声明文からは利上げの文字を削除した。利下げの開始は5月または6月となりそうだ。

#16
日本銀行は金融政策の正常化に向けて歩みだしているように見える。ただ、超低金利に慣れ切った日本経済の金利耐性は低く、慎重に歩みを進めざるを得ない。今後の物価動向や、YCC(イールドコントロール、長短金利操作)撤廃、マイナス金利解除の条件などについて、「金融政策は異次元緩和導入前の姿に戻れない」と語る、翁邦雄・京都大学公共政策大学院名誉フェローに聞いた。

#5
消費者物価上昇率は前年比で、日本銀行が目標とする2%超えが続いている。YCC(イールドカーブコントロール、長短金利操作)やマイナス金利の行方に注目が集まる。前日本銀行副総裁である若田部昌澄・早稲田大学政治経済学術院教授に今後の物価動向、金融政策の行方について語ってもらった。

#3
2023年の経済成長率は、コロナ禍からの経済活動正常化で1%台後半という高めの成長を達成できそうだ。果たして24年も成長ペースを維持できるのか?10人の著名エコノミストに経済成長率、物価などの動向について予測してもらった。

#2
米国の利上げは現状水準で打ち止めとなり、2024年春から夏までに利下げが始まりそうだ。ECB(欧州中央銀行)も24年には利下げに転じる。一方、日本銀行はマイナス金利解除に踏み切るだろう。日本と欧米の金利差が縮小すると見込まれる中、24年の対ドルレート、対ユーロレートを8人の為替のプロに予想してもらった。

10月の米国の消費者物価上昇率や雇用統計が市場予想を下回ったことで、2024年の利下げに市場の関心が集まりつつある。経済指標動向などからその時期を予想する。

日本銀行がYCC再柔軟化に踏み切った。金利上昇と円安進行に追い込まれる中、政府やアベノミクス支持者への配慮がうかがわれる苦肉の策だ。しかし、金利のある世界への一歩であることは間違いない。

中国の李克強前首相は習近平総書記が経済政策への関与を強める中で実権を失ったが、習氏の統制強化路線への歯止めだった。その死去は中国経済低迷の始まりの象徴かもしれない。

インフレ退治に向け追加利上げの可能性と高金利継続を示唆するFRB。背景には米国景気の強さがある。大規模緩和を継続する日本銀行とは対照的だ。米利下げ時期の遅れにより円高反転も後ずれしそうだ。

#7
欧米の中央銀行はインフレへの初期対応を誤った。新型コロナウイルスの感染拡大がもたらしたインフレの“新常態”を読み切れなかった。コロナ禍前のディスインフレ時代と何が変わったのか、金融政策はどう変化するのかを分析した。

#6
市場が早期の利上げ停止、年明けからの利下げを織り込む中、米連邦準備制度理事会(FRB)は利上げ停止後も金利水準を維持する見込みだ。また、パウエルFRB議長は景気後退なきインフレ退治に自信を見せる。景気後退を回避し、また再燃させることなくインフレを抑制できるのか。5人の米国経済の専門家へのアンケートを通して読み解いてゆく。
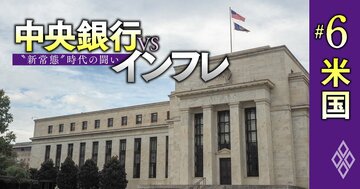
#5
インフレはピークアウトしたものの、7月の消費者物価上昇率は5.3%。ECB(欧州中央銀行)は引き締めの手綱を緩めない。製造業PMI(購買担当者景気指数)が50割れのユーロ圏。サービス業も50割れが近づき、景気後退が忍び寄る。英国もインフレはピークを付けたものの、7月の消費者物価上昇率は6.8%と水準は高い。景気後退なきインフレ抑制は可能なのか。欧州経済のスペシャリスト5人に検証してもらった。

#4
欧米のインフレ鈍化に合わせ、市場は利下げを織り込み始めた。一方、国内のインフレのピークはいまだ見えず、金融政策正常化への道筋も不確かだ。こうした状況下での株価の先行きを7人の敏腕ストラテジストに聞いた。

消費者物価上昇率が16カ月連続で目標の2%を上回る中、現在の金融政策は適切なのか。金融政策の対象は賃金ではなく物価であると吉川洋・東京大学名誉教授は語る。就任以降の植田和男日本銀行総裁のかじ取りの評価を黒田東彦前総裁の異次元緩和の功罪とともに吉川氏に聞いた。
