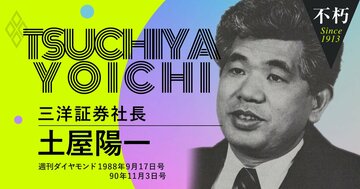深澤 献
工作機械用NC(数値制御)装置や産業用ロボットなどで世界一のシェアを持つファナックは、1972年に富士通の計算制御部門が分離独立した会社だ。富士通時代から機械技術者としてNC技術の開発に携わり、独立時には専務取締役だった稲葉清右衛門(1925年3月5日~2020年10月2日)は、副社長を経て75年に社長に就任した。サラリーマン技術者の出身ながら、ファナックを世界的企業に育て上げた実質的な創業者といえる。
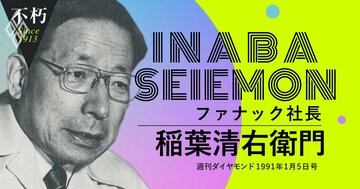
1979年に日米逆転の可能性を描き、世界的なベストセラーとなった『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(阪急コミュニケーションズ刊)。その著者のエズラ・ヴォーゲル(1930年7月11日~2020年12月20日)が、「週刊ダイヤモンド」2006年11月11日号で、改めて“日本論”を語っている。『ジャパン・アズ・ナンバーワン』執筆当時は、土光敏夫(元経済団体連合会会長)や松下幸之助(パナソニック創業者)、井深大(ソニー創業者)といった経営者が最前線で活躍していて、「国全体に今とは異なる活気と自信が満ち溢れていました」とヴォーゲルは振り返る。しかし、バブル崩壊で自信を失っていた当時の日本に対し、「そんなに悲観ばかりするものではない」とも言う。

「週刊ダイヤモンド」2004年9月11日号で「知られざる巨大財閥ロッテの全貌」という特集が組まれた。ロッテグループの創業者、重光武雄(1921年11月3日[戸籍上は1922年10月4日]~2020年1月19日、韓国名:辛格浩=シン・キョクホ)のインタビューが掲載されている。

バブル崩壊を機に、住専7社の債権10兆7000億円のうち約6兆8000億円が、回収不能と目される不良債権となった。それらの不良債権は住宅金融債権管理機構(現整理回収機構)に移管され、15年をかけて回収することになった。そして住管機構の社長に就いたのが中坊公平(1929年8月2日~2013年5月3日)である。
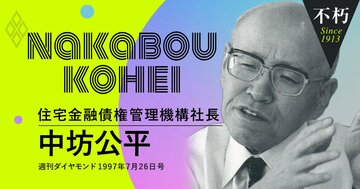
今回は「週刊ダイヤモンド」1987年4月18日号に掲載された、野村證券会長の田淵節也(1923年10月25日~2008年6月26日)のインタビューだ。「ザ・経営者」と題された連載シリーズで、聞き手は精神科医にしてノンフィクション作家の野田正彰である。
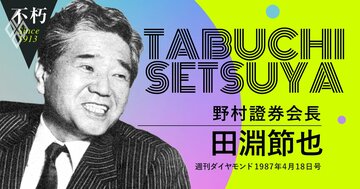
今回は、「週刊ダイヤモンド」1977年1月8日号に掲載された、松下電器産業(現パナソニック ホールディングス)の創業者、松下幸之助(1894年11月27日~1989年4月27日)の新春特別インタビューだ。
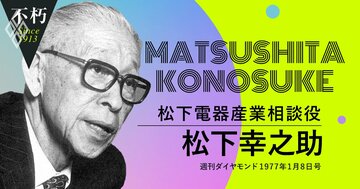
1946年5月、戦後の焼け野原から生まれた東京通信工業(現ソニーグループ)を、グローバル企業へと育て上げた盛田昭夫(1921年1月26日~99年10月3日)。その国際感覚は、53年に3カ月にわたって米国やヨーロッパを歴訪した経験が大きなきっかけとなっている。この初めての長期海外出張で米ウエスタン・エレクトリックやオランダのフィリップスを歴訪し、盛田はトランジスタラジオで米国市場に打って出ることを決意した。
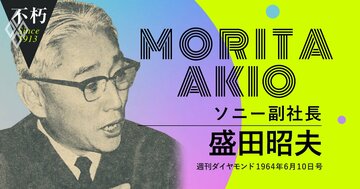
1912年にシャープを創業した早川徳次の言葉に「人にまねされる商品を作れ」というものがある。他社がまねをするということは、消費者のニーズが高いことの証左であり、それを他社に先駆けて開発し、量産することが勝利の法則ということだろう。実際、シャープは数々の世界初、日本初の製品を生み出し、戦後の日本を「家電王国」に押し上げる重要プレーヤーとなった。

「経済学の巨人」と称されるジョン・K・ガルブレイスは、米ウォール街の過熱ぶりについて警告を発し続けていた。マネーゲームの行き過ぎ、M&Aブーム ジャンクボンド(くず債権)外国資金の大量流入など、ぬぐい切れない不安が米国経済に根差していて、この浮かれ騒ぎが収まったとき、深刻な不況に見舞われると予測している。また、米国と同様に、金融危機の可能性を抱えているのが日本だとガルブレイスは指摘する。
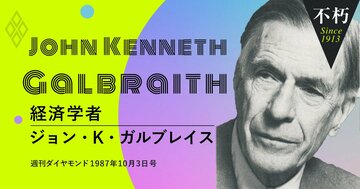
保守系の評論家として知られる山本七平(1921年12月18日~91年12月10日)は、56年に聖書学を専門とする山本書店を創業。70年に『日本人とユダヤ人』(イザヤ・ベンダサン著・山本訳)という、ユダヤ人との対比による独自の日本人論を出版すると、これがベストセラーとなった。イザヤ・ベンダサンは山本のペンネームであるとされており、その後は『私の中の日本軍』『論語の読み方』『「空気」の研究』など数多くの著書を残した。
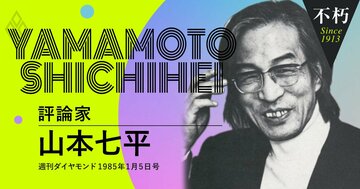
1971年、小倉昌男(1924年12月13日~2005年6月30日)は、父である小倉康臣が創業したヤマト運輸の2代目社長に就任した。ところが、間もなく訪れたオイルショックとガソリン価格の高騰で業績が低迷。そこで76年、小倉が乗り出した新規事業が個人向け小口貨物配送サービス「宅急便」である。当時、個人間の輸送は、郵便局の小包(現在のゆうパック)か国鉄(現JRグループ)による鉄道小荷物の寡占だった。
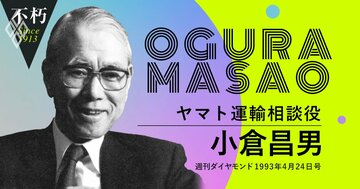
1918年3月、大阪で創業した松下電気器具製作所(現パナソニック)の創業メンバーは松下幸之助、幸之助の妻・むめの、その弟・井植歳男の3人だった。その後、むめのは歳男の下の弟2人や妹の夫らも呼び寄せ、家族を挙げて松下家とその経営を支えた。だが第2次世界大戦後、幸之助が連合国軍総司令部(GHQ)から公職追放されたことで、歳男らは47年に独立創業する。これが三洋電機の始まりだ。
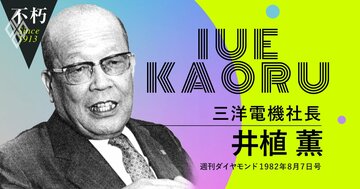
「週刊ダイヤモンド」1986年5月24日号に掲載された、サントリー(現サントリーホールディングス)社長の佐治敬三(1919年11月1日~1999年11月3日)と東京急行電鉄(現東急)社長の五島昇(1916年8月21日~1989年3月20日)による「今こそ世界のリーダーシップを握る好機」と題した対談だ。五島は日本商工会議所会頭、佐治は大阪商工会議所会頭という肩書で登場している。

今回は、「ダイヤモンド」1964年1月6日号に掲載された八幡製鐵(現日本製鉄)社長の稲山嘉寛(1904年1月2日~87年10月9日)のインタビューだ。稲山は「競争より協調路線」のスタンスを貫き、「ミスター・カルテル」の異名を取ったほどの人物である。
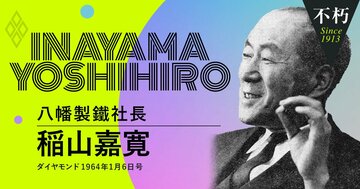
今回紹介するのは、「ダイヤモンド」1966年5月23日号に掲載された住友金属工業(現日本製鉄)社長の日向方齊(1906年2月24日~93年2月16日)と、ソニー(現ソニーグループ)社長の井深大(1908年4月11日~97年12月19日)の対談である。
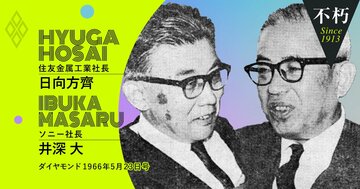
今回紹介するのは、「週刊ダイヤモンド」1981年9月12日号に掲載された韓国サムスングループ会長、李秉喆(イ・ビョンチョル:1910年2月12日~1987年11月19日)のインタビューだ。李は日本統治時代に早稲田大学政治経済学部で学び、38年に大邱(テグ)で三星商会を設立した。これが韓国最大の財閥の始まりである。
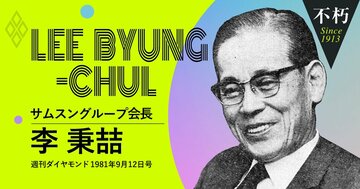
キヤノンの前身、精機光学研究所は1933年11月創業。ドイツのライカに「追い付け追い越せ」で国産カメラの開発にいそしむ。47年にキヤノンカメラに社名変更し、54年にはライカに劣らぬ名機と評価を受ける「IV Sb改」を世に出した。賀来龍三郎が入社したのは、まさにその年である。

荒畑寒村(1887年8月14日~1981年3月6日)は、日本の社会主義運動の先駆者である。1903年、横須賀海軍造船廠で職工見習だったときに、日露戦争に非戦論を唱えた幸徳秋水、堺利彦らに感化される。幸徳、堺が非戦の主張を貫くために発刊した社会主義新聞「平民新聞」に参加し、社会主義運動に身を投じた。
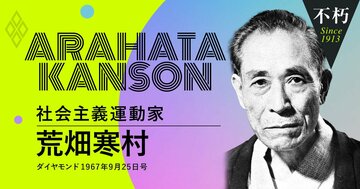
今回は「週刊ダイヤモンド」1984年12月29日号に掲載された、作家で経済企画庁長官などを務めた堺屋太一(1935年7月13日~2019年2月8日)の談話記事である。

今から35年前、バブル景気真っただ中の1988年5月、東京都江東区塩浜に三洋証券のトレーディングセンターが建設された。東京証券取引所の立会場の約2倍、サッカー場がすっぽり入る広さのトレーディングルームは当時、東洋一と称された。壁には巨大モニター、フロアには最新鋭のコンピュータ端末が3000台も並び、世界中の市場動向が常に映し出されていた。24時間取引に対応できるよう、仮眠室も完備していたという。