深澤 献
山一証券の破綻、大蔵省ノーパンしゃぶしゃぶ事件、そごう倒産、ビットバレーとネット人脈【ダイヤモンド111周年~平成前期 3】
1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正~令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第17回は平成前期、1997~2000年までの4年間だ。

安藤太郎(1910年1月3日~2010年5月9日)は、住友銀行(現三井住友フィナンシャルグループ)の副頭取から1974年に住友不動産社長に転身した。住友銀行時代は、頭取を19年務めて「住銀の法皇」と称された堀田庄三に重用されたが、堀田の引退を受け、次期頭取レースに敗れた結果だったという。しかし、三井不動産、三菱地所の財閥系不動産デベロッパーの中で最後発だった住友不動産を大きく飛躍させ、「中興の祖」とまで呼ばれる存在となった。
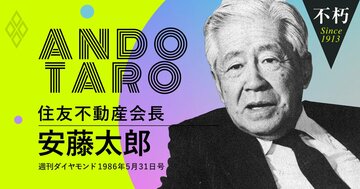
阪神・淡路大震災の衝撃、先送りされた住専問題、価格破壊とデフレの始まり【ダイヤモンド111周年~平成前期 2】
1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正~令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第16回は平成前期、1993~96年までの4年間だ。
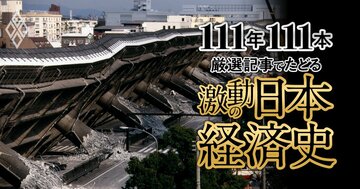
#7
米オープンAIの新AIモデル「OpenAI o1」は、論理的思考力に長け、博士号を持つ人間をしのぐ実力を有する。AI活用に関して最先端で情報発信やコンサルティングを行うTHE GUILD代表の深津貴之氏にo1について聞いた。
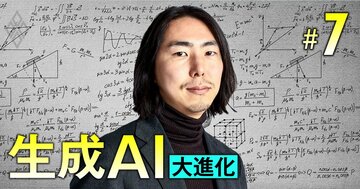
バブルの絶頂と崩壊で平成が幕開け、株価下落で証券会社に不正横行、先見えぬ“新型不況”に突入【ダイヤモンド111周年~平成前期 1】
1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正~令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第15回は平成前期、1989~92年までの4年間だ。
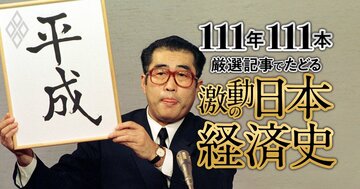
阪急電鉄をはじめとする阪急東宝グループ(現阪急阪神東宝グループ)の創業者である小林一三(1873年1月3日~1957年1月25日)。関西財界の雄にして、戦時中には政界にも入り、商工大臣も務めた。終戦直後、幣原喜重郎内閣は戦災復興院を設置し、小林を初代総裁および戦災復興担当の国務大臣に任命したが、就任からわずか4カ月後にGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)によって公職追放となった。
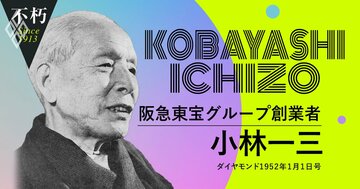
バブルへの入り口「プラザ合意」、男女雇用機会均等法、究極のカネ余りと日本企業の“米国買い”【ダイヤモンド111周年~昭和後期 4】
1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正~令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第14回は昭和後期、1985~88年までの4年間だ。

「土光臨調」の行政改革と民営化への道筋、トヨタの“工販合併”、日米スパコン摩擦【ダイヤモンド111周年~昭和後期 3】
1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正~令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第13回は昭和後期、1981~84年までの4年間だ。

ロッキード事件の闇、松下電器のトップ交代、深刻化する“サラ金”問題、火花散る日米経済戦争【ダイヤモンド111周年~昭和後期 2】
1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正~令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第12回は昭和後期、1976~80年までの5年間だ。

1ドル360円の終わり、日本列島改造論、石油ショック、三菱も狙っていたディズニーランド誘致【ダイヤモンド111周年~昭和後期 1】
1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正~令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第11回は昭和後期、1971~75年までの5年間だ。
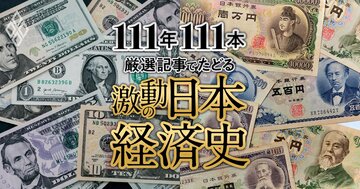
セブン&アイ・ホールディングスの名誉会長、伊藤雅俊(1924年4月30日~2023年3月10日)は終戦直後の1945年、21歳のときに、母、兄と3人で東京・千住に軒下洋品店「羊華堂」を開いた。56年に急逝した兄の後を継いで社長に就任すると、欧米で生まれたチェーンストア業態に学んだヨーカ堂の店舗網を広げて成功する。同じく米国からレストランチェーンのデニーズ、コンビニエンスストアのセブン-イレブンも日本に導入、展開し、小売業として利益1位という地位を築いた。

サントリーと宝酒造が“2弱”のビール戦争、新日本製鉄誕生、セブン参入以前のコンビニ事情【ダイヤモンド111周年~高度成長期 3】
1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正~令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第10回は高度成長期、1963~66年までの4年間だ。

東京五輪の前後で景気が激変、「所得倍増計画」の功罪、ケネディ米大統領暗殺の影響は?【ダイヤモンド111周年~高度成長期 2】
1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正~令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第9回は高度成長期、1961~65年までの5年間だ。
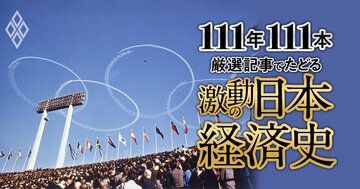
ロイヤルホールディングスの創業者である江頭匡一(1923年3月25日~2005年4月13日)は、自身について「食べ物屋」という表現を好んで用いた。戦後、22歳で福岡の米軍基地でコックの見習となったのが、食べ物屋としてのスタートだった。その後、米軍基地の御用商人として基地内でパンやケーキを販売したり、福岡空港の国内線運行開始に合わせて機内食と空港内食堂への納入を開始した。

#10
専門的なケアや介護・医療サポートを提供してくれる老人ホーム。しかし一口に老人ホームと言ってもさまざまな種類と特徴がある。主な12タイプについて特徴と費用を解説する。

家電三種の神器、国民車構想、為替・貿易自由化の波…「もはや戦後ではない」経済成長の始まり【ダイヤモンド111周年~高度成長期 1】
1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正~令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第8回は高度成長期、1956~60年までの5年間だ。

#9
どんなライフスタイルを理想とするかによって老後を見据えた住み替えの選択肢は多様だが、人生の後半戦だからこそ失敗は許されない。明確なビジョンと共に余裕のある計画を立てておこう。

朝鮮戦争で特需到来、日本航空の育成を誌面で主張、ホンダ、ソニー…“戦後派”企業の活躍【ダイヤモンド111周年〜戦後復興期 2】
1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正~令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第7回は戦後復興期、1950~55年までの6年間だ。
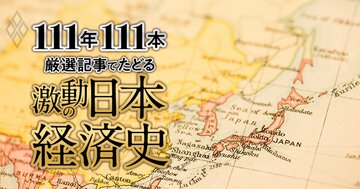
「週刊ダイヤモンド」1996年11月16日号に、経営学者のP・F・ドラッカー(1909年11月19日~2005年11月11日)のインタビューが掲載されている。ドラッカーは著作の中で、独ヒトラー政権の崩壊、日本の劇的な経済成長、バブル経済の到来、旧ソビエト連邦の崩壊など、さまざまな“予言”を行い、しばしば「未来学者」と呼ばれた。しかし、本人は「未来はすでに起こっている」のであって、すでに起こった未来を「観察」して知らせたに過ぎないと語り、自身では「社会生態学者」と称していた。
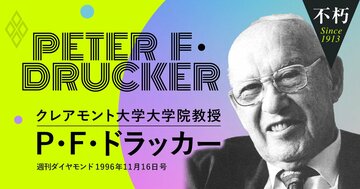
終戦で誓った平和と日本再生、渋沢蔵相の手腕を辛辣批判、超インフレを収束させた“劇薬”ドッジ・ライン【ダイヤモンド111周年〜戦後復興期 1】
1913年に(大正2)に創刊した「ダイヤモンド」は、2024年に111周年を迎えた。そこで、大正~令和の日本経済を映し出す1年1本の厳選記事と、その解説で激動の日本経済史をたどる「111年111本」企画をお届けする。第6回は戦後復興期、1945~49年までの5年間だ。
