ダイヤモンド・セレクト「オリイジン」
障がい者雇用のいま(3) 「コロナ禍」がもたらす影響
厚生労働省(2020年8月4日発表・ハローワーク業務統計)によれば、新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年2月から6月までに解雇された障がい者の数は1104人(去年の対前年同時期比=約116%)――「一般労働者と比較すると、障がい者の就職件数や就職率の減少幅は、小規模に収まっている」との同省の見解だが、実際、今回のコロナ禍における、企業・団体の障がい者雇用はどのような状況だろう? “障がい者が制約を機会に変えてイノベーションを創出するための支援を行う”一般社団法人 企業アクセシビリティ・コンソーシアム(ACE)の栗原進事務局長に話を聞いた。
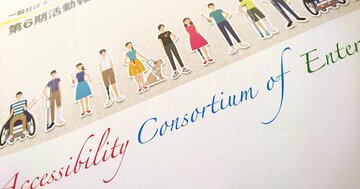
いま、企業の人事部が知っておきたいLGBTのこと(1) 性的指向について
最近では、米国で使われている「LGBTQ」という言葉を使うメディアもあるが、性的マイノリティの総称のひとつとして使われているのが「LGBT」だ。2010年代以降、組織の成長を促す「ダイバーシティ&インクルージョン」を掲げる企業や団体が増え、それを実現する多様な人材としてLGBTも挙げられている。そこで、今回は、企業の人事担当者やダイバーシティ推進担当者が知っておくべき、「LGBT」に関する基礎知識をまとめる。
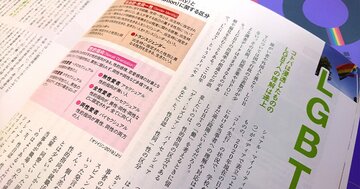
障がい者雇用のいま(2)「医療型就労支援」が導く光明
前稿(「障がい者雇用のいま(1) 数字を伸ばす『就労移行支援』とは何か?」)では、就労系の障害福祉サービスである“就労移行支援事業”についてまとめた。全国に3400以上ある事業所が就労を希望する障がい者と向き合っているかたちだが、内在する問題点や課題も多い。今回は、問題解決のひとつとなる“医療型就労支援モデル”について、その第一人者である清澤康伸氏(一般社団法人 精神・発達障害者就労支援専門職育成協会代表 医療法人社団欣助会 吉祥寺病院勤務)に話を聞いた。
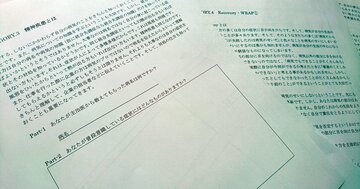
障がい者雇用のいま(1) 数字を伸ばす「就労移行支援」とは何か?
厚生労働省によれば、民間企業で働く障がい者は56万人を超え、過去最多を毎年更新している(2019年発表/16年連続)。1960年の「身体障害者雇用促進法」制定から今年2020年で60年。企業による障がい者の雇用は「努力目標」から「法定義務」となり、1998年には知的障がい者が、2018年には精神障がい者が含まれるようになるなど、法律の改正も後押ししている。一方で、障がい者の職場定着率を上げるために、“就労系障害福祉サービス”を行う事業者(就労支援機関)と企業の連携が、いま強く望まれている。
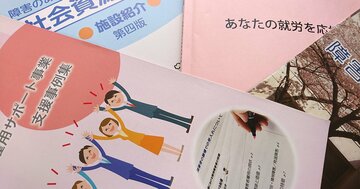
はるな愛さん、いじめに耐え抜いていま世の中に望むこと
個性あふれるキャラクターで多くの人に注目され、マルチな活躍を続けるタレント・はるな愛さん。2009年には、国際大会の「ミス・インターナショナルクイーン」で、日本人初の優勝を果たし、現在は飲食店経営の事業家としての顔も持っている。いつも明るく元気なイメージだが、子どもの頃は壮絶ないじめに遭い、自殺することを何度も考えたという。デビューからおよそ25年。ダイバーシティ社会の中で、いま、彼女が思うことは……。

パラリンピックを創った日本人医師・中村裕と「太陽の家」
新型コロナウイルスの感染症拡大がなければ、この夏、世界は「東京2020オリンピック・パラリンピック」の開催で盛り上がっていたはずだ。そして、パラリンピックの開催でパラスポーツが注目され、ひとりの偉人が改めて注目されていたにちがいない。中村裕医師(医学博士)――昭和40年に、「No Charity, but a Chance!(保護より機会を)」を理念に、〈太陽の家〉を創設した人物だ。いま、社会で障がい者雇用が進むなか、中村医師の足跡を振り返ってみよう。

2045年の日本社会の変化を「ダイバーシティ」の観点から考える
働き方改革とともに、ダイバーシティ&インクルージョン(多様性の受容)が進む日本社会の動向を、前稿「LGBT・障がい者・外国人・要介護者……多様な人が多様に暮らす社会の現在形」でまとめたが、それでは、いまから四半世紀後=2045年の社会はどうなっているのだろう? 今回は、テクノロジーの進化がもたらす変化ではなく、あらゆる人が暮らし働く“ダイバーシティ社会”の観点から考えてみよう。
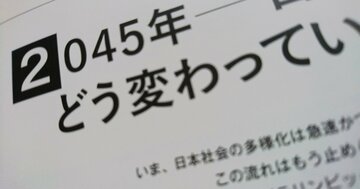
ジャニー喜多川さんの逝去から1年――V6から学ぶ、組織を長続きさせる条件
2019年7月9日、“キング・オブ・エンターテインメント”ジャニー喜多川さん(元ジャニーズ事務所/代表取締役社長・プロデューサー)が逝去した。あれから1年――新型コロナウイルス感染症の拡大で、人々の生活は急激な変化を余儀なくされ、エンターテインメント業界もまだ大きな打撃を受けている。そうしたなか、ジャニーズ事務所で、この2020年に25周年を迎えたグループがある。V6だ。彼ら6人の姿から、時代のキーワードである“ダイバーシティ”の本質を考えてみよう。
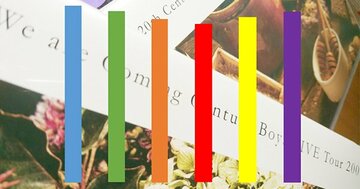
LGBT・障がい者・外国人・要介護者……多様な人が多様に暮らす社会の現在形
「働き方改革」とともに、ダイバーシティ&インクルージョン(多様性の受容)が進む日本の社会――外国人労働者のほか、高齢者、障がい者、LGBTなど、「働く人」の多様化が顕著だ。また、要介護者・がん患者などの存在も目立ってきている。それぞれの数字をもとに、日本の「ダイバーシティ&インクルージョン」の現在地を見てみよう。
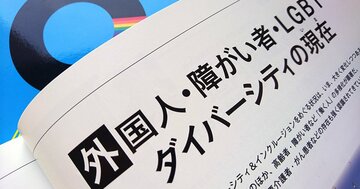
「ダイバーシティ&インクルージョン」はどう生まれたのか?その歴史を振り返る
「多様性(ダイバーシティ)」という言葉が、ツイッターなどのSNSでもすっかり目立つようになり、「ダイバーシティ」は「インクルージョン」という言葉とセットで、ビジネス用語としていまや一般的になりつつある。今後、新型コロナウイルス感染症の拡大が終息すれば、なおさらキーワードになっていくにちがいない。では、その“ダイバーシティ&インクルージョン”は、どう生まれ、日本においてはどう展開してきたのか――いま、その歴史を振り返ってみよう。
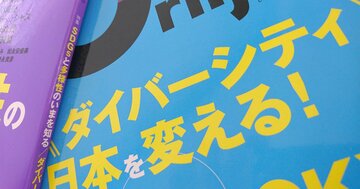
さまざまな障がい者の雇用で、それぞれの企業が得られる強み
新型コロナウイルス感染拡大の影響は、わたしたちの働き方に大きな影響を与えた。そうしたなか、今後ますます進んでいく、さまざまな障がい者と健常者の協働は、ダイバーシティ&インクルージョンの視点からも欠くことのできないビジネスシーンとなる。企業における障がい者雇用はどのような価値を生み、いかなる深化を遂げていくのだろうか?

日本の「ダイバーシティ」社会に、外国人労働者は何をもたらすか?
新型コロナウイルス感染拡大は在留外国人の「労働」にも強く影響している。少子高齢化が進む日本では労働力不足が深刻で、アフターコロナの社会のおいても、日本で働く外国人は欠くことのできない存在となる。「働き方改革」と「ダイバーシティ&インクルージョン」のキーワードのもと、ダイバーシティ社会をかたちづくる外国人の働き方に、私たち日本人はどう対応していくべきだろうか。
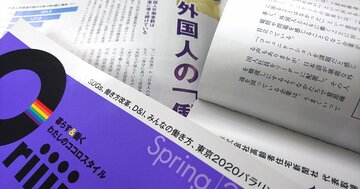
「ダイバーシティ」が導く、誰もが働きやすく、誰もが活躍できる社会
「働き方改革」と「ダイバーシティ&インクルージョン」。新型コロナウイルス感染拡大のずっと前から、メディアでも、ビジネスシーンでも頻繁に使われるようになった言葉だ。実は、このふたつの言葉は密接に関係していて、「働き方改革」=生産性の向上という目標のもと、多様な人材を受け入れることが多くの企業でスタンダードになっている。障がい者・外国人・LGBT――さまざまな人たちが、いま、職場に求められる実状とは?
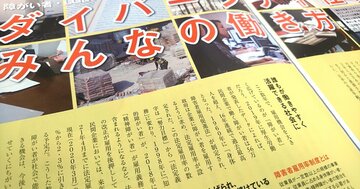
「外国人労働者」との付き合い方が、これからの企業の生命線になる理由
新型コロナウイルス感染の世界的拡大は、日本で学ぶ留学生にも、働く外国人にも影響し、アフターコロナの社会では、働き手の不足が心配される。日本の労働市場においては、外国人の存在がもはや欠かせないからだ。2020年代――外国人と協働し、実りあるダイバーシティ社会を日本人が構築するためにはどうあるべきか?実例とともに考えてみよう。

「ダイバーシティ」は、なぜSDGs実現のキーワードになるのか
前稿で、国際連合(国連)の提唱するSDGs(持続可能な開発目標)を「人類共通の課題カタログ」と称した。ダイバーシティ&インクルージョンマガジン「オリイジン」では、そのSDGsを統合するひとつの軸として「多様性(ダイバーシティ)」を提案している。多様性の視点を持つことで17のゴールそれぞれの実現が近づき、また、17のゴールがつながっていく効果も期待できるのだ。
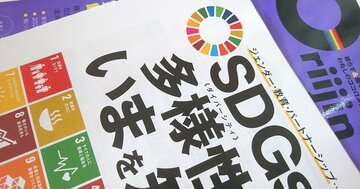
「SDGs」の誕生理由とは?今後どんな成果を実現していくのか、改めて振り返ってみる
国際連合(国連)が提唱し、2030年へ向けた世界の羅針盤として注目されるSDGs(持続可能な開発目標)。日本においても、国や自治体、民間企業が、それぞれさまざまな取り組みを進めている。これからの10年で、どのような成果を実現していくのか――その17の目標と169のターゲットを理解するだけではなく、一歩踏み込んだアプローチや角度を変えた視点が求められているいま、SDGs誕生の理由を再考してみよう。

先生・保護者が知っておきたい「LGBTと学校」のこと
毎年ゴールデン・ウィークのこの時期は、LGBT(性的マイノリティの総称のひとつ)への差別や偏見をなくすためのイベント「東京レインボープライド」が開催され、「プライドウィーク」とも呼ばれている。「LGBT」という言葉は、いまや日本の社会にも知れ渡ったものの、トランスジェンダーと性同一性障がいが混同されて論議されるなど、正しい理解がなされているとは言い難い。そうしたなかで、LGBTの子どもたちへの理解をまずいちばんに進めていく必要がある。いま改めて、学校関係者や保護者が知っておくべきこと、そして、小・中・高校におけるLGBT対応の方向性を考えてみよう。

LGBT(セクシュアル・マイノリティ)の当事者は職場でカミングアウトをするべきか?
映画やドラマの世界でもゲイやトランスジェンダーのキャラクターが描かれ、「LGBT」というコトバ(セクシュアル・マイノリティの総称のひとつ)が知れわたっている。そのため、いまや当事者の「カミングアウト」は当たり前とも思われるが、必ずしもそうではない。「LGBT」の可視化が進むなかで、職場における「カミングアウト」の是非を考えてみる。

外出自粛のいまだから考えたい、「パブリックトイレ」への向き合い方
あらゆる人たちが暮らすダイバーシティ社会において、みんなが必要で、みんなが気にしなければいけないもの――それがトイレです。自宅のトイレは個人個人で考えればよいですが、公共トイレ(パブリックトイレ)はそうはいきません。「みんなが使うもの」という意識、「次の時代&世代に残すもの」という心がけが必要です。多くの公共施設が閉まっているいまだからこそ、公共トイレ(パブリックトイレ)について考えてみましょう。

LGBT当事者が職場で感じる“ハート”と“ハード”の違和感
LGBTというコトバを、誰もが知る時代になった。しかし、「(LGBTが)自分の周りにはいない」という非当事者の声も相変わらず多いようだ。いま、LGBTの当事者たちが職場で抱えている問題と、それに対し、企業がどう臨むべきかを考えてみる。

