橋本卓典
石川、富山、福井の北陸3県を地盤とする地方銀行の北國銀行が、「虎の子」であるCRM(顧客情報管理)システムの一部を石川県信用保証協会と共有することにより、保証付き融資における手続きの「完全電子化」を進めている。実現すれば手続きの合理化やスピードアップが図れるのはもちろんだが、実は完全電子化には、それ以上のメリットと意義が秘められている。

銀行間の送金手数料が40年ぶりに引き下げられることに伴い、今年10月から、銀行各行が振込手数料を一斉に引き下げる。銀行業界にはびこる「横並び文化」を象徴するような対応だ。しかし、石川、富山、福井の北陸3県を地盤とする地方銀行、北國銀行だけは様子が違う。インターネットバンキングの振込手数料で「攻めの改定」を行い、地域のデジタル化に弾みをつける考えだ。
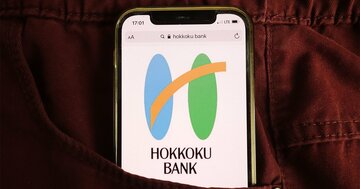
石川、富山、福井の北陸3県を地盤とする地方銀行、北國銀行が、システムのクラウド化を契機に「地域金融エコシステム構想」を実現させようと動き始めた。地銀業界で再編の必要性が叫ばれて久しいが、再編効果が見いだせず二の足を踏む地銀は多い。そんな中、このエコシステム構想が新たな生き残り策の選択肢となり得る理由とは何か。

5月、石川県の第一地方銀行である北國銀行が、日本の銀行(インターネット専業を除く)で初めて、勘定系システムをクラウドに移行した。クラウド化のメリットといえば、コスト削減がいの一番に上がる。だが、クラウド化で狙えるのはそれだけではない。北國銀行は、システムのクラウド化によって、ビジネスモデルをも変革させようとしている。

政府・与党がコロナ禍で浮上する過剰債務問題の解決に向け、中小企業版の私的整理ガイドラインの検討を進めている。企業の事業再生や廃業を促し、地域の持続可能性を高めるために、金融機関が検討するべきこととは何か。
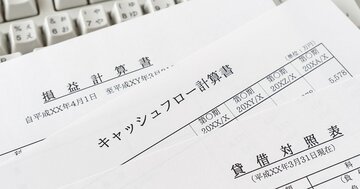
新型コロナウイルスをめぐっては、高齢者へのワクチン接種が国内でも始まったが、「第4波」への警戒、そして変異株の感染拡大もあり、経済への悪影響は長期化が避けられない。国のコロナ対策により、中小企業の倒産件数が低下しているため、地方銀行への打撃は今のところ限定的だ。

古今東西、国家や組織の運営で共通するジレンマは、有事に直面したとき、何を優先し、どのように対処するのかによって、結果が大きく違ってしまうという問題である。

前回のコラム掲載から約1週間後の1月27日、山口フィナンシャルグループ(YMFG)は福利厚生代行事業会社「イネサス」を設立した。地元企業への福利厚生サービスの提供や、サービス提供側の機会を創出することで、地元企業の雇用の安定と地域内経済の循環、活性化を同時に実現しようという試みだ。

2019年12月に金融検査マニュアルが廃止されたことは、銀行の歴史において、一つの時代が終わったことを象徴している。言うなれば、20年間続いた不良債権処理時代の終焉(しゅうえん)だ。

100年前、人々は走り去る自動車を目にしていながら「馬なしの馬車」としか認識していなかった。今では担保を取って融資(証書貸し)をするのが当たり前の民間銀行も、当時は企業が毎月必要としている仕入れや給与支払いの運転資金を短期継続融資で貸し出すことを主力業務としていた。

100年前、人々は自動車のことを「馬なしの馬車」と呼んだ。見慣れた馬車のアップデート版にすぎないと認識したからだ。しかし、現実は違った。それまでの産業構造を次元の違うものに変えてしまうモータリゼーション革命が起きていたのだ。
