矢部謙介
2025年5月、パナソニックホールディングスはグループ全体で1万人規模の大型リストラを行うことを公表した。パナと日立製作所、大手電機メーカー2社の会計指標の推移を見ながら、パナが「黒字リストラ」を断行する背景や、両社における株価の上昇度合いに大差がついた要因を探る。

日立製作所とパナソニックホールディングス、どちらも日本を代表する大手電機メーカーだが、ここ10年の株価の推移を見ると明暗がくっきりと分かれている。日立が順調に株価を伸ばしてきた一方で、パナの株価が伸び悩む理由とは何か。会計指標に注目して読み解いていこう。まずは両社の「成長性指標」の推移を分析していく。

倒産や閉店が相次ぐなど「オワコン」とも囁かれた百貨店業界において、好調ぶりが際立つ三越伊勢丹ホールディングス。2025年3月期は営業利益で過去最高益を更新した。同社の営業利益や売上高営業利益率を押し上げたものとは何だったのか。前編に引き続き、決算書を基に解説していく。

百貨店事業などを手掛ける三越伊勢丹ホールディングスが好調だ。地方を中心に倒産や閉店のニュースが相次ぐなど、厳しい印象も強い百貨店業界で好業績を叩き出せる理由とは何か。決算書から読み解いてみよう。

近年、業績不振に陥っていた花王の業績に回復の兆しが見えている。不調の要因は何だったのか。前編では、同社が20年以上前から導入している経営指標、EVAについて解説した。後編では、花王の「EVA経営」に生じた課題を明らかにするとともに、復活に向けた戦略について見ていこう。

このところ業績不振に陥っていた花王の業績に回復の兆しが見えている。2024年12月期は6期ぶりに最終増益となった。花王の業績はなぜ低迷してしまっていたのか。また、どのように復活への道を見いだしたのか。同社が重視する会計指標を踏まえて解説しよう。

#7
企業の成長と衰退を分ける決定的な要因は何か?売上や利益の数字だけでは、企業の本当の強さやリスクは見えてこない。決算書には、経営戦略や隠れたリスクがすべて刻まれている。本シリーズでは、決算書を「戦略の道具」として読み解く方法を、全7回の動画で徹底解説。単なる数字の羅列としてではなく、ビジネスモデルと結びつけて分析することで、企業の実態や未来の勝ち筋が見えてくる。「無機質な数字」が「刺激的なドラマ」に変わる!ビジネス・投資・就活に役立つ、一生使えるスキルを解説する。
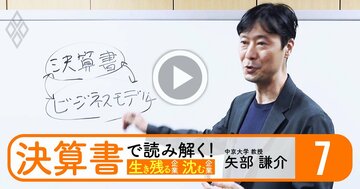
#6
企業の成長と衰退を分ける決定的な要因は何か?売上や利益の数字だけでは、企業の本当の強さやリスクは見えてこない。決算書には、経営戦略や隠れたリスクがすべて刻まれている。本シリーズでは、決算書を「戦略の道具」として読み解く方法を、全7回の動画で徹底解説。単なる数字の羅列としてではなく、ビジネスモデルと結びつけて分析することで、企業の実態や未来の勝ち筋が見えてくる。「無機質な数字」が「刺激的なドラマ」に変わる!ビジネス・投資・就活に役立つ、一生使えるスキルを解説する。
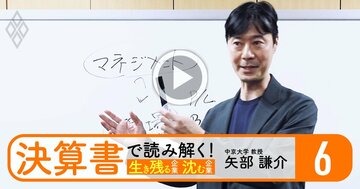
#5
企業の成長と衰退を分ける決定的な要因は何か?売上や利益の数字だけでは、企業の本当の強さやリスクは見えてこない。決算書には、経営戦略や隠れたリスクがすべて刻まれている。 本シリーズでは、決算書を「戦略の道具」として読み解く方法を、全7回の動画で徹底解説。 単なる数字の羅列としてではなく、ビジネスモデルと結びつけて分析することで、企業の実態や未来の勝ち筋が見えてくる。「無機質な数字」が「刺激的なドラマ」に変わる!ビジネス・投資・就活に役立つ、一生使えるスキルを解説する。

#4
企業の成長と衰退を分ける決定的な要因は何か?売上や利益の数字だけでは、企業の本当の強さやリスクは見えてこない。決算書には、経営戦略や隠れたリスクがすべて刻まれている。 本シリーズでは、決算書を「戦略の道具」として読み解く方法を、全7回の動画で徹底解説。 単なる数字の羅列としてではなく、ビジネスモデルと結びつけて分析することで、企業の実態や未来の勝ち筋が見えてくる。「無機質な数字」が「刺激的なドラマ」に変わる!ビジネス・投資・就活に役立つ、一生使えるスキルを解説する。
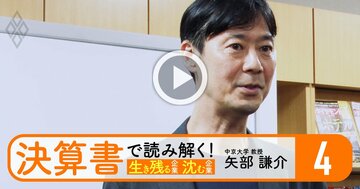
#3
企業の成長と衰退を分ける決定的な要因は何か?売上や利益の数字だけでは、企業の本当の強さやリスクは見えてこない。決算書には、経営戦略や隠れたリスクがすべて刻まれている。 本シリーズでは、決算書を「戦略の道具」として読み解く方法を、全7回の動画で徹底解説。 単なる数字の羅列としてではなく、ビジネスモデルと結びつけて分析することで、企業の実態や未来の勝ち筋が見えてくる。「無機質な数字」が「刺激的なドラマ」に変わる!ビジネス・投資・就活に役立つ、一生使えるスキルを解説する。
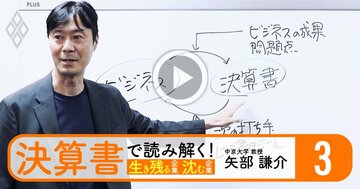
味の素がネスレ、ユニリーバに追いつくために克服すべき「深刻な課題」とは【2つの指標で分析】
今回は筆者の新刊『会計指標の比較図鑑』にも収録している、ネスレと味の素の決算書の解説をお届けする。前編に続く後編では、回転期間とCCCという2つの指標を比較することで、味の素が抱える課題をひもといていこう。

味の素は減益、ネスレは増益…食品メーカー2社で大差がついた「経営を左右する指標」
今回は筆者の新刊『会計指標の比較図鑑』にも収録している、ネスレと味の素の決算書の解説をお届けする。グローバルでビジネスを展開する食品メーカーの2社だが、売上高・営業利益ともに、ネスレが味の素に10倍以上の差をつけている。それぞれの決算書にはどんな特徴があるのか。比較して読み解いていこう。

#2
企業の成長と衰退を分ける決定的な要因は何か?売上や利益の数字だけでは、企業の本当の強さやリスクは見えてこない。決算書には、経営戦略や隠れたリスクがすべて刻まれている。本シリーズでは、決算書を「戦略の道具」として読み解く方法を、全7回の動画で徹底解説。単なる数字の羅列としてではなく、ビジネスモデルと結びつけて分析することで、企業の実態や未来の勝ち筋が見えてくる。「無機質な数字」が「刺激的なドラマ」に変わる!ビジネス・投資・就活に役立つ、一生使えるスキルを解説する。
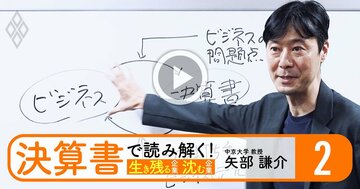
#1
決算書が読めない人は「数字の奴隷」になる!ビジネスの勝敗を決める“企業の勝ち筋”を見抜く方法【動画】
企業の成長と衰退を分ける決定的な要因は何か?売上や利益の数字だけでは、企業の本当の強さやリスクは見えてこない。 決算書には、経営戦略や隠れたリスクがすべて刻まれている。 本シリーズでは、決算書を「戦略の道具」として読み解く方法を、全7回の動画で徹底解説。 単なる数字の羅列としてではなく、ビジネスモデルと結びつけて分析することで、企業の実態や未来の勝ち筋が見えてくる。「無機質な数字」が「刺激的なドラマ」に変わる!ビジネス・投資・就活に役立つ、一生使えるスキルを解説する。

今回は東京ガスと大阪ガス、大手ガス会社2社の決算書をひもといていこう。2024年春、大阪ガスの時価総額が東京ガスを上回った。実に20年超ぶりのことだという(24年12月の本稿執筆時点では、再び時価総額で東京ガスが逆転したが)。大阪ガスの株価が上昇した背景には、同社が新たに目標値として掲げた「新指標」の効果があったとみられる。その指標とは。

日立製作所とパナソニックホールディングス――。ともに大規模な構造改革を進めてきた日本を代表する総合電機メーカーの2社だが、「株価の伸び」については大差がついている。両社のキャッシュ・フローの推移を比較すると、その要因が見えてきた。

今回は、日立製作所とパナソニックホールディングスの決算書を見てみよう。日本を代表する総合電機メーカーの2社は、近年、大規模な構造改革を進めてきた。そんな2社の株価の推移を見てみると、明暗がくっきり分かれていた。その理由とは何か。

建設業界で世界シェア1位のキャタピラーは、23年12月期のROE(自己資本利益率)が約53%となった。一方で、同2位のコマツは約12%だ(24年3月期)。株式市場が注目する重要な指標において、業界トップ2社の間に大きな差がついた理由とは何だったのか。指標を“分解”して詳しく見ていこう。

ROE(自己資本利益率)やROA(総資産利益率)は、ニュースでよく目にする指標だ。KPI(重要業績評価指標)として採用する企業も多い。建設機械大手のコマツもその一つだ。今回は、建設機械業界シェア1位の米キャタピラーと、2位のコマツの決算書からその特徴と、ROEやROAに表れた違いを見ていこう。
