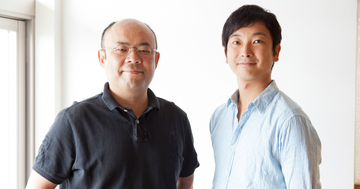ミクシィ復活をけん引し、現在は複数の企業の取締役やアドバイザーのほか、スタートアップ投資活動(Tokyo Founders Fund)など、幅広い活躍をつづける朝倉祐介さん。そうした多面的な経験をベースに築かれた経営哲学をぎゅっと凝縮した初の著書『論語と算盤と私』が10/7に発売となりました。発売を記念し、本書で取り上げた経営テーマに即してさまざまな分野のプロとのリレー対談をお送りしています。
今回のお相手は株式会社経営共創基盤(IGPI)代表取締役CEOの冨山和彦さんです。危機に瀕した組織の状況から、今後有望なビジネスにおける日本企業の優位性と弱点などに話題が広がった前編につづき、この後編では、日本企業が不連続な変化のなか強みを発揮するために改革すべき会社の基本OSともいえるガバナンス変革について議論が深まります。(構成:大西洋平、撮影:疋田千里)
その場で調和を保って嫌われたくない、
と思うタイプの人は経営者失格
朝倉 前編でトップダウンの話が出たところで、経営者やガバナンスのあり方についても少し伺えますか。
再生期の会社を率いたためかもしれませんが、経営者の役割の一つは“業”を負うことだと私は考えています。たとえば、社員の人たちは会社であれ事業部レベルであれ、所属している組織やコミュニティに対しての愛着をある程度持って働いているはずです。だから、いきなりトップに、「この事業は他社に譲渡します」とか、「まったく別の部署に異動してもらいます」と宣言されても、「ふざけるな!」という話になってしまう。ただ、組織全体が倒れるのを防ぐためには、そうした判断が必要な局面もあります。こういった意思決定を血も涙もなく敢行できれば、トップとしては非常にラクなのでしょうが、一方でそれだとリーダーとしての深みがないとも思うのですが、いかがでしょうか?
 冨山和彦(とやま・かずひこ)さんプロフィル/1960年東京生まれ。ボストンコンサルティンググループ、コーポレイトディレクション代表取締役社長を経て2003年産業再生機構代表取締役専務業務執行最高責任者(COO)。07年持続的な事業・企業価値の向上を目指し、経営支援サービスを提供する経営共創基盤(IGPI)設立、同代表取締役CEO就任。東京大学法学部、スタンフォード大学経営学修士及び公共政策課程修了。司法試験合格。『これがガバナンス経営だ!ストーリーで学ぶ企業統治のリアル』(2015年、東洋経済新報社)、『IGPI流ビジネスプランニングのリアル・ノウハウ』(2015年、PHP新書)など著書多数
冨山和彦(とやま・かずひこ)さんプロフィル/1960年東京生まれ。ボストンコンサルティンググループ、コーポレイトディレクション代表取締役社長を経て2003年産業再生機構代表取締役専務業務執行最高責任者(COO)。07年持続的な事業・企業価値の向上を目指し、経営支援サービスを提供する経営共創基盤(IGPI)設立、同代表取締役CEO就任。東京大学法学部、スタンフォード大学経営学修士及び公共政策課程修了。司法試験合格。『これがガバナンス経営だ!ストーリーで学ぶ企業統治のリアル』(2015年、東洋経済新報社)、『IGPI流ビジネスプランニングのリアル・ノウハウ』(2015年、PHP新書)など著書多数
冨山 そういう振る舞いを続ければ、結局は指示に従う人がいなくなっちゃうでしょうね。
朝倉 だけど、組織全体のためであったり、当人のためになると思って非情な意思決定をしても、いつかその真意を理解してもらえるとは限りませんよね。
冨山 その点に関しては、「わかってもらえる日がくればラッキー」ぐらいの感覚で、あまり期待しないほうがいいかもしれません。
朝倉 やはり、周囲から好かれたいと思っている人は経営者に向いていないということですか。
冨山 とりあえず、その場で調和を保って嫌われたくないと思う人は経営者として失格ですね。そういった心理の裏側にあるのは、短期的な保身です。勝負に出ると、嫌われちゃう可能性が高いからです。
朝倉 単純に嫌われたくないという思いに端を発しがちな組織の情理のことを、私は著書の中で「不作為の罪」と表現しました。
冨山 結果、不作為ということですよね。基本的には不作為のゲームを続けておけば、致命傷を負う恐れが少なくなります。絶対に勝てるゲームだけ仕掛けて「勝負した」というトラックレコードさえ持っておけば、あとは引き分けに次ぐ引き分けで1勝14分けのアベレージが最も好都合です。勝ち星を増やそうとすれば、おのずと負け星も増えるでしょ。
朝倉 その意味では、日立製作所や富士フイルムのように巨大かつエスタブリッシュメントな会社が思い切った変革を遂げたられたのはすごいことですね。
冨山 どちらもゆっくりとお湯の温度が上がって“ゆでガエル”になるパターンではなく、いきなり熱湯になったからでしょう。日立は史上最悪の大赤字を出して倒産の危機に晒されたし、富士フイルムもデジカメの台頭で写真フイルムがなくなるという大変化を突きつけられました。だから、ある意味では幸運だったわけです。じわじわとお湯の温度が上がっていると、内部の人間はそのことを検知しようとうする動機付けがありません。熱湯に達する前の段階で、社内的に警告を発するということは極めて難しいです。
朝倉 えてして“ゆでガエル”のたとえ話をする際、対象となる人々は会社の危機に全くきづいていない集団として、戯画的というか、コミカルなイメージで語られがちです。でも、往々にして内部の人たちも頭では危機が迫っていることを理解していますよね。
冨山 もちろん、頭の中ではわかっていて、“ゆでガエル”を避けるにはダウンサイジングのためのリストラに踏み切らなければならないことも承知しているはず。それには組織内で勝負する必要がありますから、特に出世コースを進んでいる人間ほど、勝負に負けて先の道が閉ざされてしまうことを恐れることでしょう。このまま普通にいけば倒産は15年後だから、俺もうこの会社にいないよな、と勝負を避けるんですよ、エリートコースのヤツほど。
取締役は執行役員の上がりポストではない
「島耕作」的なキャリアパスの終焉
朝倉 それを防ぐためにどうするかなんですけど、問題があると思うのは、今も一般的と思われている日本企業のキャリアパスです。課長、部長、取締役、常務、専務、社長と着実に昇進していく人気漫画の『島耕作』シリーズは、昭和的なキャリアパスを忠実に再現した優れた時代劇ですが、ああいったサラリーマン像をこれからのモデルにするのは問題じゃないかと思います。そもそも執行役と取締役では転向といえるほど役割が違うはずですよね。
冨山 環境が連続的に変化して右肩上がりの経済が続いている中では、同質的で連続的な組織体のほうが強みを発揮しますから、良かったんですよね。しかし、1990年ぐらいを境にそうした連続的な経済は途絶えました。さらにグローバル化が進展し、デジタル革命も本格化して、環境の変化が不連続で発生していったわけです。その結果、瞬く間に日本型企業の優位性が薄れていきました。自動車や素材関連は辛うじて持ちこたえていますが、エレクトロニクスは壊滅的なダメージを被っています。
 『論語と算盤と私』著者の朝倉祐介(あさくら・ゆうすけ)さんプロフィル/1982年生まれ。兵庫県西宮市育ち。中学卒業後に騎手を目指して渡豪。身体の成長に伴う減量苦によって断念。帰国後、競走馬の育成業務に従事した後、専門学校を経て東京大学法学部卒業。在学中にネイキッドテクノロジーを設立。マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、ネイキッドテクノロジーに復帰し代表に就任。同社の売却先となったミクシィに入社後、2013年より同社代表取締役に就任し、業績の回復を機に退任。2014年よりスタンフォード大学客員研究員。複数企業の取締役、アドバイザーを務めるほか、起業経験者によるスタートアップ投資活動(Tokyo Founders Fund)も開始している
『論語と算盤と私』著者の朝倉祐介(あさくら・ゆうすけ)さんプロフィル/1982年生まれ。兵庫県西宮市育ち。中学卒業後に騎手を目指して渡豪。身体の成長に伴う減量苦によって断念。帰国後、競走馬の育成業務に従事した後、専門学校を経て東京大学法学部卒業。在学中にネイキッドテクノロジーを設立。マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、ネイキッドテクノロジーに復帰し代表に就任。同社の売却先となったミクシィに入社後、2013年より同社代表取締役に就任し、業績の回復を機に退任。2014年よりスタンフォード大学客員研究員。複数企業の取締役、アドバイザーを務めるほか、起業経験者によるスタートアップ投資活動(Tokyo Founders Fund)も開始している
朝倉 つまり、もはや「島耕作」モデルが通用しない時代になっていることを意味しているわけですね。
冨山 そうでしょう。戦術とか戦力の問題ではなく、要は日本企業のOS(オペレーションシステム)が現状に合っていないということです。とはいえ、人生に1度しかない約30年間のサラリーマン人生で、ようやく上のほうまで上りつめてきた人間が、今までのルールを自分で大きく変えるのは難しい。予選から勝ち上がって甲子園出場を果たしたのに、「ここから先は野球ではなく、サッカーで勝敗を決めなさい」といきなり告げられるようなものですよ。
すると、内発的なメカニズムだけで会社を変えることにはおのずと限界が出てきます。やはり、外圧的な規律を働かせるという仕組みを企業経営の中に採り入れることが必要です。それも単なるアドバイザーではなく、相応の権限を有することが肝心でしょう。ガバナンスの中に多様性を担保しておくことが求められ、社外取締役の必要性が問われています。
朝倉 会社のフォーマットをガラリと変えるうえで重要なのは経営であり、トップであり、役職でいうと取締役のレイヤーだと思うのですが、日本の会社だと取締役が“スーパー執行役員”のような捉えられ方をいまだにされていますよね。
冨山 日本はマネージメントボードモデルでやってきたからね。会社法上の原理原則で言えば、あくまで代表取締役はその会社の代表であって、取締役会の代表ではありません。本来なら、取締役会の中では最も末席に位置づけられるべきで、代表取締役は他の取締役たちから監督される立場にあります。本来、取締役は執行役員のなれの果てじゃないんですよ。
朝倉 にもかかわらず、取締役が執行役員の延長線上にあるようなイメージになったのはなぜでしょうか。
冨山 戦前は会社法に則った経営が行われていたようですが、戦後になってズレが生じています。先にも述べたようにバブル崩壊までは連続的変化が続き、そういった環境下では監督的な規律を正す必要性がほとんどなかったんでしょうね。その結果、代表取締役はサラリーマン的な出世街道の一番わかりやすいゴールとなったわけです。こうした一直線の道筋でトーナメント戦をやったら、組織モデル的にはものすごく上手く機能したのでしょう。
戦後30年間ぐらいはその状態が続いたので、それが当然だと誰もが思っています。第二次大戦の敗戦のように鮮烈な出来事があれば、それから180度の変化も生じうるでしょう。日本人ってそういうとき平気でガラッと変わるから(笑)。でも、日本企業の凋落は緩慢なる“経営敗戦”の歴史であって、その流れの中で気づくのはなかなか大変です。だから結果として、ガバナンス改革もなぜか政府のお世話になって進められようとしています。