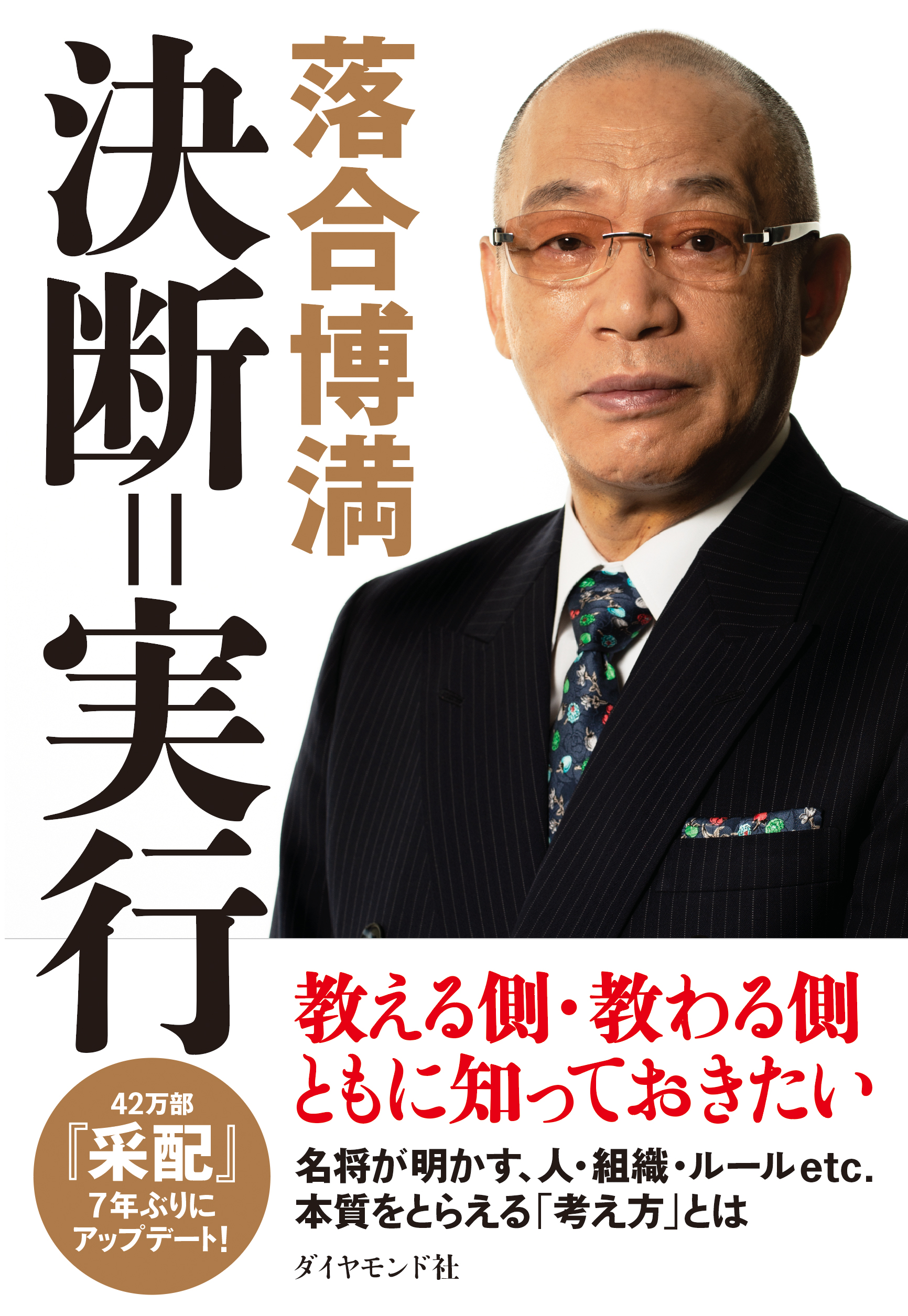名将が語る、人・組織・ルールetc.本質を捉える「考え方」とは、どういうものだろうか。 落合博満氏の新刊『決断=実行』の刊行を記念して、特別に本書の中身を一部公開する。(まとめ/編集部)
 落合博満著『決断=実行』特別公開
落合博満著『決断=実行』特別公開※写真はイメージです
仕事に取り憑かれろ
あの時、別の道に進むべきだったのか。自分の人生はこれでよかったのか。
齢を重ねれば重ねるほど、あるいは人生がうまくいっていないと感じた時ほど、そうやって自分自身の人生を振り返るものだろう。だが、自分が歩んできた道は、すでに歴史になっているのだ。ならば、「これでいいんだ」と踏ん切りをつけることが、その先に進んでいくための原動力、次への一歩になるのではないか。私はそう考えている。
〈略〉
人や組織を動かすこと以上に、実は自分自身を動かすことが難しい。それは、「こうやったら人にどう思われるのか」と考えてしまうからである。だからこそ、「今の自分には何が必要なのか」を基本にして、勇気を持って行動に移すべきだろう。
拙著『采配』の「おわりに」にこう書いた。
チームは常にその年限りのものであり、残した結果もその年のチームのもの。そのチームを率いたのはあなた自身なのだ。それは、高校でも大学でも、少年野球でも変わらない。
だからこそ、あなたは「このやり方でいいのだろうか」、「こんなことをしたらまわりになんと言われるだろう」という思いを振り払い、自分の信念に従って最善と思える決断をしてもらいたい。
これは、拙著『落合博満 アドバイス』の「おわりに」の一文である。
私の人生を振り返ると、これらの考え方が基本にあると感じている。そして、誰かに相談を持ちかけられた際にも、「人目を気にせず、自分がこうだと思ったことをやり抜けばいい」と助言することが多いと思う。
ただ、ある人によれば、「人目を気にせず、自分がこうだと思ったことをやり抜く」のがとても難しいという。それができるから落合博満なのであり、「オレ流」と呼ばれるのだろうと。
私はそんなに難しいことを考え、実行しているのか。そうした視点で自分の足跡をたどってみると、私がなぜ「人目を気にせず、自分がこうだと思ったことをやり抜く」ことができるのかが少し見えてきた。
1978年のドラフト会議でロッテオリオンズから3位指名され、私はプロ野球選手になることができた。だが、甲子園で活躍したり、大学球界を代表する選手ではなく、ドラフト1位でもなかったから、メディアからはほとんど注目されなかった。また、1年目の春季キャンプでは、「あのフォームでは、インコースは打てないだろう。プロでは無理だ」と山内一弘監督に言われてしまった。キャンプ地を訪れる野球評論家の大半も、私のバッティングを酷評した。
そう、私のプロ野球生活は、誰にも期待されずにスタートしたのだ。
その後、3度の三冠王を手にしたこともあり、私の野球に関して否定的な意見を口にする人はいなくなった。久しぶりに、そんなプロ野球界に入った頃の気持ちを思い出したのは、2003年10月に中日ドラゴンズの監督に就任した時だ。
外国人をはじめ目立つ補強はせず、現有戦力を10%底上げして優勝すると記者会見で話すと、「そんなことができるわけない」という見方が大勢を占めた。翌春のキャンプで初日に紅白戦を実施し、休日は1週間に1日という6勤1休のスケジュールを組むと、「あのやり方では選手が壊れてしまう」と言われた。
だが、その年のペナントレースを制すると、手のひらを返すように、厳しい練習をはじめとした私のやり方は認められた。このように、選手の時も監督を務めた時も、しっかりと結果を残せば周りは何も言わなくなる。
最近はあまり見られなくなったが、かつては打撃タイトルを争う選手の所属チームがペナントレース終盤に直接対戦すると、相手の打者に打たれたくないという理由で敬遠合戦になることが珍しくなかった。
確かに、見栄えのしないシーンである。しかし、敬遠合戦を経てでも首位打者や本塁打王を手にした選手は、その年のタイトル獲得者として永遠に名前が残る。そこには、敬遠合戦を経て獲得したタイトルだという注釈はつかないし、しばらくすれば「あのタイトルはいかがなものか」と批判的だった人たちの記憶からも、敬遠合戦のことは次第に消えていく。つまり、タイトルを獲ったという事実だけが残るわけだ。
ならば、ルールから外れることさえしなければ、どんな手段を用いてでもタイトルを手にしたほうがいい。そういう世界で私は生きてきた。やはり、ものを言うのは結果なのだ。いや、残した結果でしか語れない部分がある。
だからこそ、少しでもいい結果を残すために、私は野球(仕事)に打ち込んだ。
ロッテに入団してから2年間は、一軍とファームを行ったり来たりしている立場だったから、一軍に定着することを目指した。3年目に一軍に定着し、幸運にも首位打者を手にしたあとは、何らかのタイトルを手にできるように技術を磨き、4年目には三冠王だ。そこからは、毎年、三冠王を獲得することだけに注力した。
練習が好きな選手はいないだろう。私も例外ではない。できれば練習せずに寝ていても、試合になれば打てるようになりたかった。だが、それが無理だと分かっているから練習した。どうせ練習するのなら、誰よりもバットを振り、引退するまで満足できる結果を残し続けようと考えていた。
入団した時のバッティングを酷評した人たちを、見返そうなどとは考えたことはない。反対に、三冠王を手にしてからは大きな期待を受けることもあったが、そうした期待に応えようと練習したわけでもない。
野球は私の仕事で、球団が来年も契約したいと思う結果を残せなければクビになってしまうのだから、翌年もプレーできる結果を残すことに集中した。そのためには、24時間365日、野球のことだけを考える生活が必要だから、そうしたまでだ。
格好をつけた表現になってしまうが、選手の時も監督の時も、ただ野球という仕事に取り憑かれた。認めてもらいたいと人に取り憑かれたのではなく、ただ野球という仕事に取り憑かれた。
そうすれば、何も迷うことはなかった。
これをやってみたい。けれど、周りはなんと言うだろう。そんな不安は抱かなくてすむ。
もちろん、20年の現役生活で三冠王を手にできたのは3回だし、監督を8年間務めて優勝できたのは4回なのだから、目指すべき結果を残せなかったシーズンのほうが多い。それでも、どんな時も最善を尽くしているのだから、「今年は思い通りの結果を残せなかった。けれど、チームとしては、これが今年の目いっぱいの力だったのだ」と踏ん切りをつけ、次のステップに進むしかない。
そうやって生きていくのは、それほど難しくはないだろう。少なくとも、私でなければできない「オレ流」ではないと思う。
私の場合は、選手の時も監督の時もマイナスのスタートラインから歩き始めた。だから、ドラフト1位で指名され、周囲から大きな期待を寄せられてプロ入りした人の気持ちはよく分からない。だが、マイナスからのスタートとはいえ、私に期待してくれた人が一人もいなかったわけではない。
山内監督に見放されても、毎日の練習を手伝ってくれるコーチはいた。山内監督だって、私のすべてを否定したわけではなく、何かにつけて気にかけてくれてはいた。
技術というのはおもしろいもので、数年後の私の打撃フォームには、山内さんから教わったことがいくつも取り入れられていた。それに気づいた時は、驚きとともに自分の未熟さを痛感させられた。
また、批判された監督1年目の春季キャンプでも、川上哲治さん、廣岡達朗さんら、監督として実績を残している先輩たちは「いい練習をしている。これなら勝てる」と見てくれた。どれくらい期待されるかに個人差はあっても、誰からも期待されない人などいない。
たとえば、企業の人事にサプライズはつきものだろう。部下の間で「次はあの人で間違いない」という人材が係長になることもあれば、「まさかあの人が……」という場合もあるはずだ。部下からの評判が芳しくない人が係長になれば、そういう空気を察してやりにくさを感じるのかもしれない。
しかし、その人も上司に認められたから係長になれたのだ。ならば、結果を残すことだけに全力を注げばいいのではないか。プロ野球のタイトルと一緒で、ある程度の結果を残せば「あの人は係長になって変わった」と、手のひらを返したようにいい評判を聞くようになるものだ。
世間の人たちは、勝負の世界で気持ちが顔に出るのは不利になるとポーカーフェイスに努めていた私の表情、あるいはメディアにあまり口を開かない態度を不敵だと感じ、相当タフな精神力の持ち主だと思っているのかもしれない。
だが、秋田の田舎から上京し、人疲れしていた私を知らないだろう。どちらかと言えば人見知りで、グイグイと距離を詰めてくる人に圧倒されてしまう私を知らないだろう。できるだけ穏やかに生きていたいと、派閥めいた集まりに顔を出すのは気が進まない私を知らないだろう。
私に言わせれば、はじめから特別な能力を持っている人などいない。プロ野球の世界で、いわゆる素質の有無に左右されるのは否定しないが、素質だけに頼った人よりも、死に物狂いでプレーした人が圧倒的に多い。
どんな仕事でも、勉学でも、失敗したって命まで取られるわけじゃない。くよくよ悩むのも、決して恥ずかしいことではない。「今日は何もできなかった」と失望する日もあるだろうが、そんな日でも「1日を生きた」という経験だけは積んでいるのだ。どんな仕事でも、そのうちに経験が生きることはある。
そのためにも、ただひたすら仕事に取り憑かれろ。