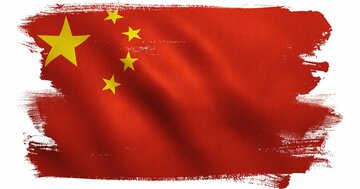ちなみに、3月の共同通信社の世論調査において、新型コロナウイルス対策として望ましい施策について尋ねたところ、消費減税は43.4%であり、現金給付の32.6%を上回ってトップであった。
このように、消費税は、衆議院解散の大義となるという観測があったり、野党再編における争点の一つとなったりと、コロナ禍の中で動揺する政局の行く末を左右する問題となりつつあるようにもみえる。
消費減税を巡っては、すでに多くの経済学者等が論じており(その大半は消費減税に否定的な見解である)、さまざまな論点が提出されている。本稿では、こうした諸論点を念頭に置きつつ、改めて消費減税の妥当性を論じておきたい。
世界の「常識」に背を向ける国・日本
消費税の政策的な意義にはさまざまな側面があるが、まずは、コロナ不況に対する経済対策としての面から検討しよう。
最初に確認すべきは、不況時に減税措置を講じるのは、いたって真っ当な経済政策であるということである。これについては、本来であれば、わざわざMMTを援用するまでもなく、主流派経済学においても、入門書レベルの「常識」であるはずだ。
消費税は、消費に課される税である。温室効果ガスの排出に課される環境税が、温室効果ガスの排出を抑制するのと同じように、消費税には、消費を抑制する効果がある。
したがって、不況時に消費を喚起したければ、消費税の減税は有力な選択肢の一つになるのは当然である。逆に言えば、不況時で消費が落ち込んでいる時の消費増税は、非常識としか言いようがないのだ。
ゆえに、コロナ禍によって、消費がかつてない規模で急減している中においては、消費税の軽減は正しい措置である。ドイツやイギリスなど23ヵ国が消費税を減免したのも、至極当然であった。
もちろん、感染拡大防止の観点から経済活動が制約される状況だから、消費を喚起する効果は限定的かもしれない。しかし、消費者の負担を軽減し、国民の生活をより楽にすることに疑いの余地はない。しかも、低所得者ほど、所得に占める消費の割合が高いので、その恩恵はより大きいのだ。
実は、我が国でも、2019年、消費税率の8%から10%への引き上げを前に、安倍総理は「リーマン・ショック級のことがない限り」、消費税率の引き上げは予定通り行うと繰り返し強調していた。これは、裏を返して言えば、リーマン・ショック級の大不況が勃発したら、消費税率は10%にすべきではないということだ。その意味では、当時の日本政府は、不況時における増税は不適切であるという「常識」を共有していたのである。
2020年に入って勃発したコロナ禍は、リーマン・ショック級どころか、それをはるかに凌駕する戦後最悪の不況を引き起こした。そうであるならば、消費税は、最低でも8%に戻してもよいはずだ。そうでない限り、「リーマン・ショック級のことが起きれば、消費税率を引き上げない」とした昨年の方針との整合性がとれないはずである。
ところが、コロナ禍において、消費減税は行われなかった。
それどころが、6月末日でキャッシュレス決済のポイント還元事業が終了したため、7月以降は、実質的に、消費税が再び増税されたことになる。つまり、不況下、しかも戦後最悪の大不況下で消費増税を行うという非常識な政策が行われたのだ。
そもそも2019年の「消費増税」が非常識だった
仮にコロナ禍が勃発しなかったとしても、2019年10月の消費増税は、経済政策の「常識」からは逸脱したものであった。というのも、日本経済は、2018年10月から景気後退に入っていたのであり、世界経済の成長率も2019年はリーマン・ショック以降最低水準という見通しであった。
つまり、消費税率の10%への引き上げは、国内外ともに景気が後退する中で断行されたということになる。2019年10~12月期のGDP(国内総生産)は年率換算7.1%減となったが、これは、景気後退期での増税が引き起こしたセオリー通りの結果であって、何も驚くようなことではない。