中野剛志
トランプ大統領が8月1日から、日本からの輸入品に「25%」の関税を課すことを発表した。高率関税賦課の根拠は第1次世界大戦の戦時法制の流れをくむ国際緊急経済権限法で、貿易赤字は米国にとって「異例かつ重大な脅威」というわけだが、金本位制離脱やニクソン・ショックなど国際経済システムを自国に有利に改変する際には戦時法制を活用してきた米国にとっては異常なことではない。

EUがウクライナ支援や対ロ安全保障強化のため国防費増額で合意した「ヨーロッパ再軍備計画」はドイツが積極財政に転換したことが大きな要因になった。今後、財政統合、さらには政治統合に進む可能性を感じさせるが、一方で各国の経済ナショナリズムの高まりもありEU深化の大きな岐路だ。

財務省がここまで嫌われる「根本的な理由」とは?【書籍オンライン編集部セレクション】
『安倍晋三 回顧録』の財務省批判に対し、元大蔵事務次官・齋藤次郎氏が「荒唐無稽な陰謀論」「財政規律が崩壊すれば、国は本当に崩壊してしまいます」などと反論(『文藝春秋』2023年5月号)して、話題となっている。しかし、齋藤氏の反論は妥当なのだろうか? 資本主義における財政の仕組みを根本から解説した『どうする財源ー貨幣論で読み解く税と財政の仕組み』の著者・中野剛志氏が検証する。

「103万円の壁」見直しは、自民、公明党が示した課税最低ラインを123万円に引き上げる案に国民民主党が低すぎるとして反発し、協議打ち切りを表明、結末は一段と不透明になった。もともと見直しの議論に誤解も多かったが、減税による税収減に固執したことが根本的な間違いだ。
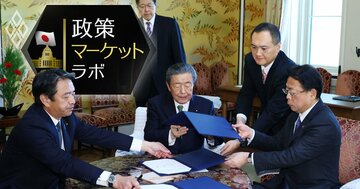
成長戦略としてNISA(少額投資非課税制度)拡充などの「貯蓄から投資」への取り組みが行われてきたが、株式市場は活性化しても経済成長や賃金上昇には結びついていない。企業が投資資金を調達し付加価値を生むのを支える株式市場が、自社株買いのように企業が創造する価値を収奪する場になっているからだ。

財政制度等審議会は「金利ある世界」のもと財政健全化の必要性を強調するが、超低利時代にも歳出抑制を掲げ経済停滞を長引かせた失敗の反省がなく、金利上昇は成長の証で税収も増えることや国債利払い費増は民間の貯蓄増になるなど、財政と実体経済の関係や影響を理解しない“財政独りよがり”の認識が目立つ。

日本がGDPで世界4位に転落したのは1990年代後半以降、間違った経済政策を続けてきたことが最大の原因だ。需要不足でデフレに陥った中、金融緩和を除き財政健全化や「小さな政府」路線で需要を抑え、規制緩和などの供給を拡大する“逆向きの政策”を続けてきたからだ。

岸田首相が「増収の国民還元」を掲げた所得減税の議論の混乱の背景には税や国債について間違った認識がある。信用貨幣論の考えの下では、税とは財源確保の手段でなく、政策経費の財源は国債発行であり税収ではない。正しい財源論議をするにはこの理解が必要だ。

コロナ禍からの回復が進む中、財政の「平時への移行」が主張されるが、危機と不確実性に満ちた「複合危機」の時代には積極財政は常態化が必然だ。金融政策も含め「裁量」に重きを置いた政策に発想を切り替える必要がある。

米債務上限問題で懸念されたデフォルトは米国のような自国通貨を発行する政府では起きない。「複合危機」の時代にその克服は積極財政しかなく、債務上限を法定していることが「真の危機」を招きかねない状況にしているのだ。

財務省がここまで嫌われる「根本的な理由」とは?
『安倍晋三 回顧録』の財務省批判に対し、元大蔵事務次官・齋藤次郎氏が「荒唐無稽な陰謀論」「財政規律が崩壊すれば、国は本当に崩壊してしまいます」などと反論(『文藝春秋五月号』)して、話題となっている。しかし、齋藤氏の反論は妥当なのだろうか? 資本主義における財政の仕組みを根本から解説した新刊『どうする財源』がベストラーとなっている評論家・中野剛志氏に検証してもらった。

「国債60年償還ルール」の見直し論に財政規律が緩むとの批判があるが、日本はすでに財政法4条という規律を保つ枠組みを持つだけでなく、国の債務は完済するという国際標準とは違う財政運営をしていることを認識する必要がある。

インフレ抑制でFRBが急ピッチで利上げを進めているが、今は供給制約が原因のコストプッシュ・インフレだ。金融政策での対応は難しく、利上げは需要を抑え失業や不況をもたらす「悪手」だ。

安倍元首相が進めたアベノミクスは「財政ファイナンス」などの問題で「日本銀行の独立性」を侵したとの批判があるが、中央銀行や金融政策は民主的統制を受け、もともと政治から独立しているものではない。

円安で原油など輸入価格上昇が加速するが日本銀行は景気悪化を懸念し利上げができず袋小路だ。だが省エネ投資などの財政支出で需要を拡大し利上げ環境つくれば同時に供給のボトルネック解消にもつながる。

ウクライナ危機を契機に世界経済は「スタグフレーション」の様相を強めるが、グローバル化の行き過ぎなどによるさまざまな供給制約や地政学リスクが複雑に絡み、事態は70年代のときよりはるかに深刻だ。

日本経済を壊滅させる「スタグフレーション」に警戒せよ
スタグフレーションが始まった。物価が上昇しているのに、経済が停滞し、国民所得も増えないスタグフレーションのもとでは、国民の生活は苦しくなる一方だ。それを放置すれば、衰退の一途を辿る日本経済にとどめを刺すことにもなりかねない。では、我々はどうすればよいのか? その答えは、経済アナリスト・森永康平氏の最新刊『スタグフレーションの時代』にその処方箋が書かれている。(評論家/中野剛志)

ロシアの「ウクライナ侵攻」が、日本に突きつける“残酷な現実”とは?
ロシアがウクライナに侵攻したのはなぜか? さまざまな議論があるが、理由は明白。ウクライナがNATOに加盟したら、ロシアの安全保障が危機に陥るからだ。そして、アメリカがロシアに対して経済制裁しかしない理由も明白。アメリカ本国の安全保障には関係がないからだ。この国際政治の現実を踏まえれば、中国が台湾や尖閣に侵攻したときに、日本に何がもたらされるかも明白であろう。その意味で、ウクライナ問題は、「日本の問題」にほかならないのだ。最新刊『変異する資本主義』(ダイヤモンド社)で、日本を取り巻く安全保障問題について詳述した中野剛志氏が解説する。

約40年ぶりの高インフレの米国で価格統制論が急台頭する。新自由主義のもとで長くタブー視されてきたが、主流派経済学者らが有効な処方箋を示せない中、脚光を浴びることになっている。

17人のノーベル経済学賞受賞者が、インフレ抑制のために「積極財政」を求める理由
現在、原油高、物流の混乱、半導体の供給不足などを背景にインフレが起きている。これを受けて、健全財政に固執する論者たちは、「インフレ抑制」のために緊縮財政を主張し始めている。しかし、これは供給不足による「コストアップ・インフレ」と、需要増による「デマンドプル・インフレ」を履き違えた“誤った主張”である。現在のインフレは「コストアップ・インフレ」であり、これを克服するためには「積極財政」が不可欠なのだ。なぜか? 最新刊『変異する資本主義』(ダイヤモンド社)で、インフレと財政政策の関係性を深く考察した中野剛志氏が解説する。
