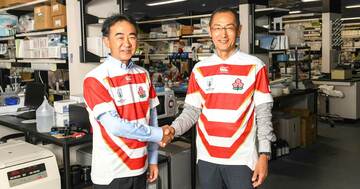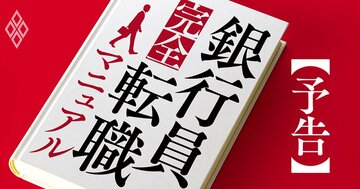ドラマのセカンドシーズンも、いよいよ大詰めの『半沢直樹』。
ドラマ原作の『ロスジェネの逆襲』『銀翼のイカロス』に続き、
シリーズ最新作『半沢直樹 アルルカンと道化師』が9月17日に刊行された。
躍動感のあるエンタテインメントの筋立ての中で、人物の心情に迫った物語は、どのように造形されたのか。刊行開始から12年を経た現在、池井戸潤氏に、新作とシリーズへの思いを尋ねた。
(撮影/小林 司、文/大谷道子)

銀行員としての肌感覚を取り戻す
半沢直樹・原点回帰の物語
――コロナ禍により7月スタートとなったドラマ『半沢直樹』第2シーズン。視聴率も反響も予想を上回り、毎週、世を席巻しています。原作者として、どのようにご覧になっていますか。
池井戸潤氏(以下、池井戸) 毎週観ていますが、シナリオがほとんど役に立っていないドラマですよね(笑)。一応僕のところにも送られてくるので台本には目を通しているんですが、放送を見ると「あれ? こんな場面あったかな」と。で、調べてみると、やっぱりない。香川照之さんが演じる大和田の《施されたら施し返す。恩返しです》も《おしまいdeath!》も、伊佐山(市川猿之助・演)の《詫びろ詫びろ詫びろ……》もありません。誰がどう決めてああなっているのかまったくわかりませんが、あまりにも変わるから僕にも先が読めなくて、それはそれで面白いなと思って。毎週、楽しんで見ています。
――原作第3作の『ロスジェネの逆襲』編が終わり、現在は航空会社の再建をモチーフにした『銀翼のイカロス』編を放送中。しかし、9月6日にはドラマ本編の収録が間に合わず放送が延期され、代わりにキャストやスタッフによる生放送トークを急遽代替放送されました。それでも、22パーセントを超える高視聴率です。
池井戸 本当に全10回オンエアできるかどうかというところもまた、見どころになっているようですね(笑)。とはいえ、ドラマも終盤に向けてきっちりとストーリーが示される展開になっていくはずなので、さらに楽しめるのではないかと思います。
――その最中、「半沢直樹」シリーズ6年ぶりの新作である『半沢直樹 アルルカンと道化師』が刊行されます。今年1月に行った当媒体のインタビューで予告されていたとおり、舞台はシリーズ第1作『オレたちバブル入行組』の前の時代。いわば“エピソードゼロ”に当たりますが、この時代を舞台にしようと思った理由は?
池井戸 『銀翼のイカロス』まで書いてきて、ちょっと物語が大きくなりすぎたという感覚があったんです。銀行員としてもう少し現場に近い、卑近な戦いを書いてみたい。巨大航空会社と、何千億という資金を巡って切った張ったを繰り広げるのもいいですが、もう少し肌感覚のある話も書いてみたいと。そうすると、半沢が大阪西支店にいた融資課長時代がいちばんいいなと思って。読者目線に比較的近く、規模も大きすぎないから、『半沢直樹シリーズ』の本筋である人間ドラマを際立たせることができるんじゃないかと考えました。いわば、原点回帰というわけです。