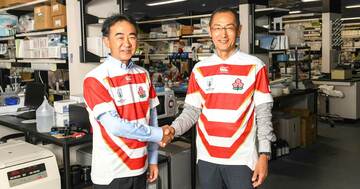Photo by Kuninobu Akutsu
Photo by Kuninobu Akutsu
やられたら、やり返す。倍返しだ――痛快な決めぜりふで世を席巻した前作から7年、ついに2020年春、ドラマ「半沢直樹」が帰ってくる。平成のサラリーマンのヒーローは、新時代をどう生きるのか? 1年で最も売れる「週刊ダイヤモンド」年末年始の恒例企画をオンラインで同時展開するスペシャル特集「総予測2020」。今回は、「半沢直樹」の原作者である池井戸潤氏に尋ねた。(構成/大谷道子)
ドラマ「半沢直樹」は
それまでにない作品だった
――2013年に放送され、記録的大ヒットとなったドラマ「半沢直樹」。原作者として、この大ブレークをどう受け止めましたか。
映像作品に関して僕は完全に他力本願なんですが、おそらくそれまでにない作品だった、ということなんでしょうね。テレビ局のドラマ作りには、例えば「恋愛要素が入っていなければならない」「かわいい女の子をヒロインに」といったヒットのための“縛り”が存在している。おっさんが主人公で、銀行員で、恋愛パートのない「半沢」には、はっきり言ってヒットする要素がほとんどなかったわけです。でも、ふたを開けてみたら、なぜか受けた。その理由は、本当に分かりません。
――ビジネスパーソンにとっては、誰もが実感、共感できる、リアリティーにあふれた作品でした。
一つ言えるのは、「半沢」には原作2冊分(『オレたちバブル入行組』『オレたち花のバブル組』)のエピソードがあった。それはプラスに働いたと思います。
小説をドラマ化するとき、たいてい原作は単行本1冊ですが、これだとだいたい連続ドラマ5、6話分のボリュームしかない。そうすると、尺を伸ばすために、小説には書いていないエピソードやキャラクターをいろいろと追加することになる。でも「半沢」にはエピソードが潤沢にあったので、話の展開に無理がなく、なおかつスピーディーで飽きずに見られたのではと思います。