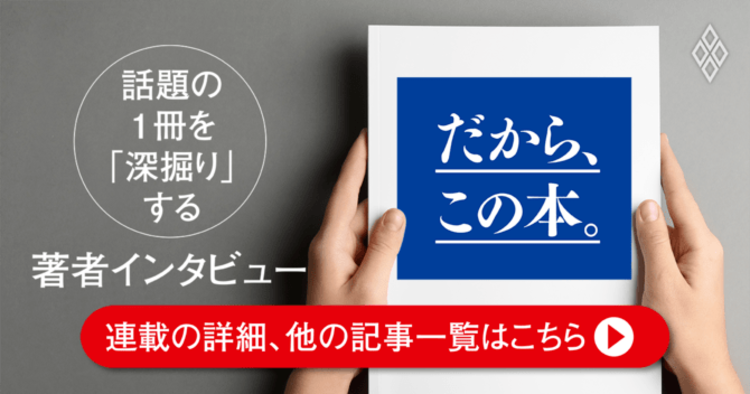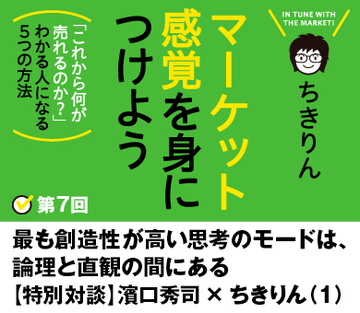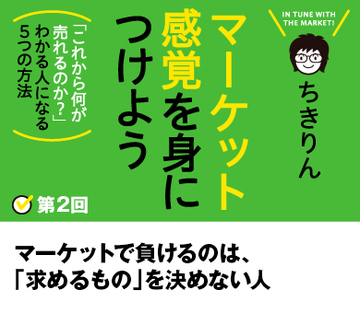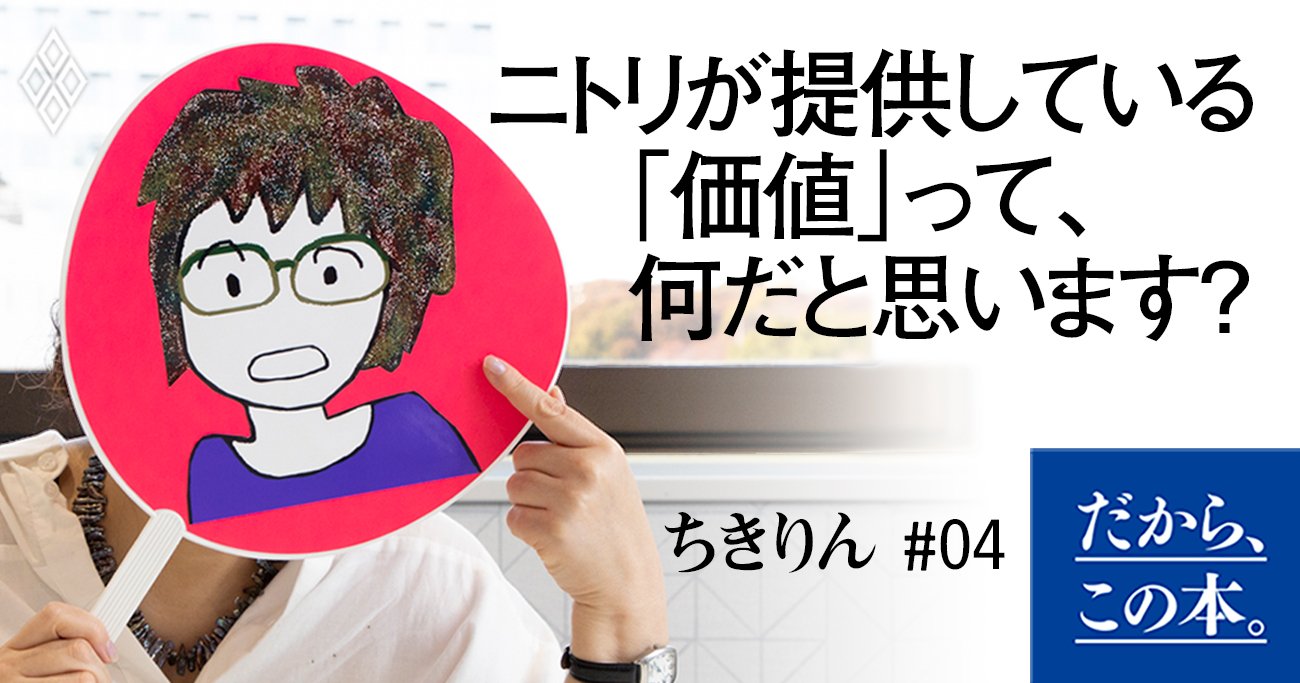
社会派ブロガー・ちきりんさんの『マーケット感覚を身につけよう』で描かれた未来がどんどん現実となり、高学歴でもない人や専業主婦でも、市場価値の高いビジネスに乗りだし、成功する人が増えている。
その一方で、「なんとなく」モノやサービスの価値に気づいても、うまく言語化できずに困っている人もいるのではないだろうか? そこでインタビュー最終回では、「価値」あるものを言語化する方法と、言語化能力の鍛え方について話を伺った。(取材・構成/樺山美夏、写真/疋田千里)
世の中の9割と違う意見でも、
絶対に自分にウソをつかない
――前回まで伺ってきたようにして、市場価値の高いものを見極めるマーケット感覚を身につけても、ちきりんさんのようにうまく言語化できなければ、評価されません。価値を表現するスキルはどのようにして磨けばいいでしょうか。
ちきりん 言語化能力を鍛えたいなら、自分の意見を常に言語化して明確にする訓練をするしかありません。誰でも毎日、食べるもの、着るもの、使うものなど、多くの選択をしていますよね。そのひとつひとつについて、「なぜ自分は今日それを選んだのか?」と意識し、言語化してみてください。特にお金は使うたびに、「いま自分は何の価値に対してお金を払ったのか?」と深掘りし、言語化する練習をしてみればいいと思います。
 ちきりん
ちきりん関西出身。バブル期に証券会社に就職。その後、米国での大学院留学、外資系企業勤務を経て2011年から文筆活動に専念。2005年開設の社会派ブログ「Chikirinの日記」は、日本有数のアクセスと読者数を誇る。シリーズ累計34万部のベストセラー『自分のアタマで考えよう』『マーケット感覚を身につけよう』『自分の時間を取り戻そう』ダイヤモンド社)のほか、『「自分メディア」はこう作る!』(文藝春秋)など著書多数。
Chikirinの日記 https://chikirin.hatenablog.com/
ちきりんセレクト https://chikirin-shop.hatenablog.com/
ツイッター https://twitter.com/InsideCHIKIRIN
そのとき気をつけたほうがいいのは、周りに流されないことです。たとえば牛肉でも、私の場合は「霜降りだらけの脂の塊より、赤身のほうが牛肉は絶対に美味しい!」と思っています。だから「霜降り肉なんてなにがおいしいのかわからない」と明言します。
でも木箱に綺麗に並べられた霜降りだらけの肉を見せられると、多くの人が「わー、おいしそう!」とか言うんです。それって、自分で食べてみて本当にそう思えるのか。広告や世間の常識で「そういう肉がいい肉である」と思わされているだけではないのか、よく考えてほしい。味覚なんて人それぞれで正解なんてありません。それなのに「すべての人にこっちのほうがおいしいはず」なんておかしいですよね。
――日本人がランキング好きなのも、自分に自信がなくて何か目安になるものがほしいからでしょうね。
ちきりん アマゾンにしろグルメサイトにしろ、私は人の評価をそのまま信じることはほとんどありません。ミシュランも星3つでもおいしい店と、なんでこの店が、という店が混在してる。人がなんと言おうと自分が食べて美味しければ美味しい、不味ければ不味い。自分の判断基準を信じることはとても大事です。
映画や本のレビューにおいて、他の評価がどれも絶賛だと、最初に「おもしろくなかった」と書くのは勇気が要ります。そして「私は基本的なことがわかってないから理解できなかった」みたいな、言い訳じみたレビューを書いたりする人がいます。「おもしろいと感じられなかったのは私のせいです」と卑下するのです。
そういうレビューを読むと、ほんとにみんな、自分の意見に自信がないんだなと驚きます。自分がおもしろくないと思えば、普通にそう書けばいい。反対も同じ。酷評されている映画や本でも、おもしろかったら「めっちゃおもしろかった」と表明すればいい。
私の場合、周りと意見が違ってもまったく気になりません。むしろ「私と同じような意見の人がいないってことは、私の意見には価値があるってことね」と嬉しく思えるほどです。
――ちきりんさんが、そこまで自信を持てるようになったのは、自分は間違っていないと実感できる経験を多く積んできたからでしょうか。
ちきりん 小学校の頃から、計算の練習問題をしたあと答合わせをして違っていると「解答ページに印刷ミスがあるんじゃないか?」と思っていました。もちろん私の計算が間違っているんですよ。つまり、私の自信には根拠もなければ能力の裏付けもありません。でも「人と自分が違っているとき」に、まずは自分を信じるようにしてるんです。
計算問題は正解がある問題なので、私のような態度はどうかと思いますが、映画や本や料理の評価には正解がありません。だったらまずは自分の意見を信じるべきです。
「ニトリの価値」を言語化すると?
――マーケット感覚のキーワードでもある「価値」について考えるようになったのは、何かきっかけがあったのでしょうか?
ちきりん 前に働いていた外資系企業がやたらとバリューという言葉を使う会社で、ことあるごとに「おまえは今日、どんなバリューを出したのか?」と問われ続けていたので、そのころから「価値」に注目して考える癖がつきました。
今は身の回りにあるものの価値についても、よく考えます。たとえばコロナ危機のなかでも絶好調のニトリ、あの「ニトリの価値」って何だと思います?
――「青山のマンションの価値は何か?」の質問より難しいです。コスパが高いことでしょうか……。
ちきりん ニトリには私も行く度に「この店はなぜ、いつもこんなに人気なんだろう?」「どんな価値を提供しているのか?」とよく考えます。
私が考えるニトリの最大の価値は、「経済的に余裕がない人でも、インテリアを楽しめるようにしてくれること」です。
ひと昔前までは、インテリアにこだわるなんて贅沢なことで、普通の家庭では不可能でした。一般家庭だと、まずは冷蔵庫を買おう、次は洗濯機だ、そのあとはぜひエアコンを買いたい、という感じで、まずは必要なモノを揃えるだけで精一杯。お部屋をより素敵にコーディネイトするなんてできなかった。
でも当時から、雑誌や映画に出てくるお金持ちのおうちでは、素敵なソファや家具が並んでいた。そういう素敵なお部屋に住めるのはお金持ちの特権だったんです。
でもニトリの店舗が増えてくると、経済的に余裕がなくてもナチュラルとかブルックリンスタイルとか、好みに合うお部屋を作れるようになりました。お金持ちの特権だった「インテリア・コーディネイト」という生活の楽しみを、庶民の手の届くものにしてくれた。これがニトリの最大の価値です。
ニトリはこうした「自分たちの提供している価値」についてまったくぶれない。そこが彼らの強みだと思っています。
考え尽くしたうえで、
12歳のときの自分でも理解できる言葉で書く
――すごく具体的でわかりやすいですね。コスパしか理由が思いつかなかった自分が情けないです。
ちきりん コスパという言葉もそうですけど、面白い、美味しい、希少価値が高いといったざっくりとした言葉でしか価値を表現できないのは、結局のところ、この店の価値とはなにか、十分に深掘りできていないからです。
言語化能力が足りないのではなく、考える量が足りていないだけ。自分で考え尽くしていないものを言語化するのは不可能ですよね。
――言語化するときのセオリーのようなものはあるのでしょうか。
ちきりん 難しい、抽象的な言葉を使わないことかな。私はブログを、12歳のときの自分でも理解できるレベルの言葉で書くようにしています。だから難しい言葉はあまり使いません。誰にでもわかるように書こうとすると、ぼんやりした理解では書けない。むしろしっかり考えることが求められるんです。
ただ、私は小さな頃はよく本や新聞を読んでいました。言語化能力を高めるためにはいろいろな言葉や文章にたくさん触れて語彙力を増やす必要もあります。
とはいえ訓練の基本は、インプットではなくやはり書くこと、つまりアウトプットです。文字にして書いてみると、自分の思考が具体性に欠けることに気づけます。プロのラーメン評論家が食べたラーメンを、「すげえウマかった」「スープも麺も最高!」などと表現しているだけでは、何の説得力もありません。
自分の意見は言語化を経ないと他者には伝わりません。ここは訓練あるのみなので、今は不得意という人も、ぜひ諦めずに頑張って欲しい。それに、表現スキルを身につけると、頭の中で漠然としていたことや、自分の中でモヤモヤしていることも言語化できるようになるので、ストレス発散にも役立つと思いますよ!
【大好評連載】
第1回 5年前の本で、コロナ下の状況を予言したように見えたわけ
第2回 「プライシング能力」が低い人がよくやる失敗
第3回 成功の鍵を握る「市場の選択」という概念