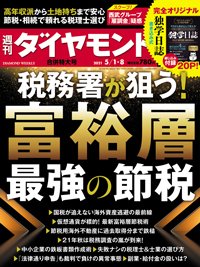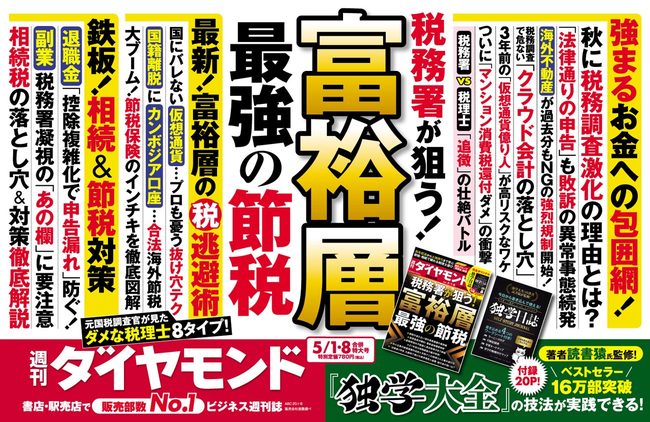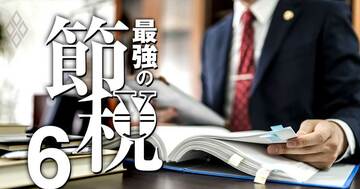税務署がターゲットにするのは、基本的にはやはり“金持ち”だ。国税庁が19年3月に作成した「税務行政の現状と課題」では、「重点的に取り組んでいる事項」として「経済社会の国際化、富裕層への対応」「消費税の不正還付防止」「無申告の把握」の3点を挙げている。先のベテラン税理士は「富裕層は金額が大きいのでおのずと調査対象になりやすく、さらに、増差が調査官の評価に結び付くことを考えると、無申告者からの徴収は増差額が大きくなるためマークされやすい」と話す。
昨今のトピックスとして、個人がメルカリ等でネットビジネスを行い、SNSに「もうかった!」などと無邪気に投稿しているケースは調査官の目に付きやすいという。申告書類はもちろん、調査官はSNSまでもチェックしているのだ。
さらに、税務当局は世間の目を気にする。金余りが続き、投資に成功した人とそうでない人の格差が広がる中、仮想通貨も要注意といえるだろう。現状では、仮想通貨が国税の網の目を擦り抜けているケースもある。その動きが拡大すれば、今後、税務当局が黙ってはいないだろう。
実際、あまりに目につくからか、すでに規制されてしまったものがある。これまでは不動産は保険と並び“二大節税商品”の一つだった。特に海外不動産を利用した節税策は富裕層を中心に近年人気を集め、オープンハウスなどの大手不動産会社がこぞって販売するほど。ところが業を煮やした国税が、過去に不動産を購入した者までひとからげで節税効果を帳消しにする前代未聞の強烈規制に2021年度から乗り出したのだ。
コロナ禍でも税務調査の手が緩められることはなく、富裕層、コロナ禍でも“もうかっている”企業、そして多様な稼ぎ方で新たな利益を手にしている個人に対しては、特に調査官は目を光らせている。もちろん、まっとうに納税していれば何も恐れることはないが、この秋は特に、調査官の“手の内”を知り、正当な節税対策の知識を身に付け、備えを万全にしておきたい。