メール、企画書、プレゼン資料、そしてオウンドメディアにSNS運用まで。この10年ほどの間、ビジネスパーソンにとっての「書く」機会は格段に増えています。書くことが苦手な人にとっては受難の時代ですが、その救世主となるような“教科書”が今年発売され、大きな話題を集めました。シリーズ世界累計900万部の超ベストセラー『嫌われる勇気』の共著者であり、日本トッププロのライターである古賀史健氏が3年の年月をかけて書き上げた、『取材・執筆・推敲──書く人の教科書』(ダイヤモンド社)です。
本稿では、その全10章99項目の中から、「うまく文章が書けない」「なかなか伝わらない」「書いても読まれない」人が第一に学ぶべきポイントを、抜粋・再構成して紹介していきます。今回は文章のリズムを決定づける「句読点」について。(写真/兼下昌典)
 『取材・執筆・推敲』の著者・古賀史健が2021年に開校した「バトンズ・ライティング・カレッジ」
『取材・執筆・推敲』の著者・古賀史健が2021年に開校した「バトンズ・ライティング・カレッジ」
文章にも、心地よい音楽的リズムがある
今回は、文章の「リズム」について考えたいと思います。リズムのなかでもいちばんわかりやすい「音楽的リズム」の話です。
人は、どんな文章を気持ちよく思って、どんな文章を気持ち悪く思うのか。
本来これは、個人の感覚や感性に帰結する問題です。また、同じ人間であっても読む場所やタイミング、年齢などによって、感じ方に違いは出てくるでしょう。なので、文章のリズムを考えるときにも、基本的には「自分が気持ちいいと思うリズム」で書いていくしかありません。無理にルールを設けるほうが、リズムを損なわせてしまうでしょう。
日本語のリズムといってよく引き合いに出されるのが、短歌や俳句などに見られる「五七調」や「七五調」です。古典的な詩歌の世界にとどまらず、その韻律は童謡や唱歌、交通標語や広告コピー、あるいはポピュラーソングのなかにまで求めることができます。万葉の時代から、五拍や七拍の音でつくられるリズムは、なぜか気持ちよく、憶えやすい。日本語を母語とする人間にとって、これはほとんど生理的な感覚といえるのかもしれません。
しかし、五七調や七五調はそもそも詩歌(韻文)のリズムであって、実用的文章にそれを当てはめようとするのは無理があります。そこでぼくは、文章の音楽的リズムを決定づける要素を、「句読点」と「語尾」のふたつで考えています。
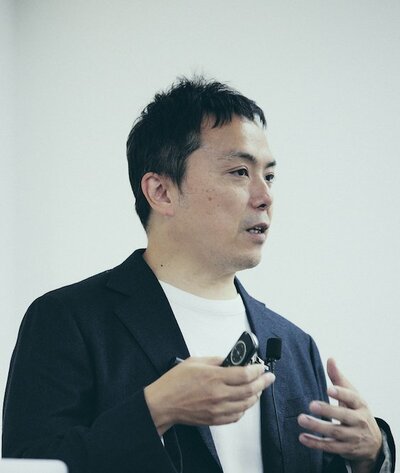 古賀史健(こが・ふみたけ)
古賀史健(こが・ふみたけ)1973年福岡県生まれ。九州産業大学芸術学部卒。メガネ店勤務、出版社勤務を経て1998年にライターとして独立。著書に『取材・執筆・推敲』のほか、31言語で翻訳され世界的ベストセラーとなった『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』(岸見一郎共著、以上ダイヤモンド社)、『古賀史健がまとめた糸井重里のこと。』(糸井重里共著、ほぼ日)、『20歳の自分に受けさせたい文章講義』(星海社)など。構成・ライティングに『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』(幡野広志著、ポプラ社)、『ミライの授業』(瀧本哲史著、講談社)、『ゼロ』(堀江貴文著、ダイヤモンド社)など。編著書の累計部数は1300万部を超える。2014年、ビジネス書ライターの地位向上に大きく寄与したとして、「ビジネス書大賞・審査員特別賞」受賞。翌2015年、「書くこと」に特化したライターズ・カンパニー、株式会社バトンズを設立。2021年7月よりライターのための学校「バトンズ・ライティング・カレッジ」を開校。
もともと日本語には句読点がなかった
卒業証書や賞状には句読点が用いられません。年賀状にも、本則としては用いられない。そして講談社や集英社の漫画でも、フキダシ内のことばは句読点なしで表記されます(小学館の漫画は句読点アリ)。
いったいなぜか?
もともと日本語に、句読点が存在しなかったからなのです。漢文の訓読用に訓点の一種として使われたり、蘭学の翻訳書で例外的に使われたりすることはあったものの、江戸期までの仮名文に句読点は使われていませんでした。意外と知られていないことですが、現在のような句読点が生まれ、一般化していったのは言文一致運動を経た明治後期になってからのことです。西洋からカンマ「,」やピリオド「.」を輸入した結果、急ごしらえでつくられたのが日本語の句読点なのです。
そんな歴史の浅さも関係しているのでしょう。日本語の句読点には、いまだ正書法(統一的な表記ルール)が確立されていません。たとえば、学術論文や理工系の文書ではしばしば「、」や「。」ではなく、カンマとピリオドが使われる。これはまったく誤用ではありません。テン、マル、カンマ、ピリオドの混在は許されています。事実、学校教科書においても、横組みで記述する場合(つまり算数、数学、社会、理科、音楽など)はカンマを読点としています。それほどにも日本語の句読点は未整備であり、よく言えば自由なのです。
読点のつけ方で、リズムはがらりと変わる
そんな「正解のなさ」を踏まえたうえで考えたいのが、読点「、」の打ち方です。
一般的に読点とは、「意味の区切り」と「リズムの区切り」のいずれかにおいて使われます。「意味の区切り」とは、たとえば次のような文です。
A わたしは、泣きながら彼がつくった料理を食べた。
B わたしは泣きながら、彼がつくった料理を食べた。
一読して、Aの文で──どういう状況なのかはともかく──泣いているのは「彼」です。他方、Bの文では「わたし」が、泣いている。こうした「意味の区切り」としての読点は、ぼんやりとした正解(らしきもの)もあり、用法もわかりやすいですよね。
これに対してわかりづらいのが、「リズムの区切り」です。
文をどこで区切ると読みやすいのか。あるいは、どこで区切ると気持ちいいのか。ここについては、いよいよ明解な表記ルールが存在せず、書き手の感覚に委ねられています。小説家のなかでも、読点を多用する作家と、読点を極力控える作家はそれぞれいるし、どちらが正解というわけでもありません(ちなみにぼく自身は、読点を多用するほうです)。注意点があるとすれば、原稿全体での統一感でしょう。たとえば、ひとつの原稿の前半と後半で読点のリズムが違っていたら、気持ち悪いし読みづらい。読点は、楽譜でいえば休符であり、水泳でいえば息継ぎ。自分の書いた文章をそのたびごとに音読しながら、自分にとっての「気持ちのいいリズム」を探っていきましょう。次回は句読点とともに大切な「語尾と文末表現」について説明します。
(続く)



