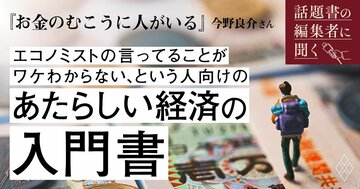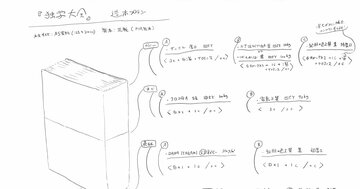本作りで欠かせない工程が「装丁」である。
カバーをデザインすることは、本の顔を作ることでもある。
『あの日、選ばれなかった君へ 新しい自分に生まれ変わるための7枚のメモ』(阿部広太郎)の装丁を行ったのは、人気デザイナー・鈴木千佳子。
彼女は何を考えて、書店で手に取ってもらえる本を目指したのか?
著者の阿部広太郎との対談で浮かび上がってきたものとは?
(取材・ダイヤモンド社/亀井史夫 撮影・小島真也)
 装丁家の鈴木千佳子さん(左)とコピーライターの阿部広太郎さん
装丁家の鈴木千佳子さん(左)とコピーライターの阿部広太郎さん
阿部さんの言葉に、装飾はあまり必要ないと思った
阿部広太郎(以下、阿部) 最初の打ち合わせのときに、もしかしたら本文はイラストを入れるかもと鈴木さんがおっしゃっていた記憶があるんです。今回は本当に写真もなければ図版もない、ビジネス書としては珍しいかたちになったと思うんですけど、もうここは文章のみで進んだほうがいいんじゃないかと最終的に思われたんですか?
鈴木千佳子(以下、鈴木) 一つは阿部さんの言葉の真っ直ぐさをそのまま伝えたいので、できるだけ装飾的なものがないほうがいいなというのはありました。阿部さんの人柄ごと伝わってくるような言葉なので、絵を入れてしまうとどこかそれが嘘っぽくなってしまう。それがいい嘘になってくれればいいのですが、今回のこの本の場合はむしろないほうがいいと思いました。入口として、装丁のほうにはイラストがあったほうがいいと思ったのですが、あくまでも導入になるものとしての、装飾的なものであり、絵と言えるのか言えないのかっていうぐらいのことになっていたほうがいいと思いました。どうしても絵が入ると言葉と紐づき過ぎてしまう側面があるので。あと、読んでいて、阿部さんの断片断片の光景が浮かぶので、逆にそれを限定するようなビジュアルは必要ないという感じもありました。
阿部 いやぁ、そういうふうに言っていただけると嬉しいですね。改行をするとしても、リズムが生まれやすい改行であったり、その辺りはすごく意識しました。よく、文章中で1文字だけ残して改行せざるを得ない状況ってあると思うんですけど、僕は異様にそれが気になってしまって(笑)。行が変わるんだったら、この1文字だけじゃなくて、少なくとも数文字あってほしいから言葉選びを調整したりして……こんなことを気にしているの自分だけかもなと思いながらも、最後までいろいろ粘りながらやっていたんです。読んでいてリズムが目に見えるようだと言っていただけるのは嬉しいです。
鈴木 それから、選んでると言っても、その時点で見えてる範囲で選んでるということにしか過ぎないので、結局、選ばれない可能性の大きさのほうに目を向けたほうがやっぱりいいのかなと思ったりしました。
阿部 僕が本当に思うのは、選ばれようとしたことにこそ意味があるんじゃないかと、コンペだったり試験だったり、その場に身を置こうとしたことに意味があるなと思うようにしているんです……今回、タイトルに反応してくださる方もいて、「選ばれなかったってことにドキッとしました」みたいな人も多いんです。でも、この本で伝えたいのは、過去に選ばれなかったことがあったことで、その中に、現在の自分の行くべき道があったり、ヒントや道しるべが見つかったりするということなんです。第1章「卒業アルバムの君は『ひとりぼっち』だった」では10代の頃に、卒業アルバムがきっかけで自分がどこにもいないと孤独感に苛まれたエピソードを書いているんですけど、過去と向き合いながら構成した今回の本はある意味、本当に卒業アルバムのようだなと感じていたんです。額縁というキーワードも……つながっていると感じましたね。
鈴木 ああ、確かにそうですね。
目指すは対話型クリエイター
阿部 鈴木さん的には、一番印象に残った章はどこですか?
鈴木 私が印象に残ったのは、第5章「この仕事『向いてないかも』と言われたら」から第6章「『選ぶ側』に回ってしまったら」で、対話型に切り替えたという話のところです。とても自分とも重なっていて。私が1案しか出さないというのもちょっと似たところがあります。対話型に行き着くのって、一見簡単そうですが、きっといろいろ葛藤があったのだろうなと感じて、一番印象に残りました。
阿部 確かに、下手な鉄砲数撃ちゃ当たるじゃないですけど、これまで量に救われてきたんです。けど、量に溺れそうになることもありました。案出しだけを目的にずっとやっていると、本当に呑み込まれてしまうというか、健全じゃないようにも感じることがありました。今は、量産型ではなく対話型として、ディスカッションをしながら、これがいいんじゃないですかと相手にそっと言葉を差し出せるような人でありたいなと思っています。もしかしたら、作り手の人はすべからくそういう道を辿るのかもしれません。最初は量に揉まれて、そして、自分の中でこうすればいいんだという手法を獲得していくのかもしれませんよね。
鈴木 そうですね。さっきの話に戻ってしまうのですが、なんで1案しか出さないのかというと、私自身、なるべく細かいニュアンスを最初の打ち合わせで聞くようにはしてるんです。何案も出すというのは結局、その最初にやるべき対話をデザインを通じて対話してる状態なんだなって私は考えるんです。何案も出して、例えば「こことこのあいだがいいな」といったやりとりも、それも一つの対話の方法だと思うんですけど、作りながら対話するよりも、最初に必要なことをちゃんと真っさらな状態で対話した上で出る答えって、意外とそんなにたくさんはない。私が決めつけてる側面もあるんですけど、実は見てくださる著者の方や編集者の方も、「いや、絶対これだね」というふうに自然と1個に決められるのがいいなと思って。そういう自分の制作のあり方と重なるところがあったので、すごく印象に残ってます。