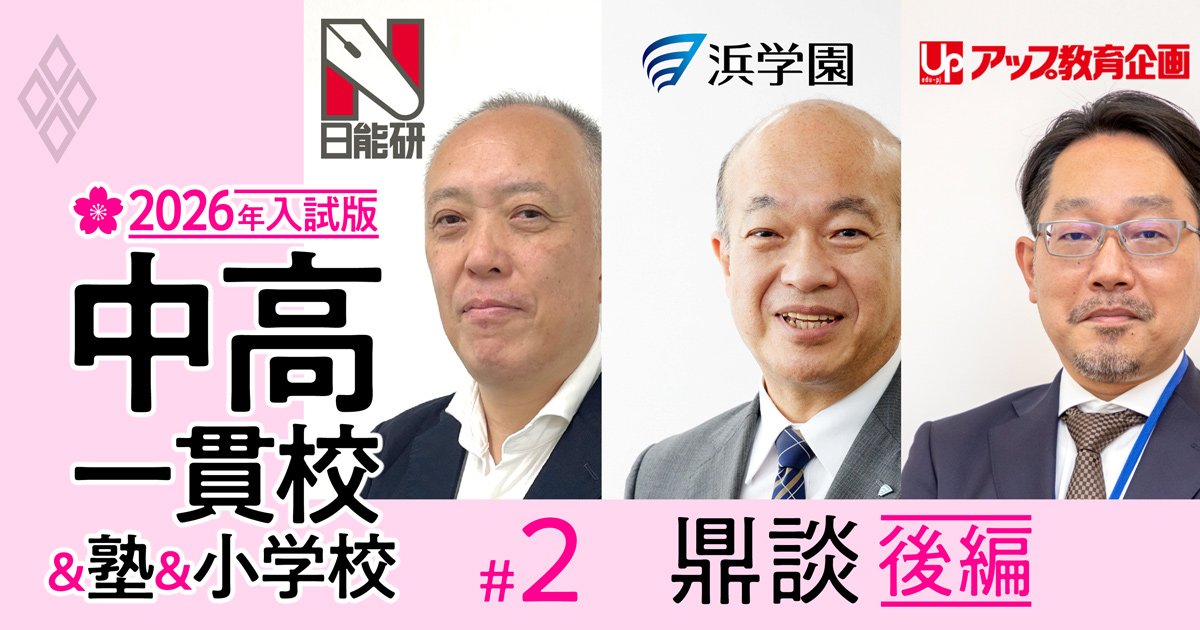「変化を嫌う人」の深層心理に潜む
4つの要因とは?
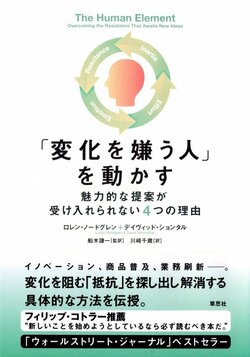 『「変化を嫌う人」を動かす -魅力的な提案が受け入れられない4つの理由』ロレン・ノードグレン/デイヴィッド・ションタル 著、船木 謙一 監訳、川崎千歳 訳、草思社、2200円(税込)※翻訳者・川崎氏の「崎」は、正式には「たつさき」
『「変化を嫌う人」を動かす -魅力的な提案が受け入れられない4つの理由』ロレン・ノードグレン/デイヴィッド・ションタル 著、船木 謙一 監訳、川崎千歳 訳、草思社、2200円(税込)※翻訳者・川崎氏の「崎」は、正式には「たつさき」
自社で開発した新商品やサービスが、たとえそれがきわめて画期的で確実に人々の生活を豊かにするものであったとしても、市場で初めから評価されることは多くない。新機能が急進的で、これまでになかったものであるほど、すんなりと消費者に受け入れられにくいのが常だ。
また、市場投入以前に、アイデアや企画書の段階で、上司や上層部の「抵抗」に遭い、開発のゴーサインすら出ないこともある。
このような「抵抗」には、「惰性」「労力」「感情」「心理的反発」の4つの要因があると、著者らは分析している。
惰性と労力はわかりやすいだろう。そして、この2つが実際のケースとしてかなり多いと思われる。惰性は「よく知っている、慣れた行動を変えたくない」、労力は「変えるための労力をかけたくない(面倒くさい)」といった心理だ。
では、この2つに対抗し、斬新なアイデアを受け入れてもらうには、どんな取り組みが必要なのか。
惰性については、本書では「何度も提案を繰り返す」「アイデアを小出しにする」といった対策が紹介されている。労力は、工夫を重ねて「変えるための労力を減らす」のが最も手っ取り早い方法だという。
これらよりも若干複雑なのが、残りの2つ、感情と心理的反発である。
感情による抵抗は、理屈ではないので少々厄介だ。著者らは、わかりやすい例として、1926年に米国で初めて「ケーキミックス」が発売されたときの消費者の反応を紹介している。