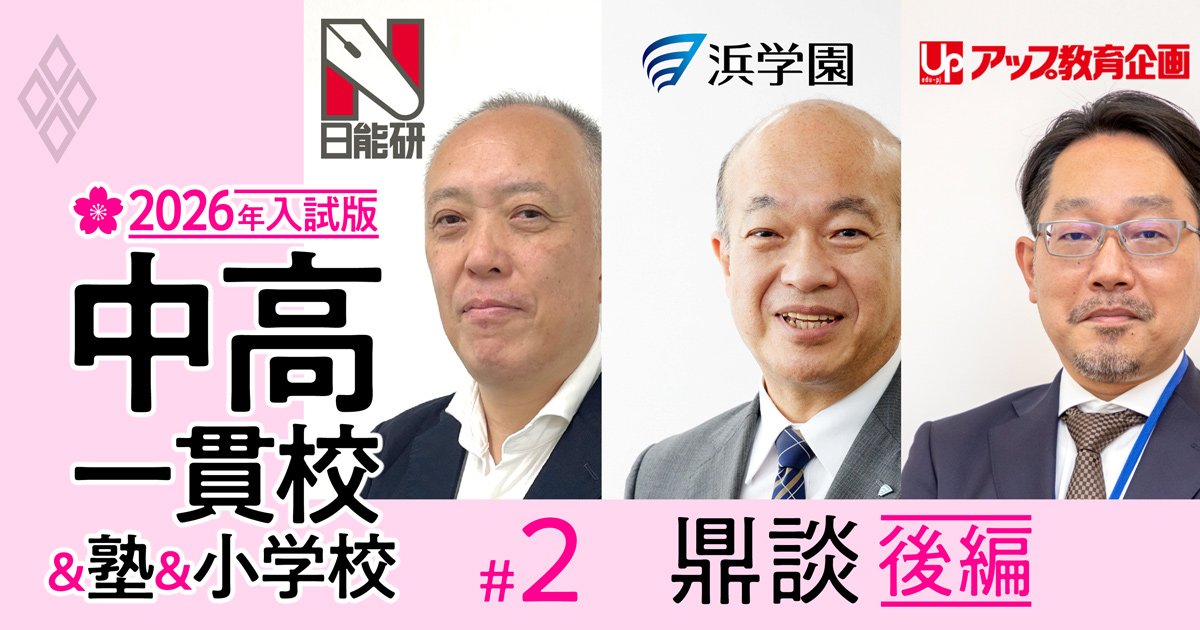米国のケーキミックスが
「あえて面倒な仕様」になったワケ
言わずもがなだが、ケーキミックスとは、ケーキやクッキーの材料となる小麦粉などを混ぜたもの。そのまま焼けば、短時間、手間要らずで目的のスイーツが出来上がるという、当時としては画期的な商品として売り出された。
しかし、発売当初の反応は今ひとつ。人気商品になるまでには時間がかかった。なぜか。当時の人々にとって、ケーキを焼くというのは特別な行為だったからだという。
自分のために焼くことは少なく、大切な人へのもてなしとして焼くことがほとんどだった。したがって、「丁寧に時間をかけて焼くこと」が心遣いを表すことになる。ケーキミックスで「ちゃっちゃ」と作るのでは、もてなしの相手に失礼と感じられたのだ。
理屈の上では、安く、効率的にケーキ作りができるケーキミックスは、きわめて利便性の高い、おトクな商品に違いない。だが、もてなしという感情がそれに抵抗を示した。
こうした事態に対し、販売元のゼネラル・ミルズは、心理学者のアーネスト・ディヒターを雇い、消費者心理の分析をもとに商品を改良することにした。
両者はこの際、ケーキミックスを使ったケーキ作りの手順を、あえて「非効率化」した。ミックスを使ってケーキを焼く際に「泡立てた卵を加える」という工程を加えたのだ。
これだけのことで、ユーザーは、商品の利便性を損なわないまま、「自分でケーキを焼いておもてなしをした」という達成感、満足感を得られるようになり、商品をこぞって買うようになったそうだ。感情を(良い意味で)うまく誘導することに成功したのだ。
心理的反発は、冒頭でも触れたが、「強制されるとかえって反発したくなる」心理だ。子どもの頃に親から「勉強しろ」としつこく言われ、反抗してサボってばかりいた、というのが心理的反発の典型だ。
本書で例示されているのは、1980年代に米国の各州で自動車のシートベルト義務化の法整備がなされたときのことだ。
当時、シートベルトをした方が安全だという認識が広まっていたのにもかかわらず、人々は反発し、シートベルトを常時着用している米国人は1986年時点で17%にとどまっていたという。
中には車からシートベルトを切断したり、義務化に反対して訴訟を起こしたりする人もいた。
変化に合理性があっても、それを強要されることを、少なくとも米国人は嫌ったのである。心理的反発は、変化そのものに対する抵抗というよりも、「変化させられること」への抵抗といえるのだ。