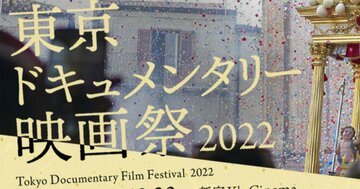「多様性」で知られるバービーの風刺に満ちた作品
実際のところ、『バービー』は社会問題への風刺に満ちた作品である。もっとはっきり言えば、フェミニズムをベースとして、資本主義の行き詰まりを指摘し、男性中心社会あるいは白人至上主義からの脱却を訴えている。それらをコミカルにコーティングし、随所にクスッと笑える批評を忍ばせている。
バービー人形に関心を持ったことがない人にはあまり知られていないことかもしれないが、米国でバービーといえば多様性への取り組みが有名だ。
バービー人形のバリエーションは、肌や髪の色あるいは体形がさまざまであるだけではなく、医師やサッカー選手、宇宙飛行士、消防士などさまざまな職業のバービーが存在する。また近年では車椅子のバービーやダウン症のバービーも登場した。
これらの“多様性バービー”は映画にも登場する(ちなみに、バーベンハイマー炎上の背景には、「多様性やポリコレに配慮してきたあのバービーが原爆の被害には無関心だなんて」という文脈もある)。
バービーがこのように進化したのは、かつてのバービー人形が、画一的な美を少女たちに押し付けているという批判があったからである。さまざまな職業のバービーがいるのは、「消防士やサッカー選手、医師や大統領は男性の職業」「看護師やシッターは女性の職業」といった、子どもたちが社会から刷り込まれがちな性的役割分担から少女を解放する目的がある。
このような経緯から、米国では公開前から『バービー』は当然ポリコレ的であり、フェミニズムをベースとした映画であると受け止められ、それを期待する層が見に行っている。一方で保守派による批判もある。
では、日本の場合はどうだろうか。