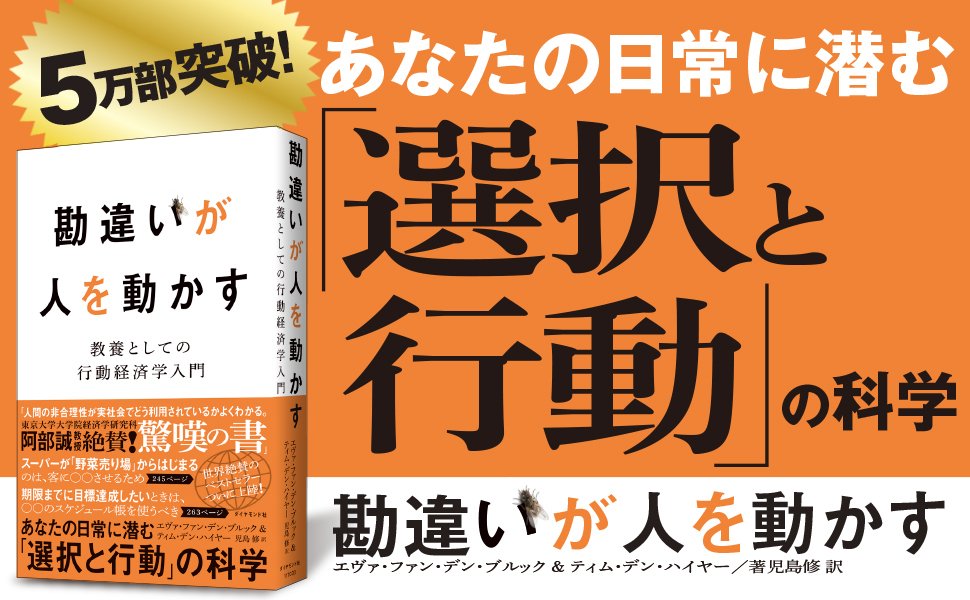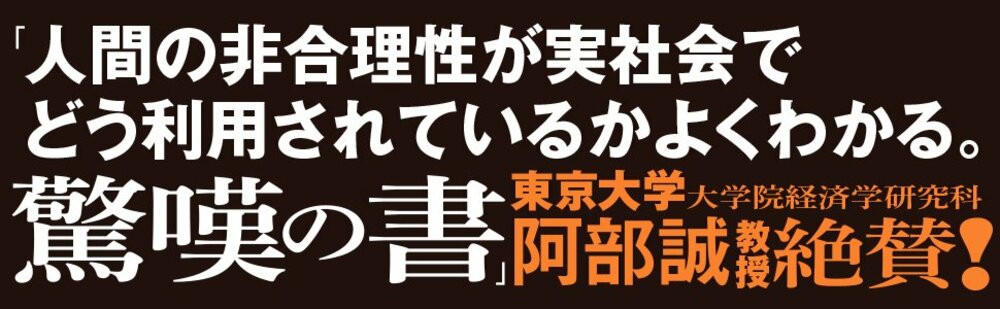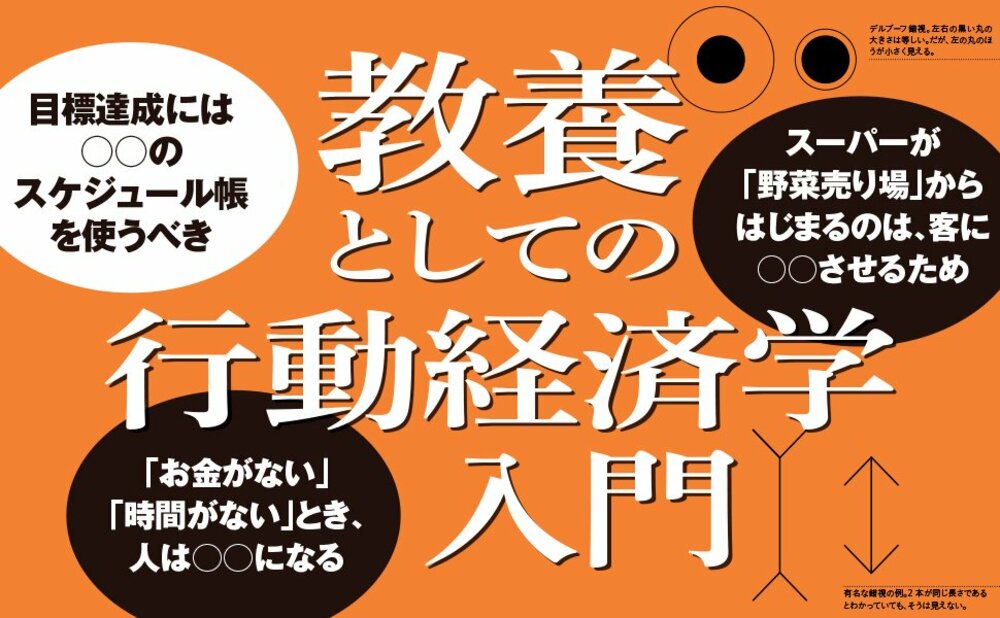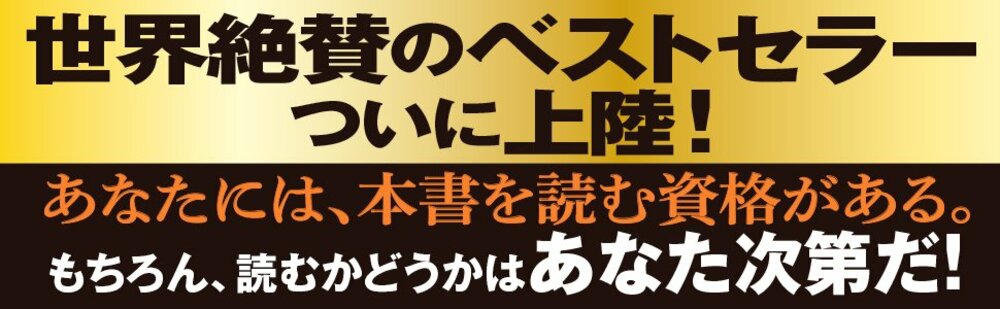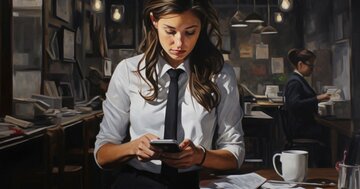人を動かすには「論理的な正しさ」も「情熱的な訴え」も必要ない。「認知バイアス」によって、私たちは気がつかないうちに、誰かに動かされている。人間が生得的に持っているこの心理的な傾向をビジネスや公共分野に活かそうとする動きはますます活発になっている。認知バイアスを利用した「行動経済学」について理解を深めることは、様々なリスクから自分の身を守るためにも、うまく相手を動かして目的を達成するためにも、非常に重要だ。本連載では、『勘違いが人を動かす──教養としての行動経済学入門』から私たちの生活を取り囲む様々な認知バイアスについて豊富な事例と科学的知見を紹介しながら、有益なアドバイスを提供する。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
ブランドのプラシーボ効果
ブランドは、ある意味で究極のプラシーボだ。
銘柄を隠して飲み比べをするブラインドテストでは、「一番よく売れているコーラ」が必ずしも一番美味しいと評価されるわけではないことがわかる。
だが、銘柄を隠さないでおくと、ベストセラーのコーラが一番美味しいと答える人の数が跳ね上がる。
ビールの愛飲者も、ブラインドテストで一番好きな銘柄を当てられないことが多い。
とりわけ当てはまるのは、高級オーディオの分野だ。純金のプラグやスピーカーケーブルが付属している最上級のオーディオは、新車が買えるほどの値段になる。
そしてオーディオマニアは、「私はどんな音の違いでも聞き分けられる」と自信たっぷりに言う。使用する電力を再生可能エネルギーに替えるだけで、音が違って聞こえると言い張る人すらいる。
お察しの通り、ブラインドテストでは誰もケーブルによる音の違いを聞き分けられなかった。レジ付近で売られている5ユーロのケーブルとも区別がつかなかったのだ。
とはいえ、オーディオマニアが最高級のステレオセットで音楽を聴くときに無上の喜びを感じるのは事実だ。
もし購入できる余裕があって、心から満足できるのなら、それでよいのではないだろうか。
(ただし筆者は、高額のローンを組んでまでバカ高いステレオセットを買うのはあまりお勧めしない。納得できないなら、まずはブラインドテストをしてみてほしい)
プラシーボは、日常生活でうまく活用することもできる。もちろん、医者に処方してもらう必要などない。
有名シェフも、プラシーボ効果をよく理解している。客がレストランに足を踏み入れると、店内はスタイリッシュに飾り付けられ、チベットの僧院に触発されたという極小サイズの前菜が目の前に差し出される。
最初の一口を味わう前から、客はもうすっかり期待している─それが格別に深くて絶妙な味わいの、びっくりするほど美味しい料理だということを。
グルメサイトの高評価を巡ってしのぎを削るシェフたちは、あの手この手のトリックを客に仕掛けてくる。
あるレストランは、「当店では、オイスター料理がさらに美味しくなるような特別な音楽を流しています」と宣伝する。
客は「そんな馬鹿な」と思いつつ、やっぱりその音楽を聞きながら食べるオイスターは一段と美味しいような気がしてしまう。
ノーブランドのワインを洒落たボトルから注ぐと、安物のボトルから注いだ場合に比べて、美味しいと感じやすくなる。
高価なワインは食事の楽しさを高めるという脳科学の研究もある。
この効果は「自分を納得させる」以上の働きをする。
インセンティブは偽りだが、経験は本物なのだ。
ニンジンをファストフードの包装紙で包んで与えると、子どもは「いつもより美味しい」と言うだろう。
(本記事は『勘違いが人を動かす──教養としての行動経済学入門』から一部を抜粋・改変したものです)