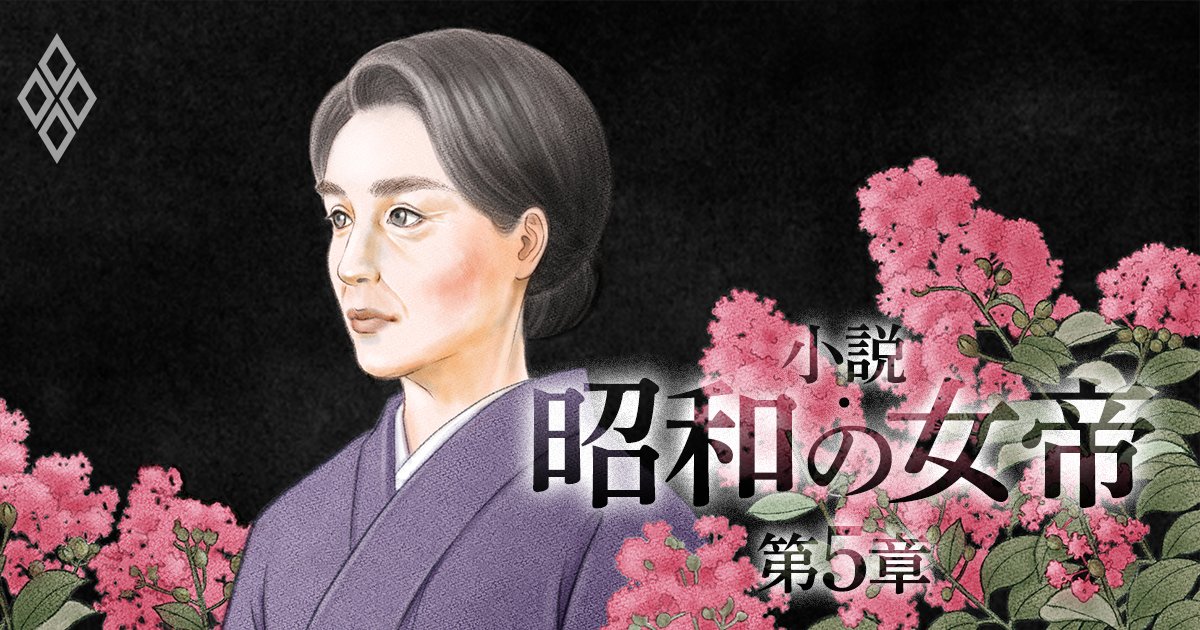「個人的には起業するのが遅くなってしまったという思いがある反面、『大きな事業、大きな会社を作りたい』という目標に向けて、焦りよりも世の中の仕組みを活かしながらやっていきたいという思いが前提にありました」(西條氏)
そもそも業績が伸び悩んでいるような上場IT企業であっても、「やり方を少し変えることによって業績を伸ばせるのではないか」という考えが以前からあったという西條氏。エキサイトTOBの話が舞い込んできたのは、まさにそんなタイミングだった。
売上が50億円以上あるならなんとか事業を盛り返せるのではないか──。直感的にそう考えた一方で、「見切り発車」の部分もあったという。
「2004年に上場して、ピーク時には売り上げが130億円を超えていました。ただそこから低迷し、売上は半分にも満たない。前年比で10%落ちているような状況で、証券用語で言うところの『落ちてくるナイフをつかむ』ような状況でした。この売り上げの下降を食い止めることができるのか。正直、そこは不安もありました」(西條氏)
インサイダー取引を未然に防止する目的などから、TOBにあたって情報が限られていたことも大きい。XTech側の担当者は⻄條氏のみ、エキサイト側も基本的には社⻑と経営企画担当者の2人だけだった。
公開資料や社内の状況をまとめたドキュメントなどはあれど、実際の様子は2人から口頭で聞く内容が中心。現場で働くメンバーにヒアリングすることもできなかった。
ただ、勝算がなかったわけではない。当時のエキサイトは「メディア事業」「課金事業」「ブロードバンド事業」の3つのセグメントから構成されていた。事業家や投資家としてさまざまなITビジネスを見てきた西條氏としては、「(売上の規模や事業構造的に)少なくとも10%程度の営業利益が出ないとおかしいビジネスモデル」だという見立てがあった。既存事業に手を入れるだけでも、十分に黒字化できる可能性があると考えたわけだ。
当時のエキサイトの組織体制も西條氏の目には魅力的に映った。約200人の社員のうち、4割程度はエンジニア。エンジニアの獲得競争が激しい時代において、80人ものエンジニアを採用することは簡単ではない。
しかも当時のエキサイトには“チームになった状態のエンジニア”が80人在籍しており、事業が縮小傾向にあったとは言え、そのメンバーを雇用するだけのキャッシュを生み出す事業も存在していた。