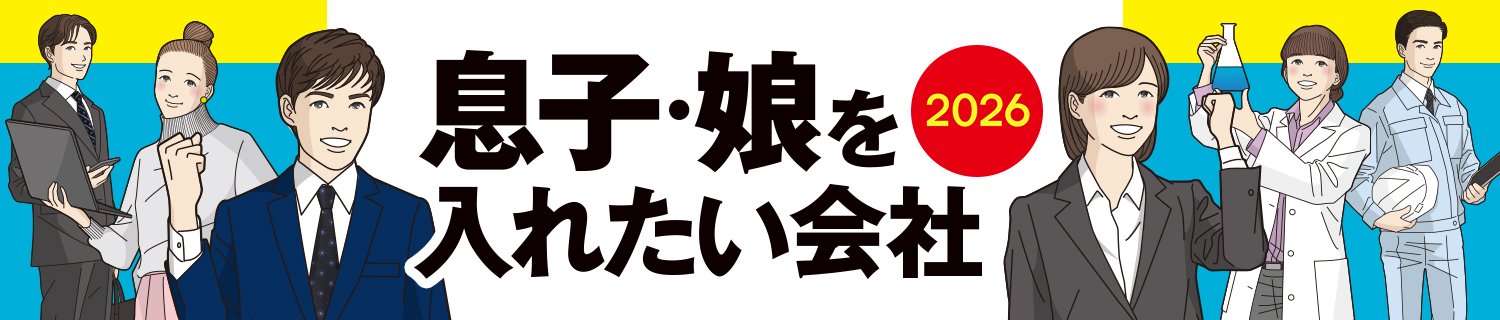7割以上の学生が参加!
変わるインターンシップ
一方で、外資系企業やベンチャー企業は上記の就活スケジュールに縛られず、早くから優秀な学生にアプローチしています。ほぼ8割の学生が選考解禁日にすでに内定を得ている状況は、企業によって就活スケジュールが異なっているために起こっていると言えるでしょう。労働力人口減により人材不足が深刻な今、「少しでも多くの学生と早期接点を作りたい」「自社を認知してもらいたい」という企業の思いは切実です。そこで企業側が進めてきた取り組みの一つに、インターンシップがあります。
保護者世代の就活において、インターンシップに参加した人はごく一部で、一般的ではありませんでした。インターンシップが浸透してきたのは、ここ10年の変化が大きく、実施状況を経年で見ると、14年卒向けの実施率は39.0%だったのに対し、20年卒向けでは89.4%まで広がっています。23年卒ではコロナ禍の影響で減少に転じて70.2%ですが、多くの企業がインターンシップを行っていることがわかります。
学生側の参加状況を見てみると、14年卒では23.9%だった参加率が、23年卒では75%になっています。夏や秋、冬など長期休暇を中心に実施されるインターンシップへの参加は、就活において、企業を知る重要なプロセスの一つになっています。
さらにインターンシップのあり方は、25年卒を機に大きく変化しています。もともとインターンシップは、企業と学生が相互理解を深めるためのキャリア教育の場という位置づけで始まりました。企業理解を早い段階から深めたい学生と、優秀な学生に自社を知って欲しい企業。双方のニーズがマッチし広がってきたものの、学業とキャリア形成(就活)の両立という観点で、学生の準備・選考・参加の負荷が大きすぎるのではないかとの課題も指摘されてきました。
そこで、学業の機会を損なわない取り組みの実施を進めようと、2022年6月に文部科学省、厚生労働省、経済産業省の3省合意により「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」が改正されました。25卒以降の学生を対象とし、2023年の夏以降に実施される、インターンシップをはじめとした大学生などの「キャリア形成支援に係る取り組み」が4つに類型化されることになりました。
5日以上の開催で、就業体験が半分以上を占めるなど、一定の要件を満たしたもののみを「インターンシップ」(タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ、タイプ4:高度専門型インターンシップ)と呼称し、企業はそれらに参加した学生の情報を採用選考に利用してもよいことになりました。