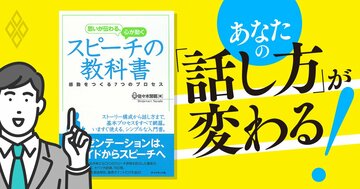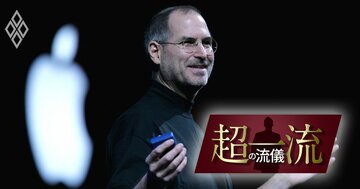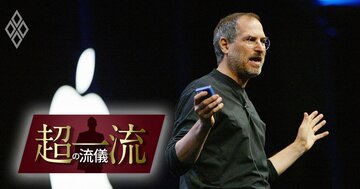日常的に蓄えた、さまざまな言葉やデータなどの知識やメディアなどで得た情報を、ほんの少し手を加えて話の中に取り込んでいます。
知識とは、それ自体、あれこれ情報を取り込んだ引用の集合体のような側面があります。その断片を切り取って、また別の話の流れに組み込んでやることで、新たなストーリーになっていきます。
名言もあれば失敗談やちょっとしたエピソード、あらゆる数字やデータも引用できます。簡単なところでは「誰かがこんなふうに言ったんだけどさ」というのも引用ですね。
引用は、自分が伝えたいことや主張を補完し、拡張し、押し上げてくれる役割を果たすもの。話が引用によって展開され、進化して、どんどんおもしろくなって、人を引き込んでいってくれます。
引用を自分の名言に変えたスティーブ・ジョブズ
引用の名手といえば、スティーブ・ジョブズです。
ジョブズは、ご存じの通りアップル社を創設しiPhoneやiPadなどを生み出した人物ですが、特に、スタンフォード大学の卒業式のスピーチ「ハングリーであれ、愚かであれ」の名言は有名です。
これは、まるでジョブズの名言のように独り歩きしていますが、実はジョブズが考えた言葉ではありません。
「ホールアース・カタログ」という雑誌の裏表紙に書かれていた言葉を、スタンフォードでのスピーチ原稿で引用したものでした。
スピーチの中でその雑誌の魅力について語り、掲載された荒野の一本道の写真と、そこ書かれていた「Stay hungry, stay foolish(ハングリーであれ、愚かであれ)」の言葉を、こんなふうに説明していました。
「(雑誌ホールアース・カタログの)最終版の裏表紙は朝の田舎道の写真で、冒険好きがヒッチハイクをしていそうな場面でした。その下にこんな言葉があります。
『ハングリーであれ、愚かであれ』。これは、(編集長の)スチュアートたちが活動を終えるに当たっての別れの言葉。私は常にこの言葉のようにありたいと願ってきました。そして今、皆が卒業して新たに歩みを始めるに当たり、皆にもそうあってほしいと思います。
ハングリーであれ、愚かであれ」