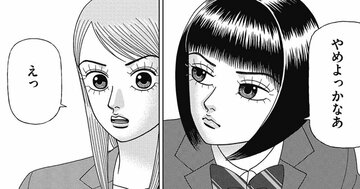Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
世界ランキングトップの大学に通う学生の男女比がほぼ半数である一方、日本が誇る東京大学に通う女子率は未だに低く、20.1%(2022年)でしかない。女人禁制だった明治時代の東大を舞台に描かれた小説『三四郎』(夏目漱石)から見た、東大における女子の扱いとは。※本稿は、矢口祐人『なぜ東大は男だらけなのか』(集英社新書)の一部を抜粋・編集したものです。
東大生が主人公の『三四郎』に
勉学の話はあまり出てこない
夏目漱石の『三四郎』は東大を舞台にした小説である。1908年に『朝日新聞』に連載され、翌年、書籍として刊行された。漱石は1907年まで東大で英文学を教えていたから、『三四郎』に登場する東大生、本郷キャンパスとその周辺の描写は当時の様子をかなり細かく反映していた。
『三四郎』では東大に入学するために九州から上京してきた23歳の青年、小川三四郎の学生生活の日々が描かれる。三四郎は本郷キャンパスの近くに住み、歩いて大学へ通う。とはいえ、その学生生活に勉学の話はあまり出てこない。
せっかく入学したのに、三四郎は大学の授業がとても退屈だと思っている。教授たちは授業に遅れてくるし(学期の1週目は教室に来ることさえしない!)、教壇に立って一方的に難しい話ばかりをしている。
三四郎は講義を聞きながら、だいたい他のことを考えている。そのうち「神経が鈍くなって、気が遠く」なる。図書館にはよく行くが、そこでもしょっちゅう物思いにふけっていて、勉強に集中することはほとんどない。
三四郎の頭にあるのは勉強のことでも、将来のことでもなく、東大のキャンパスで知り合った美しい女性、里見美禰子のことである。彼はいつも美禰子について考えている。