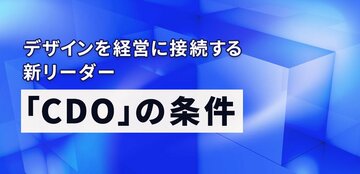ビジョンと実際を行き来しながらプロダクトに落とし込む
しかし、優れたアイデアだけではプロダクトは成立しない。プロダクトマネジメントに際して、「コンセプトの純度を保ちながらビジネスとして成立させる」という難題にどう挑むのか。本間氏はそれを「核にある強いエゴや偏愛にやすりをかけていく」と表現する。
「僕らの会社は、理念に強く共感した者の集まりです。だからこそ、ツッコミどころが多い。『この壁、かっこいいけど自然には優しくない』とか『SANUっぽいけど、ユーザーの本質を捉えていない』など、情熱から生まれたものに対して冷静な視点をぶつけていきます。チーム単位でもこういった会話は日常的だし、けんかに見えるほどの言い合いをすることもあります。僕らはこの対立を『ゆらぎ』と呼んで大事にしています」(本間氏)
やすりをかける行為を「妥協」ではなく、ブラッシュアップの機会にするためには、デザイナーが先導して「初手からユニークなビジュアルを示していく」ことも有効だ。成澤氏は、「メルカリのプロダクト開発は超デザインドリブンです。『カード決済を作る』『銀行口座の接続を作る』などの目的が決まれば、ドキュメントは一切作らず、いきなりデザイナーがUIを書き起こす。それを、ドメインのスペシャリストを加えたチームで多面的に検討しながら、プロダクトを垂直に立ち上げていくのです」と語る。
「裏付けのないドリームだけじゃモノにならないし、エキスパートの視点でオペレーションを磨くだけでは魅力がない。ビジョンとビジネスの両側からサンドイッチして、その真ん中にプロダクトをピン留めした状態をつくっていくイメージですね」と田川氏。ビジョンを軸に、異なる要素をつなぎ合あわせていく動きは、まさにデザイナーが得意とするものといえるだろう。
では、プロダクトをローンチした後のグロース期、いわゆる「1→10」フェーズではどうか。ここでマーケットの反応に気を取られて方向感覚を見失うとイノベーションが失速する。「ガラパゴス化」に陥ることなくマーケットにフィットさせるには何が必要だろうか。
成澤氏が「これも、経営陣から教え込まれたことを、自分の体に染み込ませて実践していることなのですが」と前置きをしながら強調したのが、「足元から塗り込む」ことの重要性だ。
「大玉を打ち上げて、自分たちのドリームを高く掲げるだけではマーケットにフィットしません。初期モデルをリリースした直後はチームのテンションも高いので、立て続けに『次なる大玉』を出そうとしがちですが、ここでいったん踏みとどまるのがすごく大事。プログラムの設計を見直し、ユーザーの反応に真摯に向き合うと、意図とずれている部分やボトルネックが必ず見つかります。まずはそれらをしっかり塗り込むことで『本来の仮説』に近づけていく。これを地道に数カ月続けていると、突然ボンッと跳ねる日が来るんです」(成澤氏)