各シナリオにおける実質GDPへの影響を大和総研のマクロモデルを用いて試算すると、2040年時点で「PB:0%」シナリオではベンチマーク比▲4.0~▲1.0%、「PB:▲3%」シナリオでは同▲5.6~▲2.9%、「PB:▲5%」シナリオでは同▲6.5~▲3.9%となった(図表7・10)。リスクプレミアムの上昇が実体経済に大きな悪影響を及ぼす可能性が示唆される。
日本経済に負の影響が大きい
長期金利の上昇リスクに警戒が必要
実質GDPの内訳への影響としては、個人消費への影響は比較的小さいと予想される。金利上昇の影響は、ローンを組んで購入することの多い自動車など一部の費目に限られるためだ。
長期金利の上昇は、企業収益の減少や景気の悪化を通じて、労働需要を減少させる。結果として、実質賃金と雇用者数の双方に減少圧力がかかることから、実質雇用者報酬を下押しする効果を持つ。半面、家計は金融負債よりも資産を多く持つことから、長期金利の上昇は純利息収入を押し上げ、実質可処分所得の減少を緩和する。
一方、設備投資への影響は大きいと考えられる。長期金利の上昇によって企業の資金調達環境が悪化することに加え、景気の悪化による企業収益の減少も設備投資を下押しする方向に作用するためだ。
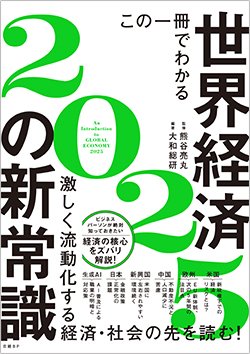 『この一冊でわかる 世界経済の新常識2025』(日経BP)
『この一冊でわかる 世界経済の新常識2025』(日経BP)熊谷亮丸 監修
大和総研のマクロモデルでは十分に反映されていないものの、設備投資の大幅な減少は資本ストックの増加を抑制することで、潜在成長率を下押しするとみられる。これは自然利子率の低下を招き、金融環境を引き締め的にすることで設備投資をさらに減少させるだろう。
「設備投資の二面性」(需要と供給の双方に影響するという設備投資の性質)を考慮すれば、長期金利の上昇は需要の抑制だけでなく、供給能力の低下という経路でも日本経済に大きな負の影響を与える恐れがある。
以上のように、今後は日銀が国債保有を減少させていくことで、海外投資家の国債保有割合が上昇する可能性が高く、長期金利が上昇するリスクには警戒が必要だ。
日銀が金融政策の正常化を進める中で金利上昇リスクを抑制するためにも、政府は財政健全化を着実に進め、国債発行の増加を抑制することが重要である。







