そこからが、欽ちゃんの本領発揮である。一般の素人は、もちろんタイトルコールの経験などまったくない。だから声がつい小さくなってしまったり、ちゃんと声が出たとしても「欽ちゃんのドーン!」とタイトルを間違えてしまったりする。すると欽ちゃんはすかさず「違うよー、もう1回お願い」と繰り返しやらせる。だが今度は叫ぶことや正しい番組タイトルに気をとられるあまり、同時に右手を突き上げるポーズもするように言われていたのをすっかり忘れてしまい、また繰り返させられる。
芸能界の専門用語「ウケる」を
一般的な語彙にしたのも欽ちゃん
もうお気づきだろう。ここでの素人は、コント55号の二郎さんの役回りになっている。欽ちゃんの矢継ぎ早のツッコミに翻弄され追い詰められるなかで、失敗を繰り返す。しかも二郎さんのようなプロのコメディアンではないので、返せる技術があるわけではない。
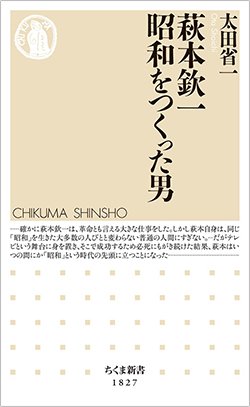 『萩本欽一 昭和をつくった男』(筑摩書房)
『萩本欽一 昭和をつくった男』(筑摩書房)太田省一 著
だがそれこそが、萩本欽一の狙いだった。「ひとは一度に3つのことをやることはできない」というのが萩本の持論だ。ここでは、右手を突き上げながら大きな声で、正確な番組名を叫ぶという3つのこと。突然振られるとプロでも難しいことであり、素人であればなおさらだ。そこに誰も予想しなかったような笑いが生まれる。
プロの芸を見ることに慣れ切っていた視聴者にとって、このように素人が前面に出て笑いの主役になる番組は新鮮以外の何物でもなかった。初回の視聴率も17%を超えた。萩本は、電話でその数字を聞いたとき、涙声になり絶句したという(前掲『欽ちゃんつんのめり』201頁)。ここから、「欽ちゃん番組」の快進撃が始まる。
『欽ドン!』の影響力は、テレビバラエティ全般に対しても小さくなかった。意外性を求める演出は、素人主体ではないがアドリブの笑いを前面に押し出して成功したフジテレビ『オレたちひょうきん族』(1981年放送開始)にもつながっている。実際、三宅恵介ら『欽ドン!』のスタッフが『ひょうきん族』に携わっていた。
また、「ばかウケ」「ややウケ」「ドッチラケ」は流行語になった。いまでは普通に使われる「ウケる」という表現は、元々芸能界の専門用語。萩本欽一が、それを番組で使って一般的なボキャブラリーにしたのである。そんなところにも萩本の言語センス、『欽ドン!』という番組の当時の人気ぶりがうかがえる。







