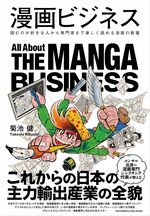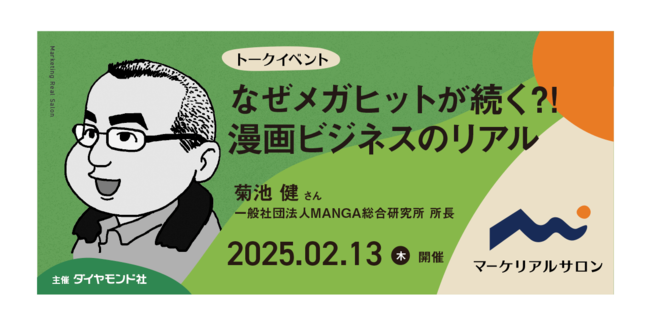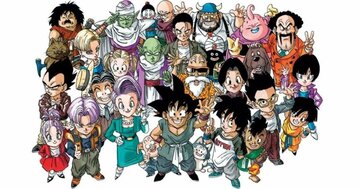「『鬼滅の刃』のようなメガヒットマンガを作るには、どうすればいいですか?」――そんな相談をよく受けるという、MANGA総合研究所所長の菊池健さん。実際、巨大な資本が漫画業界に流れ込み、世界的なヒットとなるマンガが次々と生まれています。そうした巨大かつ成長をつづけるマンガビジネスの実態をわかりやすく解説した菊池さんの著書『漫画ビジネス 読むのが好きな人から専門家まで楽しく読める漫画の教養』(クロスメディア・パブリッシング発行)から、いずれも世界的なヒットとなった『ドラゴンボール』と『鬼滅の刃』の売れ方にどのような違いがあったのか、近年の業界変化は大手出版社にどのような影響を与えたのか等、解説の一部をご紹介します。(書籍オンライン編集部)
 写真はイメージです (Photo: Adobe Stock)
写真はイメージです (Photo: Adobe Stock)
アニメは、映像配信ビジネスの影響で同時期に急成長し、その世界的な影響力は破壊的なものとなりました。『ドラゴンボール』は世界的に売れた作品ではありますが、日本から遠い中南米やヨーロッパまでブームが届くには、何年もの長い歳月がかかっています。
しかし、2020年前後に大ヒットした『鬼滅の刃』は、ネット配信の影響で、アニメとしては最初の放送時からいきなり世界中に配信され、世界同時に大ヒットしました。短い時間でヒットしていく映像ビジネスは、マンガ出版社にもライセンス収入というかたちでインパクトを与えます。
特に、これまでのアニメビジネスは、TV・映画放映後に、いわゆる「円盤」と呼ばれるDVDが、利益になるレベルで売れるかどうか、やってみないとわからない出たとこ勝負なところがありました。しかし、配信ビジネスの場合は配信される前に事前に映像が買い付けられるため、放映前に黒字化が確定するようなビジネスモデルなのです。これは、早々にアニメの放映継続を決められるなど、ビジネスの先を見通しやすくなる良い影響を与えました。
また、この配信の影響で、従来よりもはるかにスピーディーに、かつ広い範囲へ作品の認知が広がることから、海外における日本のマンガの売り上げも上がりました。これまでは日本に比べるとかなり小さい規模ではありましたが、いまやフランスの日本マンガは530億円(※1)、同じく米国では1500億円(※2)の市場と言われています。
グッズ、原画展などの各種イベントは、従来はあくまでマンガの付帯的なものとして、出版社にとってあくまで副次的な売り上げでしたが、最近は出版社自身が原画展やイベントを主催することも珍しくなくなりました。外部にグッズやイベントを委託する限り、3~10%ほどライセンス収入のみだったものが、自社内でグッズをつくると10倍以上の売り上げになることもあり、当然利益も上がります。ただし、書籍と違い、グッズ関係では、小売りが非常に強い専門部署をつくる必要が出てくるなど、ハイリスクハイリターンではありますが。
そうしたことから、集英社、講談社、KADOKAWAなど、デジタルによる収入はもちろん、映像化、国際化、版権の収入などの部署を強化するなどして、その売り上げの割合が大きくなっています。
2020年代に入り数年、2022年あたりから国内のスマホの使用時間の伸びも頭打ちになったという民間調査が出ました(※3)。
このタイミングと時を同じくして、電子コミック市場の伸びも1桁%台となり落ち着きを見せます。
マンガ市場の成長はこの伸びを持って踊り場を迎えるかという見方もあるかもしれません。
ただし、この時期大手出版社、わけても集英社、講談社、KADOKAWAなどのマンガの売り上げ比率が高い企業は依然成長を続けていました。これは、マンガ出版社の売り上げの中に、
・本以外のライセンス収入
・海外のマンガ販売
・イベント/グッズ販売 など
IPを活用したマンガ以外のビジネスの売り上げが大きく占めて行くビジネスの構造変化がありました。
マンガ出版社は、デジタルを含めた本を売るだけの存在から、生み出した作品をIPとして多くの周辺ビジネスに展開する存在へと進化したと言えそうです。
(『漫画ビジネス』第8章「IPビジネスとしてのマンガ」2項「近年のアニメ、マンガ産業のデジタル化による変化」を抜粋)
※2 JETRO「全米最大級のアニメイベント、Anime Expo 2024に出展」
※3 Glossom株式会社「スマートフォンでの情報収集に関する定点調査2023」