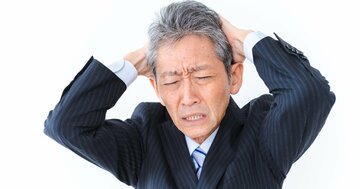相続税の非課税枠を使えないケース
国税 相続税の節税をするなら、亡くなった被相続人自身が、生命保険の被保険者(保険がかけられている人)であり、保険契約者(保険料負担者)になっていなければならないのでしたよね。
前田 はい。ここで注意が必要なのが、「相続税の対象になるけれど、非課税枠を使えない」というケースが2つあることです。
-
「相続人以外の人」が保険金の受取人に指定されていた場合
たとえば孫や相続人の配偶者など、相続人以外の人が保険金を受けとる場合は非課税枠を使えません。 -
「亡くなった人が被保険者ではない保険」が相続税の対象になる場合
たとえば、お父さんが、お母さんを被保険者にする生命保険をかけていて、お父さんが先に亡くなったような場合です。
保険金が出ないのに相続税がかかるケース
無知 ええっと、頭が混乱してきました……被保険者(保険がかけられている人)であるお母さんはまだ亡くなっていないので、保険金は出ないですよね。それでも相続税がかかってしまうのはひどくないですか?
前田 たしかに、まだ保険事故が起きていないので保険金は出ませんが、保険の"権利"としての価値があります。
たとえば無知さんがお父さんから、「10年後に満期になる定期預金」を相続したと考えてください。その定期預金は満期になるまで使えませんが、財産としての価値はありますよね。
亡くなった人が被保険者ではない保険も、同じようなイメージなのです。
まとめ:相続税対策に最適な生命保険とは?
国税 話をまとめると、相続税対策のためには、
・被相続人が保険契約者(保険料負担者)
・被相続人自身が被保険者(保険がかけられている人)
この2つの条件を満たす生命保険に入ることが重要です。
そのなかでも、「一時払い終身保険」が使い勝手がいい、ということですね。
前田 バッチリです!
相続税対策にならない保険って? … 誰が保険料を払って、誰が保険金を受けとるか?
POINT 相続税対策には被相続人が自分に保険をかけて自分で保険料を支払う一時払い終身保険がおすすめ
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。