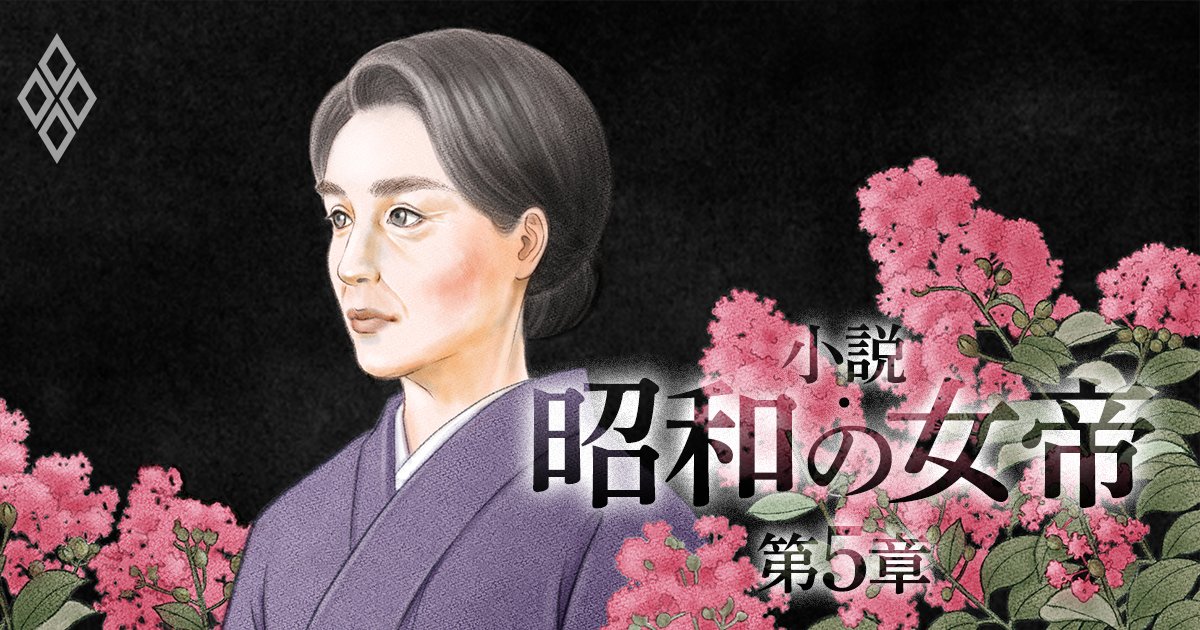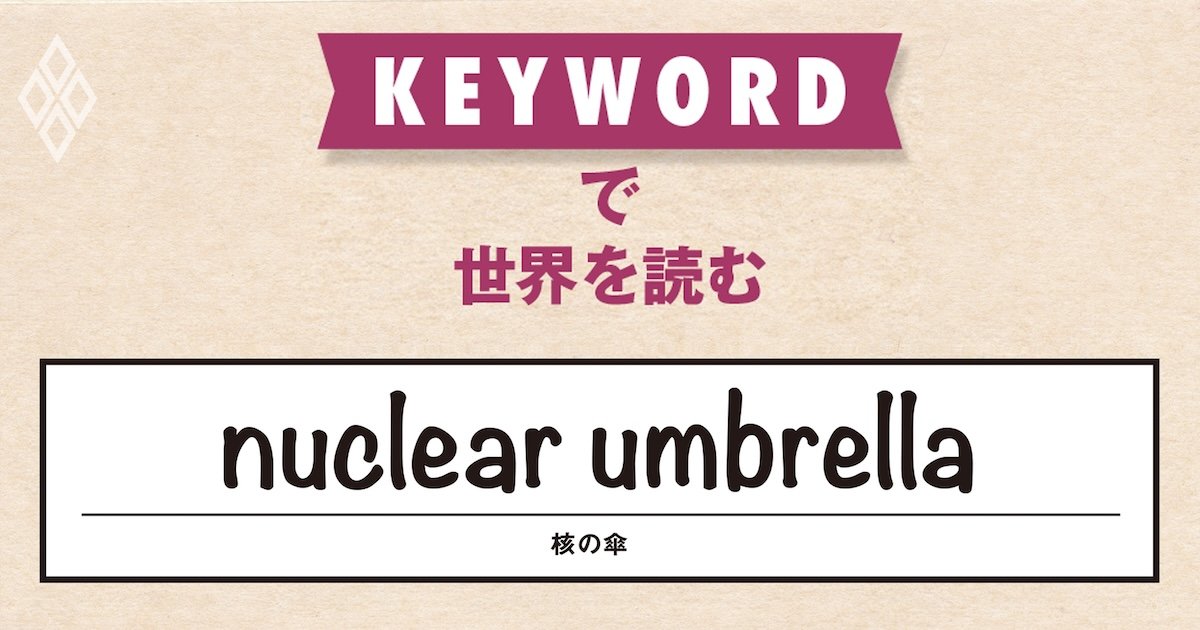孫正義と稲盛和夫の共通点
さらに、こうした企業には、競争性の低い学生やアルトリズム(利他性)スコアの高い学生が集まりやすいという傾向も明らかになった。成績(GPA)の高低とは無関係に、優秀な人材もまた、こうした理念に共鳴していた。つまり、社会的使命を持つ企業は、採用競争においても優位性を持つことができる。
職務設計の観点でも、完全な業務自律性は月給換算で約400ユーロ(約6万4000円)の価値があるとされ、異分野協働型のマルチディシプリンチームで働くことも、月285ユーロ(約4万5000円)分の付加価値として評価された。企業理念やチーム構成は、給与に匹敵するインセンティブになり得るのだ。
稲盛が説いた「動機の善」は、経営理念として美しいだけでなく、人材獲得・定着・モチベーション形成においても極めて合理的な経営戦略であった。理念を明確に掲げることは、単なる美辞麗句ではなく、企業の持続可能性を支える「見えない報酬」として機能していたのである。
1986年クリスマスの京セラ本社での交渉は、孫にとって印象深い経験ではあったが、すべての出発点だったとは言い切れない。孫はそれ以前から「事業を通じて社会を変える」という信念を持っていた。
稲盛との出会いは、その信念に哲学的な輪郭を与えるものとなった。孫は会社が大きくなり、社会的影響を持つにつれ、事業判断で「この動機は社会にとって本当に善か」という問いを意識的に抱くようになっていった。
2人はガチンコの交渉を通じて、お互いに経営者としての視座を確かめ合ったのかもしれない。孫は若きベンチャー経営者として、稲盛の哲学に敬意を払いながらも、自らの構想と熱意を真正面からぶつけた。
稲盛は経営者として真正面から応じた。意見の相違はあったが、「利益を求める姿勢」を前提としながら、「その動機が社会的に正当化されるかどうか」という視点に立脚していた。
理念に基づく企業経営は、情緒や理想に傾倒するものではなく、合理的な経営判断として機能し得る。
企業の成長は、収益の追求と社会の進歩が一致したときにこそ最大化される。孫正義と稲盛和夫の経営は、まさにその一致点を探し続けた結果として形づくられている。