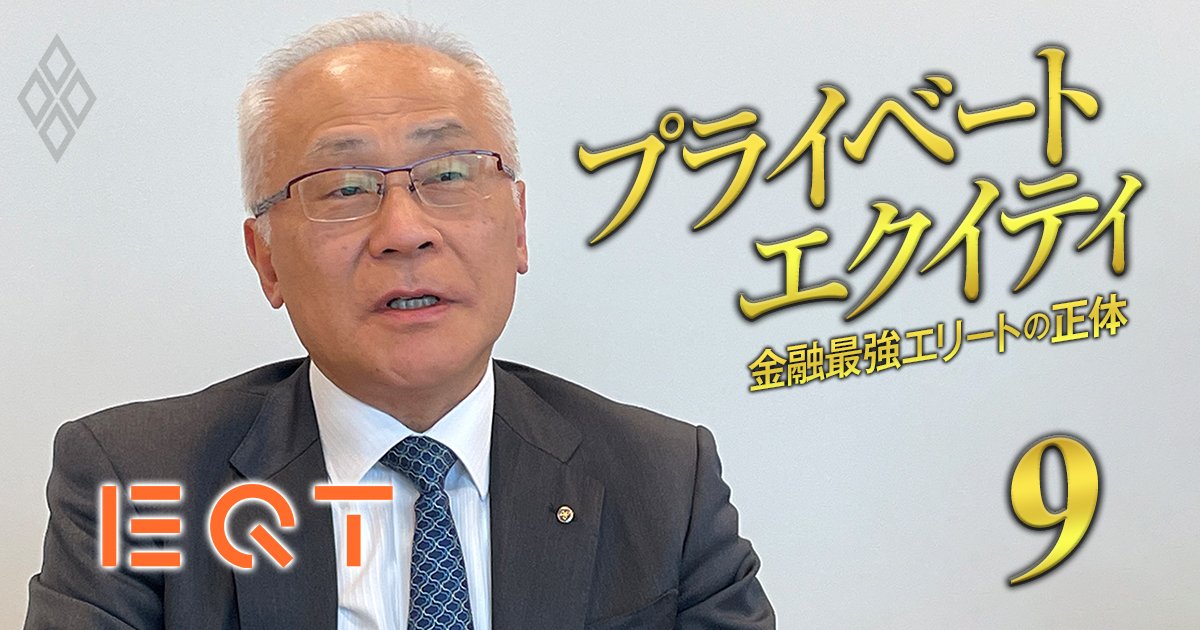もちろん、これはサントリー側もよくわかっている。トップが「財界の顔」として注目を集めることで、発言がチョキンと切り取られ、独り歩きして「炎上→不買運動」というのはサントリーにとって「お約束」ともいうべき展開なのだ。
わかりやすいのは、2代目社長の佐治敬三氏だ。1988年2月、大阪商工会議所会頭を務めていた佐治氏は、近畿商工会議所連合会で講演をした。そこで話題にしたのが「関西への遷都」だ。
バブル華やかなりし時代、東京の地価が急騰した当時の日本では「首都機能移転」が真剣に議論されていた。関西財界としてはもちろん、「首都は関西に」というムードが高まっており、佐治氏も講演でその必要性を訴えた。そこで、聴衆は「身内」ということや関西人特有のサービス精神から、同じく遷都に手を挙げていた東北をこんな風にディスってしまった。
「東北は熊襲の産地。文化的程度も極めて低い」
これをメディアが嗅ぎつける。1カ月ほど経過した後にTBSがこの発言を報じて、サントリーには批判が殺到。不買運動にまで発展、秋田県では県知事の指示により一部公共施設でサントリー商品を取り扱わなくなったほか、テレビCM出稿を見送らざるを得なくなったという。
いかがだろう。SNSのない時代の話ではあるが、やっていることは今の新浪会長の「炎上→不買運動」とほとんど変わらないのではないか。
佐治氏も新浪会長も、あくまで大阪商工会議所会頭や経済同友会代表幹事として「攻めた発言」をしている。地域経済や地域の企業を活性化させるためには時に威勢のいいアジテーション(扇動)をしなくてはいけないし、政治や行政へプレッシャーをかけるための「強気な発言」をしなくてはいけない。
しかし、それがチョキンと切り取られて報道をされるので、大衆は「サントリーの社長ってとんでもない野郎だな」と怒りが込み上げて、サントリーブランドへの憎悪が高まり、不買運動へと発展していく。